史上名高い“アルマダの海戦”の勃発前夜から終結に到るまでをエリザベス1世の視点から描いた2007年公開の本作は、1998年製作の映画“エリザベス”の続編として構想されました。
official web: http://www.elizabeththegoldenage.com/site/site.html
まず書き付けてしまえば、この監督、この主演によって本作品が撮られたことを絶賛しないわけにはいきません。というのも前作“エリザベス”は質的に非常に高い水準を達成しながらも、今日の映画を巡る状況下では続編製作が期待されるような作品とはとても思えなかったからです。主演のケイト・ブランシェットそのひとですら、続編製作の話に対しては当初から懐疑的でした。
しかし蓋を開けてみればどうでしょうか。個人的な好みから言えば、これほど緻密に練られたショットの連続する映画をしばらく観ていなかった気がします。印象に残るシーンがとにかく多い作品でした。
◆前作との違い
さて、本作は主要スタッフ・キャストがほぼ前作と共通し、ストーリーも重なるため‘続編’であることは確かなのですが、全体の構成はかなり違ったものに映りました。前作が女王として戴冠するまでの陰謀劇から“よき女王(Good Queen Bess)”として君臨するに至るまでを描いた通時的なつくりであったのに対し、本作ではスペイン無敵艦隊を駆逐した“アルマダの海戦”に時制を定め、劇中で進行するすべてのエピソードが開戦の瞬間へと収斂するまとまりのある構成になっていたのです。このため前作を観ている必要がまったくない仕上がりになったと同時に、全編の流れに振れ幅の大きな抑揚が生じ、前作よりもずっと観やすくなったとも言えそうです。
もし“歴史映画”という評価軸がありうるなら前作はまごうことなき傑作映画なのですが、その一方で一般の娯楽映画を期待する観客にとっては退屈に映るのも致し方ない面の多い作品でしたから、本作では尚更こうしたあたりに力点が置かれたのかもしれません。
◆ローリー卿と史実の再現性
エリザベスのかたわらで全編を通じてストーリーをきっちり締めていく役柄として、本作ではウォルター・ローリー卿が新たに登場します。史実での彼はイングランドで初めて新大陸へ植民団を派遣した人物として知られ、文化人としての評価も高いのですが、劇中で彼に与えられたヒーロー的な役割はこうした背景を飾りとした、男性が主人公の一般的な冒険活劇物におけるヒロイン役に相当するものがあります。導入部では宮廷の面々を前に新大陸の文物を紹介して未知の世界を傍目に置く当時の時代背景を描き出し、中盤以降では恋愛要素を絡めて主人公のエリザベスが精神的な象徴として王国に君臨していくきっかけをも用意します。おまけに二枚目貴族のローリー自らが単身で焼き討ち船を操り無敵艦隊に突撃するシーンまで登場するのですが、これはまあご愛敬といったところでしょう。商業映画としてはありがちでも、この監督の手付きとしては明らかに異様でかつ浮いていました。
かのフランシス・ドレイクと英国艦隊旗艦での軍議を共にするなど、クライマックスの海戦シーンにおけるローリー卿の獅子奮迅ぶりは劇場で観ていて唯一苦笑とともにやや興醒めした場面なのですが、あらためて考えるとこれだけの製作規模により撮られた作品でこの部分以外はほとんど違和感なく楽しめていたのがむしろ稀有なことに思えます。ローリー卿が女王と深い関係を築きながらも女王付きの女官を妊娠させて幽閉されるくだりなど、むしろ映画のために作られた挿話とみたほうが自然なくらいに全体のストーリーとよく馴染んでいました。
こうした史実の再現性を巡っては、9年前の前作で徹底的にこだわった挙げ句に舞台背景が複雑になり過ぎた反省を活かしてか、素材の削ぎ落としかたにも思い切ったものがありました。
たとえば前作での戴冠時、エリザベスは明確に「イングランド・アイルランド・及びフランスの王」という口上付きで即位しており、フランス人によるブリテン島の国家という中世イングランド王家の性格をきちんと踏まえていたのですが、スコットランドのメアリ女王とメアリの甥でエリザベスの婿候補でもあったアンジュー公とが完全にフランス語を母語とした会話を交わすシーンなども込みで、イギリス史に疎い観客にとっては恐らくかなり混乱の元となったはずです。しかし本作に登場するイングランド王朝は、まだ弱小ながらも確固としたイングランド人の意識をもった人々により運営されており、そのはじめから独立国家としてどう諸外国と渡り合うかが外交の争点として描かれました。
こうした違いはどちらが正しいかという話よりは個々人の歴史観の問題(程度の問題)なので、結果として両作品の間にこうした点で対照的な差異が生じたことは興味深いところです。素材の吟味を経た製作の過程でたまたま筋道が分かれただけで、意図した結果ではないと思いますが。
◆監督と見どころと俳優
ところで冒頭にも述べたように、本作は視覚的に強い印象を残すシーンが多いことでも特徴づけられる作品なのですが、この特徴の源泉として奇抜なアングルからのショットやシンボリックなオブジェの多用などが挙げられます。現存のセント・ポール寺院を使用したロケーション撮影による場面でも後代の建築部分を巧妙にかわしつつ、ものすごい独創的な位置から人物を映し出すことでそのひとの内面まで表現しきっているシーンがいくつもあり、ヴィジュアル面での見応えも存分にありました。
このような見た目の独創性には、シェーカル・カプール監督がインド映画の出身であることも大きく関係しているはずです。単にインド出身というだけではない異質さが随所に見られるのも、欧米の製作環境とは文脈の異なる場での経験が下地にあることを知れば納得がゆくというものです。また黒澤映画っぽいシーンが幾つもあるなと思ったら、本人かなりの黒澤マニアを自負するひとらしく。
もしこれから観るかたがいるなら、本編中に幾度も登場するイングランド王宮から覗く月影や、敵対するスペインの王フェリペ2世が眼差す蝋燭の炎の揺らめきが何を象徴しているかに注意を払いながら観ていくと、またべつの深みが味わえるはずです。
またこの作品の核にあるのは史実の正確な再現でもなければ海戦描写の迫真性でもなく、エリザベスが抱える魂の変容していく姿だと思います。肉体的な情動やそれに由来する怒りや嫉妬といった個人的な感情が、無敵艦隊が迫るなかで音を立てて削ぎ落とされていく過程の描写は圧巻と言わざるをえません。大海戦のさなかにあって、エリザベスは文字通りの“処女王(The Virgin Queen)”として急速に覚醒していきます。ローリー卿も女王の周りに起こる様々な陰謀劇も本作品ではすべての要素がこの変容の瞬間を描くために存在していると言っても過言ではないので、この点を始めから留意して観るのも面白いかもしれません。
さいごにキャスティングについても触れておきます。まず主演のケイト・ブランシェット。監督は彼女の演技を見て事前に考えていた演出法を幾度も変えたらしいのですが、それもそのはず。彼女がこの作品で見せる演技は、はっきり言って破格です。この名優にしてこの作品が主要な代表作として今後語り継がれるのは疑いのないところでしょう。ウォルター・ローリーを演じたクライヴ・オーウェンは、孤高の冒険者を演じてこれでもう何作品目なのでしょうか。知性と野性を兼ね備えたこの手の役柄は彼しかいないという性格俳優の地位をすっかり確立した観があります。ケイト・ブランシェット以外で前作に続いて登場する唯一の主要キャストにジェフリー・ラッシュ(“パイレーツ・オブ・カリビアン”のバルボッサ役)がいますが、彼もまた両作品で対照的な性格を見せ作品に深い余韻を与えました。“刺客の修道士”というダークな端役に前作ではダニエル・クレイグ(現在の“007”シリーズ主演)、本作ではリス・エヴァンスと渋目の大物俳優を起用しているのも両作品の見逃せないポイントになっています。
実はこの記事シリーズでは2年前に一度前作を扱おうと考え、作品の日本公開時にあたる今年初頭には本作を記事化しようとも思い、今回が都合3回目の思いつきにしてようやく実行に漕ぎつけました。大航海時代を背景とする良作映画という当記事シリーズのテーマのどまんなかをゆく一編なので、逆に腰が重くなっていたのですね。それだけに書き切れなかったこともかつてなく多いのですが、反面‘ようやく書けたか’という慎ましやかな達成感にも今ほのかにひたっているところです。良い意味で期待を裏切ってくれた、なかなかの好作品でした。
“Elizabeth: The Golden Age” by Shekhar Kapur / Cate Blanchett, Clive Owen, Geoffrey Rush, Samantha Morton, Abbie Cornish, Rhys Ifans / Remi Adefarasin [Cinematography] / Jill Bilcock [editing] / 114min / UK, France / 2007
official web: http://www.elizabeththegoldenage.com/site/site.html
まず書き付けてしまえば、この監督、この主演によって本作品が撮られたことを絶賛しないわけにはいきません。というのも前作“エリザベス”は質的に非常に高い水準を達成しながらも、今日の映画を巡る状況下では続編製作が期待されるような作品とはとても思えなかったからです。主演のケイト・ブランシェットそのひとですら、続編製作の話に対しては当初から懐疑的でした。
しかし蓋を開けてみればどうでしょうか。個人的な好みから言えば、これほど緻密に練られたショットの連続する映画をしばらく観ていなかった気がします。印象に残るシーンがとにかく多い作品でした。
◆前作との違い
さて、本作は主要スタッフ・キャストがほぼ前作と共通し、ストーリーも重なるため‘続編’であることは確かなのですが、全体の構成はかなり違ったものに映りました。前作が女王として戴冠するまでの陰謀劇から“よき女王(Good Queen Bess)”として君臨するに至るまでを描いた通時的なつくりであったのに対し、本作ではスペイン無敵艦隊を駆逐した“アルマダの海戦”に時制を定め、劇中で進行するすべてのエピソードが開戦の瞬間へと収斂するまとまりのある構成になっていたのです。このため前作を観ている必要がまったくない仕上がりになったと同時に、全編の流れに振れ幅の大きな抑揚が生じ、前作よりもずっと観やすくなったとも言えそうです。
もし“歴史映画”という評価軸がありうるなら前作はまごうことなき傑作映画なのですが、その一方で一般の娯楽映画を期待する観客にとっては退屈に映るのも致し方ない面の多い作品でしたから、本作では尚更こうしたあたりに力点が置かれたのかもしれません。
◆ローリー卿と史実の再現性
エリザベスのかたわらで全編を通じてストーリーをきっちり締めていく役柄として、本作ではウォルター・ローリー卿が新たに登場します。史実での彼はイングランドで初めて新大陸へ植民団を派遣した人物として知られ、文化人としての評価も高いのですが、劇中で彼に与えられたヒーロー的な役割はこうした背景を飾りとした、男性が主人公の一般的な冒険活劇物におけるヒロイン役に相当するものがあります。導入部では宮廷の面々を前に新大陸の文物を紹介して未知の世界を傍目に置く当時の時代背景を描き出し、中盤以降では恋愛要素を絡めて主人公のエリザベスが精神的な象徴として王国に君臨していくきっかけをも用意します。おまけに二枚目貴族のローリー自らが単身で焼き討ち船を操り無敵艦隊に突撃するシーンまで登場するのですが、これはまあご愛敬といったところでしょう。商業映画としてはありがちでも、この監督の手付きとしては明らかに異様でかつ浮いていました。
かのフランシス・ドレイクと英国艦隊旗艦での軍議を共にするなど、クライマックスの海戦シーンにおけるローリー卿の獅子奮迅ぶりは劇場で観ていて唯一苦笑とともにやや興醒めした場面なのですが、あらためて考えるとこれだけの製作規模により撮られた作品でこの部分以外はほとんど違和感なく楽しめていたのがむしろ稀有なことに思えます。ローリー卿が女王と深い関係を築きながらも女王付きの女官を妊娠させて幽閉されるくだりなど、むしろ映画のために作られた挿話とみたほうが自然なくらいに全体のストーリーとよく馴染んでいました。
こうした史実の再現性を巡っては、9年前の前作で徹底的にこだわった挙げ句に舞台背景が複雑になり過ぎた反省を活かしてか、素材の削ぎ落としかたにも思い切ったものがありました。
たとえば前作での戴冠時、エリザベスは明確に「イングランド・アイルランド・及びフランスの王」という口上付きで即位しており、フランス人によるブリテン島の国家という中世イングランド王家の性格をきちんと踏まえていたのですが、スコットランドのメアリ女王とメアリの甥でエリザベスの婿候補でもあったアンジュー公とが完全にフランス語を母語とした会話を交わすシーンなども込みで、イギリス史に疎い観客にとっては恐らくかなり混乱の元となったはずです。しかし本作に登場するイングランド王朝は、まだ弱小ながらも確固としたイングランド人の意識をもった人々により運営されており、そのはじめから独立国家としてどう諸外国と渡り合うかが外交の争点として描かれました。
こうした違いはどちらが正しいかという話よりは個々人の歴史観の問題(程度の問題)なので、結果として両作品の間にこうした点で対照的な差異が生じたことは興味深いところです。素材の吟味を経た製作の過程でたまたま筋道が分かれただけで、意図した結果ではないと思いますが。
◆監督と見どころと俳優
ところで冒頭にも述べたように、本作は視覚的に強い印象を残すシーンが多いことでも特徴づけられる作品なのですが、この特徴の源泉として奇抜なアングルからのショットやシンボリックなオブジェの多用などが挙げられます。現存のセント・ポール寺院を使用したロケーション撮影による場面でも後代の建築部分を巧妙にかわしつつ、ものすごい独創的な位置から人物を映し出すことでそのひとの内面まで表現しきっているシーンがいくつもあり、ヴィジュアル面での見応えも存分にありました。
このような見た目の独創性には、シェーカル・カプール監督がインド映画の出身であることも大きく関係しているはずです。単にインド出身というだけではない異質さが随所に見られるのも、欧米の製作環境とは文脈の異なる場での経験が下地にあることを知れば納得がゆくというものです。また黒澤映画っぽいシーンが幾つもあるなと思ったら、本人かなりの黒澤マニアを自負するひとらしく。
もしこれから観るかたがいるなら、本編中に幾度も登場するイングランド王宮から覗く月影や、敵対するスペインの王フェリペ2世が眼差す蝋燭の炎の揺らめきが何を象徴しているかに注意を払いながら観ていくと、またべつの深みが味わえるはずです。
またこの作品の核にあるのは史実の正確な再現でもなければ海戦描写の迫真性でもなく、エリザベスが抱える魂の変容していく姿だと思います。肉体的な情動やそれに由来する怒りや嫉妬といった個人的な感情が、無敵艦隊が迫るなかで音を立てて削ぎ落とされていく過程の描写は圧巻と言わざるをえません。大海戦のさなかにあって、エリザベスは文字通りの“処女王(The Virgin Queen)”として急速に覚醒していきます。ローリー卿も女王の周りに起こる様々な陰謀劇も本作品ではすべての要素がこの変容の瞬間を描くために存在していると言っても過言ではないので、この点を始めから留意して観るのも面白いかもしれません。
さいごにキャスティングについても触れておきます。まず主演のケイト・ブランシェット。監督は彼女の演技を見て事前に考えていた演出法を幾度も変えたらしいのですが、それもそのはず。彼女がこの作品で見せる演技は、はっきり言って破格です。この名優にしてこの作品が主要な代表作として今後語り継がれるのは疑いのないところでしょう。ウォルター・ローリーを演じたクライヴ・オーウェンは、孤高の冒険者を演じてこれでもう何作品目なのでしょうか。知性と野性を兼ね備えたこの手の役柄は彼しかいないという性格俳優の地位をすっかり確立した観があります。ケイト・ブランシェット以外で前作に続いて登場する唯一の主要キャストにジェフリー・ラッシュ(“パイレーツ・オブ・カリビアン”のバルボッサ役)がいますが、彼もまた両作品で対照的な性格を見せ作品に深い余韻を与えました。“刺客の修道士”というダークな端役に前作ではダニエル・クレイグ(現在の“007”シリーズ主演)、本作ではリス・エヴァンスと渋目の大物俳優を起用しているのも両作品の見逃せないポイントになっています。
実はこの記事シリーズでは2年前に一度前作を扱おうと考え、作品の日本公開時にあたる今年初頭には本作を記事化しようとも思い、今回が都合3回目の思いつきにしてようやく実行に漕ぎつけました。大航海時代を背景とする良作映画という当記事シリーズのテーマのどまんなかをゆく一編なので、逆に腰が重くなっていたのですね。それだけに書き切れなかったこともかつてなく多いのですが、反面‘ようやく書けたか’という慎ましやかな達成感にも今ほのかにひたっているところです。良い意味で期待を裏切ってくれた、なかなかの好作品でした。
“Elizabeth: The Golden Age” by Shekhar Kapur / Cate Blanchett, Clive Owen, Geoffrey Rush, Samantha Morton, Abbie Cornish, Rhys Ifans / Remi Adefarasin [Cinematography] / Jill Bilcock [editing] / 114min / UK, France / 2007
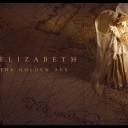

コメント
予告編やCMですでに娯楽映画の片鱗が見えていたからです。明らかに史実よりもドラマ性を優先した映画であることは明白でしたから。
しかしgoodbyeさんの感想にあるように、その点を差し引いても映画としての出来がいいのなら今度見ようかなと思ってます。ケイト・ブランシェットは好きですしね。個人的には英と西をどこまで公平に描いているかが気になります。
まあ、映画のタイトル・インド出身監督で英贔屓ないわけないでしょうがw
これ、まったくの誤解です。なぜそう誤読されたかを考えたのですが、もし前作を「通時的なつくり」とした部分が原因なら、これはあくまでプロット構成上の特徴について述べています。描かれる内容とは関係ないです。
わたしには前作も「明らかに史実よりもドラマ性を優先」しまくっているように思えますが、両者が対概念でないことは当然として「ドラマ性より史実を優先」するような性格の映画って確かにありますね。けれど少なくともわたしが過去に観たその種の作品は多くが糞味噌で、ドキュメンタリー作品なりナショナルジオグラフィックTVなりを観ていたほうがいいという代物ばかりでした。
他に一つ思ったのは「史実」や「公平」という単語にどのような思い入れがあるかたにせよ、せっかくケイト・ブランシェットが好きなのにこれらを理由に彼女の出演作を敬遠するのはもったいないんじゃないのー、ということです。単に好き具合の問題かもだけど。
プロット構成上「通時的な作り」が、こと歴史映画については私の好みなんです。前作ですら内容が「明らかに史実よりもドラマ性を優先」していたのはまったく同感ですが、それでも映画的な盛り上がりを抑え、説明不足なプロローグもまとまりのないラストも歴史の大流の一部を切り取った感があって好きでした。それを狙ったかどうかは不明ですが、結果として歴史そのものを通時的な作りで再現する方式の映画になっていたと思うのです。内容が史実とは離れていても、です。(多分いろいろ失敗した結果としてそうなっただけだとは思いますが)
なので今作ゴールデンエイジに期待していることは、そういった手法を好む私にすら面白いと思わせるストーリー展開・俳優の演技・演出があるかどうかです。言ってみれば「忠臣蔵」的な映画になっているか、でしょうか。歴史を題材にしつつも娯楽作品として高レベルの作品に仕上がっているのならば見たい、というわけですね。歴史映画(と私が定義するもの)ではないと割り切れば傑作と思えるかです。
goodbyeさんの記事を読む限りその点は心配なさそうかな・・・と思ってます。
もしかしたらgoodbyeさんが過去に糞味噌と評価した作品が私にとって「歴史映画として面白い」のかもしれません・・・。