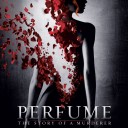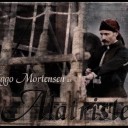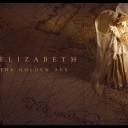Job Description 18: 天文学者 【アレクサンドリア】
2011年3月28日 就職・転職
震災当日観るはずだった映画“アレクサンドリア”、ようやく観られたので久々に映画の感想書いてみます。
映画の舞台はローマ帝国末期、かのアレクサンドリア図書館や世界の七不思議の一つ、ファロス島の大灯台が現役だった時代のメトロポリス、アレクサンドリアです。主人公は実在した哲学者のヒュパティアで、彼女は数学者・天文学者としても当代一の才能があったと推測されています。“推測”と書いたのは、彼女の著作は現在すべて失われてしまっており、彼女に宛てられた手紙や周辺の学者・政治家たちの評価に拠るしか人となりを知る術がないためです。
この知的に研ぎ澄まされていてかつミステリアスな人物像を、主演のレイチェル・ワイズは見事に演じ切っていました。この女優の笑顔には、見る者の視線を引き込んで表情の内に束の間滞留させるような深みがあり、何かしら精神的に傷を負った役柄を演じさせると抜群に光るのですが、今回の作品では男中心の政治学問の現場や、迫り来る宗教的狂騒との緊張関係が全編にわたって続くため、まさにレイチェル・ワイズの長所ダダ漏れ作品になっていました。
当初この映画の存在を知ったとき、これは観ようと即決した最大の理由は、キリスト教徒によるアレクサンドリア図書館への襲撃が描かれていると伝えられていたからでした。これまで欧米の映画がキリスト教徒の集団を悪く描くときはたいてい、それでもキリスト教側にも一定の理を確保し、迫害する相手を文明の価値として露骨に下に置くような構図がありました。しかしこの時代随一のメトロポリスであったアレクサンドリアにおいて、果たしてそのような描き方がどれだけ可能なのか、そこに興味があったんですね。そして監督が“オープン・ユア・アイズ”や“海を飛ぶ夢”のアレハンドロ・アメナバールのスペイン映画、この2点だけでもうどんな失敗作だとしても入場料分の見応えは確信できました。
さて問題のキリスト教徒による破壊行為。生々しい暴力シーンそのものは抑えに抑えられていましたが、それだけに起きている出来事の凶暴性が深く響いてくるものがありました。図書館の門がいまにも暴徒たちに破られるという騒乱のさなかにあって、一つでも多くの書巻を持ち出したいけれど万巻の書に対して人手が足りなさすぎるなか、鋭い悲痛に身を裂かれながらも弟子たちに囲まれた自分が気丈に動かなくては救える書巻も救えなくなるという葛藤に苦しむレイチェル・ワイズの演技には、自分でも意外なほどに感情移入を誘われてしまいました。観客席で涙を滲ませる程度ならあるにしても、腰を落ち着けてそれを観ているのがつらいというほどの感情に襲われたのは稀有の体験でした。腕からこぼれ落ちてしまった書巻の一つ一つに、複数の賢者が一生を割いて見い出した叡智が詰まっている。それなのに、どうしても救えない。
ところでタイトルの“アレクサンドリア”、実はこれ日本限定の国内向けタイトルで、世界的には“Agora”として公開されているんですね。アゴラは古代ギリシアのポリスにおける広場や、そこで開かれる市民集会の意として日本でもよく知られていますね。古代ギリシアにルーツがあるだけあって、英語のほか多くのヨーロッパ系言語で同じ意味で用いられています。しかしこのタイトルの抱える含蓄はもう少し広く、スペイン語では名詞の“広場”のほか、動詞になるとagorarで“[迷信的に、主に災難を]予言する”、ポルトガル語では“現在”という意味を持っています。こう考えると、この作品の立ち位置がもう一段深まって見えてくる気がします。狂信的排他主義。理に沿わぬ暴動。無自覚の女性蔑視。通念に抗って己を貫く困難。主人公ヒュパティアの排斥を指示したアレクサンドリアの総司教キュリロスはその後、ローマ教会によって聖人に列せられています。考えさせられます。表出されているのはあくまで、“いま” なんですよね。その意味でも、かなりの名タイトル。
映画のなかでは、街の通りや広場のシーンから視点が上空へとあがり、ナイルや地中海を俯瞰したあと雲を抜け宇宙に浮かぶ地球の映像にまで引いていき、また元に戻るという視覚的往還が幾度か繰り返されます。このとき見せているアレクサンドリア周辺の地理や星座の配置は、精密な考証と計算を経て生み出されたCGによるもので現存しない姿です。それはそれで見応えのあるものだったし、観客の内面において人間の営みをミクロなものとして対象化させる効果を狙った監督の意図も巧く表現し切れていると思うのですが、ふとその地球大まで引いた映像のなかで地球が半回転して、日本列島の東北部をクローズアップしてゆくと、そこにあるはずのない1600年後の福島第一原発から伸びる白煙が映り込む。そんなシーンを連想せずにはいられませんでした。当分のあいだはそうやって、体験するあらゆるものの基底に震災の影が忍び入るような日々が続くのかもしれません。何年か、あるいはさらに。
"Agora" by Alejandro Amenabar / Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac, Ashraf Barhom / Xavi Gimenez [cinematography] / Guy Hendrix Dyas [production design] / Dario Marianelli [music performer] / 127min / Spain / 2009
映画の舞台はローマ帝国末期、かのアレクサンドリア図書館や世界の七不思議の一つ、ファロス島の大灯台が現役だった時代のメトロポリス、アレクサンドリアです。主人公は実在した哲学者のヒュパティアで、彼女は数学者・天文学者としても当代一の才能があったと推測されています。“推測”と書いたのは、彼女の著作は現在すべて失われてしまっており、彼女に宛てられた手紙や周辺の学者・政治家たちの評価に拠るしか人となりを知る術がないためです。
この知的に研ぎ澄まされていてかつミステリアスな人物像を、主演のレイチェル・ワイズは見事に演じ切っていました。この女優の笑顔には、見る者の視線を引き込んで表情の内に束の間滞留させるような深みがあり、何かしら精神的に傷を負った役柄を演じさせると抜群に光るのですが、今回の作品では男中心の政治学問の現場や、迫り来る宗教的狂騒との緊張関係が全編にわたって続くため、まさにレイチェル・ワイズの長所ダダ漏れ作品になっていました。
当初この映画の存在を知ったとき、これは観ようと即決した最大の理由は、キリスト教徒によるアレクサンドリア図書館への襲撃が描かれていると伝えられていたからでした。これまで欧米の映画がキリスト教徒の集団を悪く描くときはたいてい、それでもキリスト教側にも一定の理を確保し、迫害する相手を文明の価値として露骨に下に置くような構図がありました。しかしこの時代随一のメトロポリスであったアレクサンドリアにおいて、果たしてそのような描き方がどれだけ可能なのか、そこに興味があったんですね。そして監督が“オープン・ユア・アイズ”や“海を飛ぶ夢”のアレハンドロ・アメナバールのスペイン映画、この2点だけでもうどんな失敗作だとしても入場料分の見応えは確信できました。
さて問題のキリスト教徒による破壊行為。生々しい暴力シーンそのものは抑えに抑えられていましたが、それだけに起きている出来事の凶暴性が深く響いてくるものがありました。図書館の門がいまにも暴徒たちに破られるという騒乱のさなかにあって、一つでも多くの書巻を持ち出したいけれど万巻の書に対して人手が足りなさすぎるなか、鋭い悲痛に身を裂かれながらも弟子たちに囲まれた自分が気丈に動かなくては救える書巻も救えなくなるという葛藤に苦しむレイチェル・ワイズの演技には、自分でも意外なほどに感情移入を誘われてしまいました。観客席で涙を滲ませる程度ならあるにしても、腰を落ち着けてそれを観ているのがつらいというほどの感情に襲われたのは稀有の体験でした。腕からこぼれ落ちてしまった書巻の一つ一つに、複数の賢者が一生を割いて見い出した叡智が詰まっている。それなのに、どうしても救えない。
ところでタイトルの“アレクサンドリア”、実はこれ日本限定の国内向けタイトルで、世界的には“Agora”として公開されているんですね。アゴラは古代ギリシアのポリスにおける広場や、そこで開かれる市民集会の意として日本でもよく知られていますね。古代ギリシアにルーツがあるだけあって、英語のほか多くのヨーロッパ系言語で同じ意味で用いられています。しかしこのタイトルの抱える含蓄はもう少し広く、スペイン語では名詞の“広場”のほか、動詞になるとagorarで“[迷信的に、主に災難を]予言する”、ポルトガル語では“現在”という意味を持っています。こう考えると、この作品の立ち位置がもう一段深まって見えてくる気がします。狂信的排他主義。理に沿わぬ暴動。無自覚の女性蔑視。通念に抗って己を貫く困難。主人公ヒュパティアの排斥を指示したアレクサンドリアの総司教キュリロスはその後、ローマ教会によって聖人に列せられています。考えさせられます。表出されているのはあくまで、“いま” なんですよね。その意味でも、かなりの名タイトル。
映画のなかでは、街の通りや広場のシーンから視点が上空へとあがり、ナイルや地中海を俯瞰したあと雲を抜け宇宙に浮かぶ地球の映像にまで引いていき、また元に戻るという視覚的往還が幾度か繰り返されます。このとき見せているアレクサンドリア周辺の地理や星座の配置は、精密な考証と計算を経て生み出されたCGによるもので現存しない姿です。それはそれで見応えのあるものだったし、観客の内面において人間の営みをミクロなものとして対象化させる効果を狙った監督の意図も巧く表現し切れていると思うのですが、ふとその地球大まで引いた映像のなかで地球が半回転して、日本列島の東北部をクローズアップしてゆくと、そこにあるはずのない1600年後の福島第一原発から伸びる白煙が映り込む。そんなシーンを連想せずにはいられませんでした。当分のあいだはそうやって、体験するあらゆるものの基底に震災の影が忍び入るような日々が続くのかもしれません。何年か、あるいはさらに。
"Agora" by Alejandro Amenabar / Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac, Ashraf Barhom / Xavi Gimenez [cinematography] / Guy Hendrix Dyas [production design] / Dario Marianelli [music performer] / 127min / Spain / 2009
18世紀前半、パリの最貧区に超人的な嗅覚をもった男の子が生まれ落ちます。その天性の才能はやがて、青年期のある夜に意図せず殺してしまった少女の香りによって昇華され、そこから彼の人生は‘許されざる’疾走を始めてゆきます。
公式HP日本版: http://perfume.gyao.jp/ (予告編動画あり)
この映画をめぐっては2007年の日本公開時、主に3つのエピソードによって話題になりました。ひとつは事前に放送された作品のテレビCMが、750人の裸体によるラヴシーンという衝撃的な内容からクレームによって中止されたり、放送を拒否したテレビ局もあったというエピソード。もうひとつはスピルバーグやマーティン・スコセッシといった名だたる巨匠たちが映画化を熱望しながらも、原作者の拒絶によって果たされなかったこと。そして何より、‘匂い’の主題化という難題に成功した稀有の作品であること。
◆匂いという深淵
この‘匂い’の映像化こそがこの作品の肝なのですが、匂いが攪拌され、拡散していく様を光の明滅や風などによって表現する手法には極めて独創的なものがあり、観ていて唸らされるものがありました。主人公がただひたすらにその特異な嗅覚に駆られ、翻弄されることによってのみ己の人生を蕩尽させてゆくという筋書きへの説得力もまた、この匂いの演出によって堅固に下支えされています。反対に、異常犯罪者をメインに据えた映画にありがちな‘言葉による心理描写’を一切排した展開は、ある種爽快ですらありました。
そこであらためて気づいたのですが、できるだけ多くの観客の感情移入を誘う必要がある商業映画のプロットに、共感不能の動機を抱えているからこそ結果的に異常犯罪者として屹立してしまった人間の心理描写を当てることは本来、構造的にかなり矛盾しているのですよね。たとえばハリウッドのわかりやすい勧善懲悪はこの矛盾を思考停止的に看過するための便利な‘お約束’でもあったわけですが、製作主体の多国籍化が進んだ近年どこにおいてもそうした製作手法は通用しにくくなってきたようです。
ここで映画前半の舞台である18世紀前半のパリについて少し言及しておくと、世紀の初頭に没した太陽王ルイ14世による散財などによってフランスの経済は低迷し、農村からの流入による人口増加で都市は極度に不衛生化していました。なかでもこの主人公が生まれたのは肥大化した都市の最下層に横たわるスラムですから、その悪臭に満ちた生活世界の汚さは本編の冒頭でもこれでもかというほど執拗に再現されています。
民がみな貧しく、非情なまでにサブスタンシャル(≒物質的,即物的)な原理のみが支配するその世界で、死とつねに隣り合わせの日々を生き抜いてきた彼にカトリックの恩寵はほど遠く、また当時上流社会を風靡した啓蒙主義の光が差し込むはずもなく、従ってそもそも21世紀のわたしたちが共感しうるモラル観念など彼のうちには育つ理由がなかったわけです。そのあたりにミステリアスな起源を匂わせないことも、異常犯罪を描いた作品には珍しいことかもしれません。たとえば“羊たちの沈黙”や“ハンニバル”であれば怪物的に明晰なレクター博士に対し、若きFBI訓練生のクラリスが観客側の共感装置として働くのに比べると、この作品では圧倒的な断絶が維持され続け、感情移入の契機が奪われたままストーリーは進行していきます。
◆感覚の果てなるもの
こうした断絶は、作品世界においては主人公の凶行に対する貴族社会の動揺によって表現されているとも言えるのですが、そうしたなかで唯一冷静に犯人像を割り出していく貴族の役に名優アラン・リックマンが当てられているなど、この作品は配役の妙にも非常に卓越したものがあり見逃せないところです。
天賦の才を持て余していた主人公に、香水の調合法という体系化された手段を与える、出演時間は短いながらとても重要な調合師の役にはかのダスティン・ホフマンが起用されています。恐らくは超高額なギャラをもピンポイントの端役に注ぎ込んだこの冒険的キャスティングは見事に功を奏しており、その短いシーンでダスティン・ホフマンが見せる‘嗅ぎ分ける’演技の巧みさは秀逸というほかありません。またオレンジの花やクローブ(丁子)、ムスク(麝香)といった香水の材料を判別していく際にホフマンが見せる、ハンカチを揺らせたあとに広がる空気を嗅ぎとっていく仕草は、終盤の問題のシーンの伏線としても演出上かなり重要な機能を果たしています。
この作品の制作を担当したベルント・アイヒンガーは、実は当記事シリーズでは既出の“薔薇の名前”のプロデューサーでもあります。“薔薇の名前”撮影時にはその辣腕ぶりが伝説ともなった彼ですが、本作においても時代考証へのこだわりや舞台美術の徹底ぶりは健在でした。監督のトム・ティクヴァは、実験性と娯楽性を兼ね備えた意欲作“ラン・ローラ・ラン”(Lola rennt, 1998)の監督としてすでに知られていましたが、本作はその先進性においても彼の出世作を凌ぎました。巨額の制作資金が投じられてなお実験的精神を盛り込めたのは、それ自体が制作陣の協働による稀有の達成と言えるでしょう。
またBGMをサイモン・ラトル指揮のベルリン・フィルハーモニー管弦楽団が担当していることも特筆に値します。彼らの音楽が作品の質にどれだけ作用しているかは映画を実際に観てもらうしかありません。会話以外のパートでほぼ常時流れ続ける調べの高い表現性には全編にわたって淀みがなく、決定的に効いています。
ともすればセンセーショナルなシーンばかりが話題を集めがちなのは、一般に流通する映画評としてはやむを得ないところもあるでしょう。しかし衝撃のラストとして語られがちな終盤の群衆シーンは、観てしまえば明らかなのだけれど実際にはラストではないんですね。個人的にはそのあとにある本当のラストシーンのほうが色々な意味で感銘を受けたのですが、これについてはネタバレになりかねないため詳述せずにおこうと思います。
ただこのとき主人公が感得していたであろうものに巡らせてしまう想像のうちに広がる色彩と、このきわだった異様さを湛える作品があとに残した余韻のぬめりとした触感は、わたしのなかで相異なる感覚のあいだにどこか通じる同じ波長、いわば共感覚的とでもいうべき近種の味わいにくるまれた何かでした。映画のなかで幾度か再帰的に挿入されるシーンにおいて、殺してしまった少女の乳房の香りを手のひらで必死に掬いとる主人公がその後の生涯をかけ真に追い求めていたものは、あるいは‘究極の匂い’などではなかったのかもしれません。
"Perfume: The Story of a Murderer" by Tom Tykwer / Ben Whishaw, Alan Rickman, Dustin Hoffman, Karoline Herfurth, Rachel Hurd-Wood, John Hurt / Bernd Eichinger [producer] / Patrick Süskind [book author] / Berliner Philharmoniker [music performer] / 147min / France, Germany, Spain / 2006
公式HP日本版: http://perfume.gyao.jp/ (予告編動画あり)
この映画をめぐっては2007年の日本公開時、主に3つのエピソードによって話題になりました。ひとつは事前に放送された作品のテレビCMが、750人の裸体によるラヴシーンという衝撃的な内容からクレームによって中止されたり、放送を拒否したテレビ局もあったというエピソード。もうひとつはスピルバーグやマーティン・スコセッシといった名だたる巨匠たちが映画化を熱望しながらも、原作者の拒絶によって果たされなかったこと。そして何より、‘匂い’の主題化という難題に成功した稀有の作品であること。
◆匂いという深淵
この‘匂い’の映像化こそがこの作品の肝なのですが、匂いが攪拌され、拡散していく様を光の明滅や風などによって表現する手法には極めて独創的なものがあり、観ていて唸らされるものがありました。主人公がただひたすらにその特異な嗅覚に駆られ、翻弄されることによってのみ己の人生を蕩尽させてゆくという筋書きへの説得力もまた、この匂いの演出によって堅固に下支えされています。反対に、異常犯罪者をメインに据えた映画にありがちな‘言葉による心理描写’を一切排した展開は、ある種爽快ですらありました。
そこであらためて気づいたのですが、できるだけ多くの観客の感情移入を誘う必要がある商業映画のプロットに、共感不能の動機を抱えているからこそ結果的に異常犯罪者として屹立してしまった人間の心理描写を当てることは本来、構造的にかなり矛盾しているのですよね。たとえばハリウッドのわかりやすい勧善懲悪はこの矛盾を思考停止的に看過するための便利な‘お約束’でもあったわけですが、製作主体の多国籍化が進んだ近年どこにおいてもそうした製作手法は通用しにくくなってきたようです。
ここで映画前半の舞台である18世紀前半のパリについて少し言及しておくと、世紀の初頭に没した太陽王ルイ14世による散財などによってフランスの経済は低迷し、農村からの流入による人口増加で都市は極度に不衛生化していました。なかでもこの主人公が生まれたのは肥大化した都市の最下層に横たわるスラムですから、その悪臭に満ちた生活世界の汚さは本編の冒頭でもこれでもかというほど執拗に再現されています。
民がみな貧しく、非情なまでにサブスタンシャル(≒物質的,即物的)な原理のみが支配するその世界で、死とつねに隣り合わせの日々を生き抜いてきた彼にカトリックの恩寵はほど遠く、また当時上流社会を風靡した啓蒙主義の光が差し込むはずもなく、従ってそもそも21世紀のわたしたちが共感しうるモラル観念など彼のうちには育つ理由がなかったわけです。そのあたりにミステリアスな起源を匂わせないことも、異常犯罪を描いた作品には珍しいことかもしれません。たとえば“羊たちの沈黙”や“ハンニバル”であれば怪物的に明晰なレクター博士に対し、若きFBI訓練生のクラリスが観客側の共感装置として働くのに比べると、この作品では圧倒的な断絶が維持され続け、感情移入の契機が奪われたままストーリーは進行していきます。
◆感覚の果てなるもの
こうした断絶は、作品世界においては主人公の凶行に対する貴族社会の動揺によって表現されているとも言えるのですが、そうしたなかで唯一冷静に犯人像を割り出していく貴族の役に名優アラン・リックマンが当てられているなど、この作品は配役の妙にも非常に卓越したものがあり見逃せないところです。
天賦の才を持て余していた主人公に、香水の調合法という体系化された手段を与える、出演時間は短いながらとても重要な調合師の役にはかのダスティン・ホフマンが起用されています。恐らくは超高額なギャラをもピンポイントの端役に注ぎ込んだこの冒険的キャスティングは見事に功を奏しており、その短いシーンでダスティン・ホフマンが見せる‘嗅ぎ分ける’演技の巧みさは秀逸というほかありません。またオレンジの花やクローブ(丁子)、ムスク(麝香)といった香水の材料を判別していく際にホフマンが見せる、ハンカチを揺らせたあとに広がる空気を嗅ぎとっていく仕草は、終盤の問題のシーンの伏線としても演出上かなり重要な機能を果たしています。
この作品の制作を担当したベルント・アイヒンガーは、実は当記事シリーズでは既出の“薔薇の名前”のプロデューサーでもあります。“薔薇の名前”撮影時にはその辣腕ぶりが伝説ともなった彼ですが、本作においても時代考証へのこだわりや舞台美術の徹底ぶりは健在でした。監督のトム・ティクヴァは、実験性と娯楽性を兼ね備えた意欲作“ラン・ローラ・ラン”(Lola rennt, 1998)の監督としてすでに知られていましたが、本作はその先進性においても彼の出世作を凌ぎました。巨額の制作資金が投じられてなお実験的精神を盛り込めたのは、それ自体が制作陣の協働による稀有の達成と言えるでしょう。
またBGMをサイモン・ラトル指揮のベルリン・フィルハーモニー管弦楽団が担当していることも特筆に値します。彼らの音楽が作品の質にどれだけ作用しているかは映画を実際に観てもらうしかありません。会話以外のパートでほぼ常時流れ続ける調べの高い表現性には全編にわたって淀みがなく、決定的に効いています。
ともすればセンセーショナルなシーンばかりが話題を集めがちなのは、一般に流通する映画評としてはやむを得ないところもあるでしょう。しかし衝撃のラストとして語られがちな終盤の群衆シーンは、観てしまえば明らかなのだけれど実際にはラストではないんですね。個人的にはそのあとにある本当のラストシーンのほうが色々な意味で感銘を受けたのですが、これについてはネタバレになりかねないため詳述せずにおこうと思います。
ただこのとき主人公が感得していたであろうものに巡らせてしまう想像のうちに広がる色彩と、このきわだった異様さを湛える作品があとに残した余韻のぬめりとした触感は、わたしのなかで相異なる感覚のあいだにどこか通じる同じ波長、いわば共感覚的とでもいうべき近種の味わいにくるまれた何かでした。映画のなかで幾度か再帰的に挿入されるシーンにおいて、殺してしまった少女の乳房の香りを手のひらで必死に掬いとる主人公がその後の生涯をかけ真に追い求めていたものは、あるいは‘究極の匂い’などではなかったのかもしれません。
"Perfume: The Story of a Murderer" by Tom Tykwer / Ben Whishaw, Alan Rickman, Dustin Hoffman, Karoline Herfurth, Rachel Hurd-Wood, John Hurt / Bernd Eichinger [producer] / Patrick Süskind [book author] / Berliner Philharmoniker [music performer] / 147min / France, Germany, Spain / 2006
Job Description 16: 熟練剣士 【アラトリステ】
2009年1月21日 就職・転職 コメント (6)
17世紀前半、スペインは隣国ポルトガルを併合し、アルマダの海戦に敗れつつもいまだ世界の覇権を掌中に収めていました。しかしフランドルでのオランダとの戦争はいつまでも絶えることがなく(八十年戦争)、やがて西仏戦争が勃発、カタルーニャやポルトガルでは大規模な反乱も起きるなど、その繁栄には少しずつ翳りが差し始めます。スペイン映画“アラトリステ”では、こうした時代のイベリア半島を駆け抜けた一人の剣士の生涯が描かれました。
公式HP: http://www.alatriste.jp/ (予告編は一見推奨)
主人公アラトリステは、戦時には前線に赴き、平時には貴族から暗殺依頼を請け負うなどして糊口をしのぐ暮らしに自足する男でした。しかしその研ぎ澄まされた技量や直情的な生き様は自然に仲間からの信頼を集め、王国一の女優に愛され、国を牛耳る貴族たちから一目置かれるようになります。やがて運命は彼を素朴な剣士稼業から引きはがし、時には国際情勢を揺るがすような権謀術数の渦中にも巻き込んでゆきます。映画はこうして展開される彼の波乱万丈の人生を、視覚的にもとても凝った演出によって見せてくれる、期待値以上に贅沢な作品に仕上がっていました。
◆原作と映画
原作は同タイトルの小説『アラトリステ(El capitán Alatriste)』。全6巻からなるこの小説は世界的ベストセラーで、数十カ国で読まれているようです。扱う時代的に言うならば池波正太郎の剣客物や司馬遼太郎等の戦国物のラテン版といったところでしょうか。著者のアルトゥーロ・ペレス=レベルテ(Arturo Pérez-Reverte)は元新聞記者で、国営TV局の戦場特派員の経歴もあるといいますから、そうした生の戦場体験が活かされていることも恐らくヒットの理由にあるのでしょう。
映画では一応この全6巻のエピソードが集約的に描かれています。「一応」と書いたのは、わたし自身は原作を読んでおらず、2時間前後の映画の尺に収めるにはうち1作か2作程度のエピソードを重点的に扱うのが限界だろうと推測するからです。そして実際この点に関しては、作品を観てややエピソードを詰め込み過ぎているかなあという感想も持ちました。パーツパーツは良いのに全体として過重気味なのが逆に作品を薄くしていまっている印象は、同様に原作が超長編の“グリーンマイル(The Green Mile) ”[S.キング原作, トム・ハンクス主演, 1998]を思い起こしました。
また、制作側はまずスペイン国内での大ヒットを目論んで撮ったはずですから理解はできるのですが、たとえばスペイン史に疎い日本の観客などには前後のつながりが意味不明に映るだろうと思う箇所を散見したのも気になりました。
これは上杉謙信と武田信玄、織田信長と徳川家康の関係くらい常識的に知っているだろうという前提のもとで撮られた正月の戦国ドラマを、字幕だけ付けて「さあ楽しめ」とジャマイカ人やマサイ族に観せるようなものに近く、どう考えても無理があります。なのでこの記事をきっかけにこれから“アラトリステ”を観ようと思ったかたがもしいらしたら、あらかじめスペイン史年表を少しおさらいしておくと良いかもしれません。
ところでこの原作小説、日本ではあまりというか、ベストセラー書籍というニュアンスではまったく話題になっていないと思いますが、文学に限らず文化全般においてスペイン語圏の作品は日本ではあまり普及しないイメージがありますね。文化的な相性なのか、商業構造的な制約によるのかはわかりませんが、英語に次ぐ話者人口があるのに対し、スペイン語から直接日本語に翻訳/通訳できるプロの絶対数が少なすぎるという事情もあるのかもしれません。
しかしそうした状況下で奮闘している翻訳家の方々というのはやはり確固とした信念の持ち主なのでしょうか。原作『アラトリステ』の日本語訳者さんのブログを偶然に見つけたのですが、これが凄い。その圧倒的な情報量には煮えたぎるような情熱の所在を嗅ぎとらざるをえず、よって嫌が応にもここでも紹介せざるをえませんでした(↓)。ちなみに当該ブログ署名の‘ゲベード’は映画に登場する詩人の名で、この詩人は激情型の愛すべき個性を以って描かれています。
ゲベード様のブログ: http://alatriste.exblog.jp/
◆アラトリステの侠気
ネタバレになって興を削がないような範囲で、映画本編の内容への言及をもう一点だけ。主人公の侠気(おとこぎ)について。
時代物の映像作品におけるストーリーには、大別して時代状況そのものの表出を通して人間全般について語ろうとするものと、時代的な制約のもとでもがく主人公個人の普遍的心情を描こうとするものがありますが、この作品はどちらかといえば後者です。この意味で言えばアラトリステ役の位置付けは、日本映画で言うところの黒澤映画における三船敏郎や、仁義なきシリーズの菅原文太といったところでしょうか。主要な脇役にことごとく生粋のスペイン人俳優が起用されているなかで、ただひとり主演のヴィゴ・モーテンセンだけがデンマーク人ハーフの質実剛健で静的な風貌を湛えていることは、こうした面で観客の心情を主人公の内面に焦点化させるうえでも非常に効いていたと思います。
ですからそうした感情移入の仕方でこの映画を楽しむというのは大いにアリなのですが、果たしてそれだけが制作者サイドの意図した仕掛けなのかと考え始めると、観終えて少し疑問も覚えました。わたしは映画を観ている最中は、主人公が5歳児だろうが子豚だろうが全力で感情を没入させて一喜一憂するタイプです。従ってこの作品でもエンドロールが始まった時点ではもう世の裏の裏まで見知った熟練剣士の気分満載で、早々に退場するお客さんの影が劇場脇の扉に映ろうものなら「すわ刺客か」と腰に手を当てたほどでしたが、数分たつとまた別の感興が湧き起こってきたのですね。
映画の中盤で、主人公が悪者から奪還した大量の金塊を目の前にして、それを仲間と山分けできたにも関わらず、懇意の伯爵が掲げる大義を信じて手をつけない場面があります。その功によってスペイン王が彼に褒美を直賜するのですが、この非常に高価な褒美をも主人公は、そのすぐあとに現代的な経済感覚からは考えられない交換によって簡単に手放してしまいます。その‘交換’はあるとてもロマンティックな目的のため行われたのですが、続いて起きた悲劇的な事件のためその目的も達成されずに終わります。結果としてアラトリステの思惑次第で手にしえた、大量の金塊により表現された物質的利得はほぼすべて水泡に帰すことになるのですが、その個人的損失に対する自意識の拘泥はまったく描かれることがありません。これがたとえば日本の民放ドラマなどであれば、そこで売れ線の主演タレントが悲憤に暮れるドアップが必ず来るような場面もみなスルーされてしまうのですね。これはいったいどういうことなんだろうとしばし考えて、思い至ったのが制作者側の作品に込めたアイロニーというか、現代という時代への社会批判的な演出意図の存在でした。
ここから先を作品に即して続けるのは、ラストの核心に触れてしまいそうなのでやめておきます。とにかく、この映画で描かれる剣士一人の命というのはとても軽く安いものであったがゆえに、そこに脈打ったであろう死生観には現代人が抱えるような肥大化した自意識が混じり込む余地はまるで感じられません。けれども近世以降に起きたに違いないこの価値観の変化は21世紀を生きるわたしたちにとって、本当にもろ手を挙げて喜ぶべきことだったのか。得られた安全や快適さと引き換えに失ったもののなかには、本来人間が人間的に生きるうえでとても大切な何かが含まれていたんじゃないか。だとすればそれは具体的には何なのか、すでに払った代償として忘却したままで本当に自分たちは良いのだろうか。そうした問いかけがこの作品の根底には含まれているのかも、などとエンドロールが終わる頃には思い至り、興奮の余韻とともに席を立って劇場をあとにしました。いつも通り穿ちすぎかもしれませんけど、こう考えてくるとそれはかつて小津安二郎監督が再三採り上げていた主題にも近いものを感じます。
ともあれおすすめの一篇です。衣装やセットにはふんだんに手がかかっており、ベラスケスの肖像画に怖いくらいに似ているフェリペ4世などが登場して目を楽しませてくれます。テルシオ(スペイン方陣)などもバッチリ再現されていて、絵作りにもとても気合の入った作品でした。
“Alatriste” by Agustín Díaz Yanes [+scr] / Viggo Mortensen, Eduardo Noriega, Javier Camára, Elena Anaya, Ariadna Gil / Benjamin Fernandez [art director] / Arturo Pérez-Reverte [book author] / 147min / Spain / 2006
公式HP: http://www.alatriste.jp/ (予告編は一見推奨)
主人公アラトリステは、戦時には前線に赴き、平時には貴族から暗殺依頼を請け負うなどして糊口をしのぐ暮らしに自足する男でした。しかしその研ぎ澄まされた技量や直情的な生き様は自然に仲間からの信頼を集め、王国一の女優に愛され、国を牛耳る貴族たちから一目置かれるようになります。やがて運命は彼を素朴な剣士稼業から引きはがし、時には国際情勢を揺るがすような権謀術数の渦中にも巻き込んでゆきます。映画はこうして展開される彼の波乱万丈の人生を、視覚的にもとても凝った演出によって見せてくれる、期待値以上に贅沢な作品に仕上がっていました。
◆原作と映画
原作は同タイトルの小説『アラトリステ(El capitán Alatriste)』。全6巻からなるこの小説は世界的ベストセラーで、数十カ国で読まれているようです。扱う時代的に言うならば池波正太郎の剣客物や司馬遼太郎等の戦国物のラテン版といったところでしょうか。著者のアルトゥーロ・ペレス=レベルテ(Arturo Pérez-Reverte)は元新聞記者で、国営TV局の戦場特派員の経歴もあるといいますから、そうした生の戦場体験が活かされていることも恐らくヒットの理由にあるのでしょう。
映画では一応この全6巻のエピソードが集約的に描かれています。「一応」と書いたのは、わたし自身は原作を読んでおらず、2時間前後の映画の尺に収めるにはうち1作か2作程度のエピソードを重点的に扱うのが限界だろうと推測するからです。そして実際この点に関しては、作品を観てややエピソードを詰め込み過ぎているかなあという感想も持ちました。パーツパーツは良いのに全体として過重気味なのが逆に作品を薄くしていまっている印象は、同様に原作が超長編の“グリーンマイル(The Green Mile) ”[S.キング原作, トム・ハンクス主演, 1998]を思い起こしました。
また、制作側はまずスペイン国内での大ヒットを目論んで撮ったはずですから理解はできるのですが、たとえばスペイン史に疎い日本の観客などには前後のつながりが意味不明に映るだろうと思う箇所を散見したのも気になりました。
これは上杉謙信と武田信玄、織田信長と徳川家康の関係くらい常識的に知っているだろうという前提のもとで撮られた正月の戦国ドラマを、字幕だけ付けて「さあ楽しめ」とジャマイカ人やマサイ族に観せるようなものに近く、どう考えても無理があります。なのでこの記事をきっかけにこれから“アラトリステ”を観ようと思ったかたがもしいらしたら、あらかじめスペイン史年表を少しおさらいしておくと良いかもしれません。
ところでこの原作小説、日本ではあまりというか、ベストセラー書籍というニュアンスではまったく話題になっていないと思いますが、文学に限らず文化全般においてスペイン語圏の作品は日本ではあまり普及しないイメージがありますね。文化的な相性なのか、商業構造的な制約によるのかはわかりませんが、英語に次ぐ話者人口があるのに対し、スペイン語から直接日本語に翻訳/通訳できるプロの絶対数が少なすぎるという事情もあるのかもしれません。
しかしそうした状況下で奮闘している翻訳家の方々というのはやはり確固とした信念の持ち主なのでしょうか。原作『アラトリステ』の日本語訳者さんのブログを偶然に見つけたのですが、これが凄い。その圧倒的な情報量には煮えたぎるような情熱の所在を嗅ぎとらざるをえず、よって嫌が応にもここでも紹介せざるをえませんでした(↓)。ちなみに当該ブログ署名の‘ゲベード’は映画に登場する詩人の名で、この詩人は激情型の愛すべき個性を以って描かれています。
ゲベード様のブログ: http://alatriste.exblog.jp/
◆アラトリステの侠気
ネタバレになって興を削がないような範囲で、映画本編の内容への言及をもう一点だけ。主人公の侠気(おとこぎ)について。
時代物の映像作品におけるストーリーには、大別して時代状況そのものの表出を通して人間全般について語ろうとするものと、時代的な制約のもとでもがく主人公個人の普遍的心情を描こうとするものがありますが、この作品はどちらかといえば後者です。この意味で言えばアラトリステ役の位置付けは、日本映画で言うところの黒澤映画における三船敏郎や、仁義なきシリーズの菅原文太といったところでしょうか。主要な脇役にことごとく生粋のスペイン人俳優が起用されているなかで、ただひとり主演のヴィゴ・モーテンセンだけがデンマーク人ハーフの質実剛健で静的な風貌を湛えていることは、こうした面で観客の心情を主人公の内面に焦点化させるうえでも非常に効いていたと思います。
ですからそうした感情移入の仕方でこの映画を楽しむというのは大いにアリなのですが、果たしてそれだけが制作者サイドの意図した仕掛けなのかと考え始めると、観終えて少し疑問も覚えました。わたしは映画を観ている最中は、主人公が5歳児だろうが子豚だろうが全力で感情を没入させて一喜一憂するタイプです。従ってこの作品でもエンドロールが始まった時点ではもう世の裏の裏まで見知った熟練剣士の気分満載で、早々に退場するお客さんの影が劇場脇の扉に映ろうものなら「すわ刺客か」と腰に手を当てたほどでしたが、数分たつとまた別の感興が湧き起こってきたのですね。
映画の中盤で、主人公が悪者から奪還した大量の金塊を目の前にして、それを仲間と山分けできたにも関わらず、懇意の伯爵が掲げる大義を信じて手をつけない場面があります。その功によってスペイン王が彼に褒美を直賜するのですが、この非常に高価な褒美をも主人公は、そのすぐあとに現代的な経済感覚からは考えられない交換によって簡単に手放してしまいます。その‘交換’はあるとてもロマンティックな目的のため行われたのですが、続いて起きた悲劇的な事件のためその目的も達成されずに終わります。結果としてアラトリステの思惑次第で手にしえた、大量の金塊により表現された物質的利得はほぼすべて水泡に帰すことになるのですが、その個人的損失に対する自意識の拘泥はまったく描かれることがありません。これがたとえば日本の民放ドラマなどであれば、そこで売れ線の主演タレントが悲憤に暮れるドアップが必ず来るような場面もみなスルーされてしまうのですね。これはいったいどういうことなんだろうとしばし考えて、思い至ったのが制作者側の作品に込めたアイロニーというか、現代という時代への社会批判的な演出意図の存在でした。
ここから先を作品に即して続けるのは、ラストの核心に触れてしまいそうなのでやめておきます。とにかく、この映画で描かれる剣士一人の命というのはとても軽く安いものであったがゆえに、そこに脈打ったであろう死生観には現代人が抱えるような肥大化した自意識が混じり込む余地はまるで感じられません。けれども近世以降に起きたに違いないこの価値観の変化は21世紀を生きるわたしたちにとって、本当にもろ手を挙げて喜ぶべきことだったのか。得られた安全や快適さと引き換えに失ったもののなかには、本来人間が人間的に生きるうえでとても大切な何かが含まれていたんじゃないか。だとすればそれは具体的には何なのか、すでに払った代償として忘却したままで本当に自分たちは良いのだろうか。そうした問いかけがこの作品の根底には含まれているのかも、などとエンドロールが終わる頃には思い至り、興奮の余韻とともに席を立って劇場をあとにしました。いつも通り穿ちすぎかもしれませんけど、こう考えてくるとそれはかつて小津安二郎監督が再三採り上げていた主題にも近いものを感じます。
ともあれおすすめの一篇です。衣装やセットにはふんだんに手がかかっており、ベラスケスの肖像画に怖いくらいに似ているフェリペ4世などが登場して目を楽しませてくれます。テルシオ(スペイン方陣)などもバッチリ再現されていて、絵作りにもとても気合の入った作品でした。
“Alatriste” by Agustín Díaz Yanes [+scr] / Viggo Mortensen, Eduardo Noriega, Javier Camára, Elena Anaya, Ariadna Gil / Benjamin Fernandez [art director] / Arturo Pérez-Reverte [book author] / 147min / Spain / 2006
史上名高い“アルマダの海戦”の勃発前夜から終結に到るまでをエリザベス1世の視点から描いた2007年公開の本作は、1998年製作の映画“エリザベス”の続編として構想されました。
official web: http://www.elizabeththegoldenage.com/site/site.html
まず書き付けてしまえば、この監督、この主演によって本作品が撮られたことを絶賛しないわけにはいきません。というのも前作“エリザベス”は質的に非常に高い水準を達成しながらも、今日の映画を巡る状況下では続編製作が期待されるような作品とはとても思えなかったからです。主演のケイト・ブランシェットそのひとですら、続編製作の話に対しては当初から懐疑的でした。
しかし蓋を開けてみればどうでしょうか。個人的な好みから言えば、これほど緻密に練られたショットの連続する映画をしばらく観ていなかった気がします。印象に残るシーンがとにかく多い作品でした。
◆前作との違い
さて、本作は主要スタッフ・キャストがほぼ前作と共通し、ストーリーも重なるため‘続編’であることは確かなのですが、全体の構成はかなり違ったものに映りました。前作が女王として戴冠するまでの陰謀劇から“よき女王(Good Queen Bess)”として君臨するに至るまでを描いた通時的なつくりであったのに対し、本作ではスペイン無敵艦隊を駆逐した“アルマダの海戦”に時制を定め、劇中で進行するすべてのエピソードが開戦の瞬間へと収斂するまとまりのある構成になっていたのです。このため前作を観ている必要がまったくない仕上がりになったと同時に、全編の流れに振れ幅の大きな抑揚が生じ、前作よりもずっと観やすくなったとも言えそうです。
もし“歴史映画”という評価軸がありうるなら前作はまごうことなき傑作映画なのですが、その一方で一般の娯楽映画を期待する観客にとっては退屈に映るのも致し方ない面の多い作品でしたから、本作では尚更こうしたあたりに力点が置かれたのかもしれません。
◆ローリー卿と史実の再現性
エリザベスのかたわらで全編を通じてストーリーをきっちり締めていく役柄として、本作ではウォルター・ローリー卿が新たに登場します。史実での彼はイングランドで初めて新大陸へ植民団を派遣した人物として知られ、文化人としての評価も高いのですが、劇中で彼に与えられたヒーロー的な役割はこうした背景を飾りとした、男性が主人公の一般的な冒険活劇物におけるヒロイン役に相当するものがあります。導入部では宮廷の面々を前に新大陸の文物を紹介して未知の世界を傍目に置く当時の時代背景を描き出し、中盤以降では恋愛要素を絡めて主人公のエリザベスが精神的な象徴として王国に君臨していくきっかけをも用意します。おまけに二枚目貴族のローリー自らが単身で焼き討ち船を操り無敵艦隊に突撃するシーンまで登場するのですが、これはまあご愛敬といったところでしょう。商業映画としてはありがちでも、この監督の手付きとしては明らかに異様でかつ浮いていました。
かのフランシス・ドレイクと英国艦隊旗艦での軍議を共にするなど、クライマックスの海戦シーンにおけるローリー卿の獅子奮迅ぶりは劇場で観ていて唯一苦笑とともにやや興醒めした場面なのですが、あらためて考えるとこれだけの製作規模により撮られた作品でこの部分以外はほとんど違和感なく楽しめていたのがむしろ稀有なことに思えます。ローリー卿が女王と深い関係を築きながらも女王付きの女官を妊娠させて幽閉されるくだりなど、むしろ映画のために作られた挿話とみたほうが自然なくらいに全体のストーリーとよく馴染んでいました。
こうした史実の再現性を巡っては、9年前の前作で徹底的にこだわった挙げ句に舞台背景が複雑になり過ぎた反省を活かしてか、素材の削ぎ落としかたにも思い切ったものがありました。
たとえば前作での戴冠時、エリザベスは明確に「イングランド・アイルランド・及びフランスの王」という口上付きで即位しており、フランス人によるブリテン島の国家という中世イングランド王家の性格をきちんと踏まえていたのですが、スコットランドのメアリ女王とメアリの甥でエリザベスの婿候補でもあったアンジュー公とが完全にフランス語を母語とした会話を交わすシーンなども込みで、イギリス史に疎い観客にとっては恐らくかなり混乱の元となったはずです。しかし本作に登場するイングランド王朝は、まだ弱小ながらも確固としたイングランド人の意識をもった人々により運営されており、そのはじめから独立国家としてどう諸外国と渡り合うかが外交の争点として描かれました。
こうした違いはどちらが正しいかという話よりは個々人の歴史観の問題(程度の問題)なので、結果として両作品の間にこうした点で対照的な差異が生じたことは興味深いところです。素材の吟味を経た製作の過程でたまたま筋道が分かれただけで、意図した結果ではないと思いますが。
◆監督と見どころと俳優
ところで冒頭にも述べたように、本作は視覚的に強い印象を残すシーンが多いことでも特徴づけられる作品なのですが、この特徴の源泉として奇抜なアングルからのショットやシンボリックなオブジェの多用などが挙げられます。現存のセント・ポール寺院を使用したロケーション撮影による場面でも後代の建築部分を巧妙にかわしつつ、ものすごい独創的な位置から人物を映し出すことでそのひとの内面まで表現しきっているシーンがいくつもあり、ヴィジュアル面での見応えも存分にありました。
このような見た目の独創性には、シェーカル・カプール監督がインド映画の出身であることも大きく関係しているはずです。単にインド出身というだけではない異質さが随所に見られるのも、欧米の製作環境とは文脈の異なる場での経験が下地にあることを知れば納得がゆくというものです。また黒澤映画っぽいシーンが幾つもあるなと思ったら、本人かなりの黒澤マニアを自負するひとらしく。
もしこれから観るかたがいるなら、本編中に幾度も登場するイングランド王宮から覗く月影や、敵対するスペインの王フェリペ2世が眼差す蝋燭の炎の揺らめきが何を象徴しているかに注意を払いながら観ていくと、またべつの深みが味わえるはずです。
またこの作品の核にあるのは史実の正確な再現でもなければ海戦描写の迫真性でもなく、エリザベスが抱える魂の変容していく姿だと思います。肉体的な情動やそれに由来する怒りや嫉妬といった個人的な感情が、無敵艦隊が迫るなかで音を立てて削ぎ落とされていく過程の描写は圧巻と言わざるをえません。大海戦のさなかにあって、エリザベスは文字通りの“処女王(The Virgin Queen)”として急速に覚醒していきます。ローリー卿も女王の周りに起こる様々な陰謀劇も本作品ではすべての要素がこの変容の瞬間を描くために存在していると言っても過言ではないので、この点を始めから留意して観るのも面白いかもしれません。
さいごにキャスティングについても触れておきます。まず主演のケイト・ブランシェット。監督は彼女の演技を見て事前に考えていた演出法を幾度も変えたらしいのですが、それもそのはず。彼女がこの作品で見せる演技は、はっきり言って破格です。この名優にしてこの作品が主要な代表作として今後語り継がれるのは疑いのないところでしょう。ウォルター・ローリーを演じたクライヴ・オーウェンは、孤高の冒険者を演じてこれでもう何作品目なのでしょうか。知性と野性を兼ね備えたこの手の役柄は彼しかいないという性格俳優の地位をすっかり確立した観があります。ケイト・ブランシェット以外で前作に続いて登場する唯一の主要キャストにジェフリー・ラッシュ(“パイレーツ・オブ・カリビアン”のバルボッサ役)がいますが、彼もまた両作品で対照的な性格を見せ作品に深い余韻を与えました。“刺客の修道士”というダークな端役に前作ではダニエル・クレイグ(現在の“007”シリーズ主演)、本作ではリス・エヴァンスと渋目の大物俳優を起用しているのも両作品の見逃せないポイントになっています。
実はこの記事シリーズでは2年前に一度前作を扱おうと考え、作品の日本公開時にあたる今年初頭には本作を記事化しようとも思い、今回が都合3回目の思いつきにしてようやく実行に漕ぎつけました。大航海時代を背景とする良作映画という当記事シリーズのテーマのどまんなかをゆく一編なので、逆に腰が重くなっていたのですね。それだけに書き切れなかったこともかつてなく多いのですが、反面‘ようやく書けたか’という慎ましやかな達成感にも今ほのかにひたっているところです。良い意味で期待を裏切ってくれた、なかなかの好作品でした。
“Elizabeth: The Golden Age” by Shekhar Kapur / Cate Blanchett, Clive Owen, Geoffrey Rush, Samantha Morton, Abbie Cornish, Rhys Ifans / Remi Adefarasin [Cinematography] / Jill Bilcock [editing] / 114min / UK, France / 2007
official web: http://www.elizabeththegoldenage.com/site/site.html
まず書き付けてしまえば、この監督、この主演によって本作品が撮られたことを絶賛しないわけにはいきません。というのも前作“エリザベス”は質的に非常に高い水準を達成しながらも、今日の映画を巡る状況下では続編製作が期待されるような作品とはとても思えなかったからです。主演のケイト・ブランシェットそのひとですら、続編製作の話に対しては当初から懐疑的でした。
しかし蓋を開けてみればどうでしょうか。個人的な好みから言えば、これほど緻密に練られたショットの連続する映画をしばらく観ていなかった気がします。印象に残るシーンがとにかく多い作品でした。
◆前作との違い
さて、本作は主要スタッフ・キャストがほぼ前作と共通し、ストーリーも重なるため‘続編’であることは確かなのですが、全体の構成はかなり違ったものに映りました。前作が女王として戴冠するまでの陰謀劇から“よき女王(Good Queen Bess)”として君臨するに至るまでを描いた通時的なつくりであったのに対し、本作ではスペイン無敵艦隊を駆逐した“アルマダの海戦”に時制を定め、劇中で進行するすべてのエピソードが開戦の瞬間へと収斂するまとまりのある構成になっていたのです。このため前作を観ている必要がまったくない仕上がりになったと同時に、全編の流れに振れ幅の大きな抑揚が生じ、前作よりもずっと観やすくなったとも言えそうです。
もし“歴史映画”という評価軸がありうるなら前作はまごうことなき傑作映画なのですが、その一方で一般の娯楽映画を期待する観客にとっては退屈に映るのも致し方ない面の多い作品でしたから、本作では尚更こうしたあたりに力点が置かれたのかもしれません。
◆ローリー卿と史実の再現性
エリザベスのかたわらで全編を通じてストーリーをきっちり締めていく役柄として、本作ではウォルター・ローリー卿が新たに登場します。史実での彼はイングランドで初めて新大陸へ植民団を派遣した人物として知られ、文化人としての評価も高いのですが、劇中で彼に与えられたヒーロー的な役割はこうした背景を飾りとした、男性が主人公の一般的な冒険活劇物におけるヒロイン役に相当するものがあります。導入部では宮廷の面々を前に新大陸の文物を紹介して未知の世界を傍目に置く当時の時代背景を描き出し、中盤以降では恋愛要素を絡めて主人公のエリザベスが精神的な象徴として王国に君臨していくきっかけをも用意します。おまけに二枚目貴族のローリー自らが単身で焼き討ち船を操り無敵艦隊に突撃するシーンまで登場するのですが、これはまあご愛敬といったところでしょう。商業映画としてはありがちでも、この監督の手付きとしては明らかに異様でかつ浮いていました。
かのフランシス・ドレイクと英国艦隊旗艦での軍議を共にするなど、クライマックスの海戦シーンにおけるローリー卿の獅子奮迅ぶりは劇場で観ていて唯一苦笑とともにやや興醒めした場面なのですが、あらためて考えるとこれだけの製作規模により撮られた作品でこの部分以外はほとんど違和感なく楽しめていたのがむしろ稀有なことに思えます。ローリー卿が女王と深い関係を築きながらも女王付きの女官を妊娠させて幽閉されるくだりなど、むしろ映画のために作られた挿話とみたほうが自然なくらいに全体のストーリーとよく馴染んでいました。
こうした史実の再現性を巡っては、9年前の前作で徹底的にこだわった挙げ句に舞台背景が複雑になり過ぎた反省を活かしてか、素材の削ぎ落としかたにも思い切ったものがありました。
たとえば前作での戴冠時、エリザベスは明確に「イングランド・アイルランド・及びフランスの王」という口上付きで即位しており、フランス人によるブリテン島の国家という中世イングランド王家の性格をきちんと踏まえていたのですが、スコットランドのメアリ女王とメアリの甥でエリザベスの婿候補でもあったアンジュー公とが完全にフランス語を母語とした会話を交わすシーンなども込みで、イギリス史に疎い観客にとっては恐らくかなり混乱の元となったはずです。しかし本作に登場するイングランド王朝は、まだ弱小ながらも確固としたイングランド人の意識をもった人々により運営されており、そのはじめから独立国家としてどう諸外国と渡り合うかが外交の争点として描かれました。
こうした違いはどちらが正しいかという話よりは個々人の歴史観の問題(程度の問題)なので、結果として両作品の間にこうした点で対照的な差異が生じたことは興味深いところです。素材の吟味を経た製作の過程でたまたま筋道が分かれただけで、意図した結果ではないと思いますが。
◆監督と見どころと俳優
ところで冒頭にも述べたように、本作は視覚的に強い印象を残すシーンが多いことでも特徴づけられる作品なのですが、この特徴の源泉として奇抜なアングルからのショットやシンボリックなオブジェの多用などが挙げられます。現存のセント・ポール寺院を使用したロケーション撮影による場面でも後代の建築部分を巧妙にかわしつつ、ものすごい独創的な位置から人物を映し出すことでそのひとの内面まで表現しきっているシーンがいくつもあり、ヴィジュアル面での見応えも存分にありました。
このような見た目の独創性には、シェーカル・カプール監督がインド映画の出身であることも大きく関係しているはずです。単にインド出身というだけではない異質さが随所に見られるのも、欧米の製作環境とは文脈の異なる場での経験が下地にあることを知れば納得がゆくというものです。また黒澤映画っぽいシーンが幾つもあるなと思ったら、本人かなりの黒澤マニアを自負するひとらしく。
もしこれから観るかたがいるなら、本編中に幾度も登場するイングランド王宮から覗く月影や、敵対するスペインの王フェリペ2世が眼差す蝋燭の炎の揺らめきが何を象徴しているかに注意を払いながら観ていくと、またべつの深みが味わえるはずです。
またこの作品の核にあるのは史実の正確な再現でもなければ海戦描写の迫真性でもなく、エリザベスが抱える魂の変容していく姿だと思います。肉体的な情動やそれに由来する怒りや嫉妬といった個人的な感情が、無敵艦隊が迫るなかで音を立てて削ぎ落とされていく過程の描写は圧巻と言わざるをえません。大海戦のさなかにあって、エリザベスは文字通りの“処女王(The Virgin Queen)”として急速に覚醒していきます。ローリー卿も女王の周りに起こる様々な陰謀劇も本作品ではすべての要素がこの変容の瞬間を描くために存在していると言っても過言ではないので、この点を始めから留意して観るのも面白いかもしれません。
さいごにキャスティングについても触れておきます。まず主演のケイト・ブランシェット。監督は彼女の演技を見て事前に考えていた演出法を幾度も変えたらしいのですが、それもそのはず。彼女がこの作品で見せる演技は、はっきり言って破格です。この名優にしてこの作品が主要な代表作として今後語り継がれるのは疑いのないところでしょう。ウォルター・ローリーを演じたクライヴ・オーウェンは、孤高の冒険者を演じてこれでもう何作品目なのでしょうか。知性と野性を兼ね備えたこの手の役柄は彼しかいないという性格俳優の地位をすっかり確立した観があります。ケイト・ブランシェット以外で前作に続いて登場する唯一の主要キャストにジェフリー・ラッシュ(“パイレーツ・オブ・カリビアン”のバルボッサ役)がいますが、彼もまた両作品で対照的な性格を見せ作品に深い余韻を与えました。“刺客の修道士”というダークな端役に前作ではダニエル・クレイグ(現在の“007”シリーズ主演)、本作ではリス・エヴァンスと渋目の大物俳優を起用しているのも両作品の見逃せないポイントになっています。
実はこの記事シリーズでは2年前に一度前作を扱おうと考え、作品の日本公開時にあたる今年初頭には本作を記事化しようとも思い、今回が都合3回目の思いつきにしてようやく実行に漕ぎつけました。大航海時代を背景とする良作映画という当記事シリーズのテーマのどまんなかをゆく一編なので、逆に腰が重くなっていたのですね。それだけに書き切れなかったこともかつてなく多いのですが、反面‘ようやく書けたか’という慎ましやかな達成感にも今ほのかにひたっているところです。良い意味で期待を裏切ってくれた、なかなかの好作品でした。
“Elizabeth: The Golden Age” by Shekhar Kapur / Cate Blanchett, Clive Owen, Geoffrey Rush, Samantha Morton, Abbie Cornish, Rhys Ifans / Remi Adefarasin [Cinematography] / Jill Bilcock [editing] / 114min / UK, France / 2007
Job Description 14: 司祭 【薔薇の名前】
2008年5月13日 就職・転職 コメント (4)
幼い頃にみて、強烈な印象が今も残っている映画というのは誰しもあるものだと思います。わたしの場合、“薔薇の名前”はその一つでした。恐らく周囲の大人がヴィデオかテレビ放映で観ていたとき脇にいたのだと思うけれど、まだ意味はわからなくても、とにかくオドロオドロしい世界の象徴に近いものとして以後それは心の奥底に沈澱し続けました。
十代の終わり頃を中心とした、浴びるように映画を見続けた時期をへて最近この作品をあらためて観る機会があり、驚きました。傑作という以上の傑作だったからです。
予告編動画(50秒): http://www.youtube.com/watch?v=CsjKsl1bY0Y
物語は14世紀北イタリアの修道院で起きた怪事件を舞台として展開します。原作は『フーコーの振り子』でも著名な作家・哲学者のウンベルト・エーコによる同名小説。ショーン・コネリー演じる主人公のフランシスコ会修道士は、フランシスコ会とアヴィニョン教皇庁とのあいだで起きた清貧論争に決着をつけるため会談の場所となったこのベネディクト会修道院を訪れたのですが、修道院長からその炯眼を見込まれて数日前に起きた怪事件の原因究明を依頼されます。映画はこのようにして始まります。
清貧論争の場面(40秒): http://www.youtube.com/watch?v=qwd4oA75JPk
怪事件は主人公による探索開始後も連続して発生し、修道院全体が緊張と混乱に包まれるなかでアヴィニョン教皇庁からの使節団が到着、さらには異端審問官ベルナール・ギーの一行も到着して事態はどんどん複層化していきます。主人公はこの混沌のなかで、修道院の関係者ですら立ち入りが固く禁じられている巨大な文書庫の内部に事件の真相を解く鍵の気配を嗅ぎとります。そしてなんとか文書庫として使用されている城塞様の建築深部への潜入を果たすのですが、なんとそこには…。
これから観るひとの楽しみを奪わない範囲で前半のあらすじをまとめると以上のような感じになりますが、この映画の真骨頂はその良作歴史ミステリー然としたストーリー進行にあるのではなく、むしろ背景にある作品世界の奥行と、映像化にあたって払われた繊細な努力の膨大な厚みにあるといえます。
まがりなりにも大航海時代を謳うこの記事シリーズで14世紀前半を舞台とするこの映画をとりあげることに違和感をもつ向きがあるとしても、そこは実作品に触れてもらえれば容易に解消されるはず。というのも映画本編では多種多様な宗教/哲学上の命題が登場するのですが、それらに対する主人公の思考は徹底した合理主義に根差しており、近代人の眼を感じさせるものなのですね。
たとえば文書庫の深奥部で、当時ヨーロッパには存在しない(=もうこの世界には存在しない)と思われていた大量の古典時代を中心とする書物群の実在を確認して彼は涙します。このようにその時代その時代を覆った人々の意識とは切り離されたところで純粋な知的感動を共有することのできる人物の眼差しをここでは‘近代人の眼’と表現しましたが、そういう人々がどの時代どの地域にも確実に存在し続けたことが人類の文明発展を考えるうえで必要不可欠の条件であることもまた確かです。この点では、日常のわたしたちが考えるたとえば“14世紀前半の欧州”とは本当は何なのかということのほうが、あらためて再考を迫られるべきなのかもしれません。あるいは“大航海時代”とは、でも良いのですが。
異端審問の場面(1分):http://www.youtube.com/watch?v=zwMkoibG9FQ
ここで作品中の異端審問の場面を切り取った動画もご紹介。裁かれている人物は当時カトリック教会から異端として敵視されていたドルチーノ派に属した過去を隠してこの修道院に暮していたのですが、怪事件続発の過程でその過去を暴かれてしまい裁判に至ります。首席裁判官としてここに登場するベルナール・ギーは史実上の人物で、ドルチーノ派に関する数少ない記録の一つを残した異端審問官でした。この動画では断片的だしイタリア語の吹き替えということもあっていまいち迫真性に欠けますが、短いシークエンスにおいて糾弾されることにより逆に異端教徒としての誇りを取り戻していく修道僧の演技は作品全編を通しても心に残るシーンの一つです。
異端関連やアヴィニョン教皇庁周辺、中世における禁書の保存等についてなどを叔父貴がまとめているのでついでにご紹介。下記3つ目の記事は日本の場合になりますが、洋の東西に関わらず中世における宗教組織が果たした役割の一側面として。
異端派と十字軍: http://rainyheart.blog32.fc2.com/blog-entry-96.html
聖歌と教皇庁周辺: http://rainyheart.blog32.fc2.com/blog-entry-97.html
本願寺家の禁書:http://rainyheart.blog32.fc2.com/blog-entry-23.html[記事後半]
わたしと同様に、「この作品は前に観た」という意識が働いてずっと再鑑賞する機会をもたないままでいるひとも、‘大航海時代Online’のプレイヤーにはきっと多いだろうと推測します。もしそうであれば、ぜひお薦めの一作です。公開直後の全米市場では酷評の嵐だったことが俄かには信じがたいのですが、昨今の新作映画に比して娯楽作品としてもまったく古びていない高水準の質を維持しています。ジェームズ・ホーナーの音楽も非常に効いています。(ex.予告編動画のBGM) ホーナーはこの記事シリーズで過去にとりあげた“アポカリプト”や“ニュー・ワールド”の音楽も担当しているのですが、彼がいなかったら映画音楽というジャンルの在りようは今とはまったく違ったものになっていたと思います。
なおDVD化にあたって製作当時を振り返った監督へのインタビュー等が併録されています。撮影に際していかに困難な状況に直面していたかといった裏事情が語られて興味深いものでした。個人的には本編中に登場するゴシック教会では明らかに浮いているロマネスク以降のマリア像に関する顛末や、若き修練士を演じたクリスチャン・スレーターのヒロイン役とのラヴシーンを巡るほのぼのとしたエピソードが面白かったです。題名である“薔薇の名前”は直接的にはこの無名のヒロインとして登場する地元の貧しい娘に付されたあだ名なのですが、そこは知の巨人エーコがタイトルに使用するほどです。‘薔薇’にも‘名前’にも無量のコノテーションが含意されていることは言うまでもありません。
エーコによる原作『薔薇の名前』は文学史上の事件といっても良いほどに出版当時の世界に衝撃を与えた作であり、通常のミステリー作品がもっているような伏線や謎かけ等とは根本的に次元の異なる超重層的な物語構造が施されているものでした。それは映画版でもよりわかりやすい形で再現されていて、あまりにも仕掛けが膨大であるためその一つ一つが観た者のその後の日常生活において思わぬ機会に明かされていく可能性を有しており、その点では一度観ておくとその後長く楽しめる一篇とも言えそうです。
古典といわれる文学作品はいずれも読んだのち非常に長いスケールにおいて読者に意外な形で影響を及ぼし続けるものですが、まだ歴史の浅い映画という表現ジャンルにもし古典と言えるものを探すなら、きっとそれはこうした意味での芸術としての力を十全と湛えた“薔薇の名前”のような作品のことを言うのでしょう。
“The Name of the Rose” by Jean-Jacques Annaud / Sean Connery,Christian Slater,F.Murray Abraham / Bernd Eichinger [producer] / James Horner [music composer] / Umberto Eco [book author] / 128min / Germany,Italy,France,US / 1986
十代の終わり頃を中心とした、浴びるように映画を見続けた時期をへて最近この作品をあらためて観る機会があり、驚きました。傑作という以上の傑作だったからです。
予告編動画(50秒): http://www.youtube.com/watch?v=CsjKsl1bY0Y
物語は14世紀北イタリアの修道院で起きた怪事件を舞台として展開します。原作は『フーコーの振り子』でも著名な作家・哲学者のウンベルト・エーコによる同名小説。ショーン・コネリー演じる主人公のフランシスコ会修道士は、フランシスコ会とアヴィニョン教皇庁とのあいだで起きた清貧論争に決着をつけるため会談の場所となったこのベネディクト会修道院を訪れたのですが、修道院長からその炯眼を見込まれて数日前に起きた怪事件の原因究明を依頼されます。映画はこのようにして始まります。
清貧論争の場面(40秒): http://www.youtube.com/watch?v=qwd4oA75JPk
怪事件は主人公による探索開始後も連続して発生し、修道院全体が緊張と混乱に包まれるなかでアヴィニョン教皇庁からの使節団が到着、さらには異端審問官ベルナール・ギーの一行も到着して事態はどんどん複層化していきます。主人公はこの混沌のなかで、修道院の関係者ですら立ち入りが固く禁じられている巨大な文書庫の内部に事件の真相を解く鍵の気配を嗅ぎとります。そしてなんとか文書庫として使用されている城塞様の建築深部への潜入を果たすのですが、なんとそこには…。
これから観るひとの楽しみを奪わない範囲で前半のあらすじをまとめると以上のような感じになりますが、この映画の真骨頂はその良作歴史ミステリー然としたストーリー進行にあるのではなく、むしろ背景にある作品世界の奥行と、映像化にあたって払われた繊細な努力の膨大な厚みにあるといえます。
まがりなりにも大航海時代を謳うこの記事シリーズで14世紀前半を舞台とするこの映画をとりあげることに違和感をもつ向きがあるとしても、そこは実作品に触れてもらえれば容易に解消されるはず。というのも映画本編では多種多様な宗教/哲学上の命題が登場するのですが、それらに対する主人公の思考は徹底した合理主義に根差しており、近代人の眼を感じさせるものなのですね。
たとえば文書庫の深奥部で、当時ヨーロッパには存在しない(=もうこの世界には存在しない)と思われていた大量の古典時代を中心とする書物群の実在を確認して彼は涙します。このようにその時代その時代を覆った人々の意識とは切り離されたところで純粋な知的感動を共有することのできる人物の眼差しをここでは‘近代人の眼’と表現しましたが、そういう人々がどの時代どの地域にも確実に存在し続けたことが人類の文明発展を考えるうえで必要不可欠の条件であることもまた確かです。この点では、日常のわたしたちが考えるたとえば“14世紀前半の欧州”とは本当は何なのかということのほうが、あらためて再考を迫られるべきなのかもしれません。あるいは“大航海時代”とは、でも良いのですが。
異端審問の場面(1分):http://www.youtube.com/watch?v=zwMkoibG9FQ
ここで作品中の異端審問の場面を切り取った動画もご紹介。裁かれている人物は当時カトリック教会から異端として敵視されていたドルチーノ派に属した過去を隠してこの修道院に暮していたのですが、怪事件続発の過程でその過去を暴かれてしまい裁判に至ります。首席裁判官としてここに登場するベルナール・ギーは史実上の人物で、ドルチーノ派に関する数少ない記録の一つを残した異端審問官でした。この動画では断片的だしイタリア語の吹き替えということもあっていまいち迫真性に欠けますが、短いシークエンスにおいて糾弾されることにより逆に異端教徒としての誇りを取り戻していく修道僧の演技は作品全編を通しても心に残るシーンの一つです。
異端関連やアヴィニョン教皇庁周辺、中世における禁書の保存等についてなどを叔父貴がまとめているのでついでにご紹介。下記3つ目の記事は日本の場合になりますが、洋の東西に関わらず中世における宗教組織が果たした役割の一側面として。
異端派と十字軍: http://rainyheart.blog32.fc2.com/blog-entry-96.html
聖歌と教皇庁周辺: http://rainyheart.blog32.fc2.com/blog-entry-97.html
本願寺家の禁書:http://rainyheart.blog32.fc2.com/blog-entry-23.html[記事後半]
わたしと同様に、「この作品は前に観た」という意識が働いてずっと再鑑賞する機会をもたないままでいるひとも、‘大航海時代Online’のプレイヤーにはきっと多いだろうと推測します。もしそうであれば、ぜひお薦めの一作です。公開直後の全米市場では酷評の嵐だったことが俄かには信じがたいのですが、昨今の新作映画に比して娯楽作品としてもまったく古びていない高水準の質を維持しています。ジェームズ・ホーナーの音楽も非常に効いています。(ex.予告編動画のBGM) ホーナーはこの記事シリーズで過去にとりあげた“アポカリプト”や“ニュー・ワールド”の音楽も担当しているのですが、彼がいなかったら映画音楽というジャンルの在りようは今とはまったく違ったものになっていたと思います。
なおDVD化にあたって製作当時を振り返った監督へのインタビュー等が併録されています。撮影に際していかに困難な状況に直面していたかといった裏事情が語られて興味深いものでした。個人的には本編中に登場するゴシック教会では明らかに浮いているロマネスク以降のマリア像に関する顛末や、若き修練士を演じたクリスチャン・スレーターのヒロイン役とのラヴシーンを巡るほのぼのとしたエピソードが面白かったです。題名である“薔薇の名前”は直接的にはこの無名のヒロインとして登場する地元の貧しい娘に付されたあだ名なのですが、そこは知の巨人エーコがタイトルに使用するほどです。‘薔薇’にも‘名前’にも無量のコノテーションが含意されていることは言うまでもありません。
エーコによる原作『薔薇の名前』は文学史上の事件といっても良いほどに出版当時の世界に衝撃を与えた作であり、通常のミステリー作品がもっているような伏線や謎かけ等とは根本的に次元の異なる超重層的な物語構造が施されているものでした。それは映画版でもよりわかりやすい形で再現されていて、あまりにも仕掛けが膨大であるためその一つ一つが観た者のその後の日常生活において思わぬ機会に明かされていく可能性を有しており、その点では一度観ておくとその後長く楽しめる一篇とも言えそうです。
古典といわれる文学作品はいずれも読んだのち非常に長いスケールにおいて読者に意外な形で影響を及ぼし続けるものですが、まだ歴史の浅い映画という表現ジャンルにもし古典と言えるものを探すなら、きっとそれはこうした意味での芸術としての力を十全と湛えた“薔薇の名前”のような作品のことを言うのでしょう。
“The Name of the Rose” by Jean-Jacques Annaud / Sean Connery,Christian Slater,F.Murray Abraham / Bernd Eichinger [producer] / James Horner [music composer] / Umberto Eco [book author] / 128min / Germany,Italy,France,US / 1986
叔父のブログが再開したようなのでその紹介から。ここのところ当ブログは半冬眠の状態に入ってますが、代わりにという感じで。
Mamma Mia! 教授ブログ!! :
http://rainyheart.blog32.fc2.com/
スタイルは違うけれど思考回路はほぼ一緒なので、‘さよなら航路’に頻訪いただいているかたの幾らかにはこちらも気に入ってもらえると思います。あと私事の報告になりますが、普通免許とれました>w< 技能検定、あのシチュエーションはバカみたいに緊張しますね。(笑)
では本題。‘大航海時代Online’拡張版の新章が来週からスタートしますね。地理面での追加実装はオセアニア一帯がメインとなるようです。それにちなんで今回はニュージーランドの映画をとりあげます。
▼リバー・クイーン
この映画は1860年に起きたマオリ戦争の史実が舞台になっています。イギリス帝国主義の尖兵として密林に送り込まれた開拓団の隊士たちと、彼らを待ち受けるマオリ族の戦士たちのあいだで翻弄される娘が主人公。彼女も史実上の人物で、原題の‘River Queen’はマオリの側から彼女に当てられた呼称です。
19世紀半ばといえばイギリス本国ではすでに産業革命の真っ只中ですから大局的には大航海時代とは言い難いわけですが、そこは地球の裏側の出来事です。ジェームス・クックが初めてこの周辺の海図を作成したのが18世紀後半ですから、この地域では時代を遅らせて考えたほうが妥当というケースは様々な面で見られるのですね。登場する船について言えば、河をさかのぼる小舟やタグボートには素朴な蒸気機関も使用されて始めているものの、外洋向けの大型船舶はいまだ帆走が主体という時代。マオリの人々が乗る船としてはもちろん手漕ぎの木製カヌーが多数登場します。
本編は主人公の娘がマオリ族の青年の子供を身篭るところから始まります。彼女は開拓団に属する軍医の娘であり幼い頃から父より医術の教育を受けていたのですが、このマオリの子を宿したことと医術の素養を得たことの2点がその後の彼女の軌跡を稀有のものにしてゆきます。演じるのはサマンサ・モートン。明日から国内公開される“エリザベス:ゴールデン・エイジ”でもスコットランドのメアリー女王という極めて重要な役を演じています。エリザベス最大のライヴァルといって良い存在ですね。
そして彼女を想うイギリス側の兵士として登場するのがかのキーファー・サザーランド。ドラマ“24”のジャック張りのアクションシーンも確かにあるのですが、日本では軍服姿の彼がライフルを構える姿がDVDジャケットに大きく描かれ、邦題も“ファイナル・ソルジャー”とあたかもサザーランド主人公の戦争アクション映画かのような印象を生む形で売り出されました。このためネットでこの映画の日本での感想を検索すると、この点の不満を書いたものばかりが挙がってきます。このことは騙し半分でも敢えてサザーランドを前面に出した売り手側の商業的手腕を結果的に証明するものとも言えるわけですが、それにしてもこの邦題の野暮ったさは異様です。
主人公の娘をとりあうマオリ側の戦士はクリフ・カーティスが演じています。彼の名はまだあまり知られていませんが、最近そこらじゅうのハリウッド映画に脇役出演しまくっている俳優です。過去にこの記事シリーズで扱った“ファウンテン”ではスペインの南米探検隊に属する謎のイスラム剣士として登場するし、“ダイ・ハード4.0”ではFBIの指揮官としてブルース・ウィリスを牽制します(設定はたぶんアラブ系)。メキシコ人やイラク人、インド人の役も見たことあるかも。でも本人はマオリ出身であることをこの映画を通じて初めて知りました。
実は恒例の記事タイトルに「軍医」ではなく「斥候」の語を当てようかとも考えました。娘のみごもった子がのちに斥候がやるような撹乱行為でイギリス軍を惑わせるシーンがあるためです。けれどこの子役はあまり華がなく感心できず。娘の父である軍医の役にはステファン・リー。いぶし銀の名優だけに演技の水準はキャスト陣のなかでもピカ一です。
作品全編を通しての感想としては、原生林を舞台としたロケハンがとにかく美しく、マオリの集落や開拓団の居住区を再現したセットも非常に緻密で、それだけでも見た甲斐がありました。ただストーリーの展開はやや詩的に過ぎ、説明不足のまま流れてしまうことが徒と出ているようなシーンもそこかしこにあったのはもったいないところです。往々にして制作陣の思い入れが強すぎるとこうなります。ニュージーランド人である監督のヴィンセント・ウォードはプロデューサーとしてもハリウッドで確固たる地位にある人物のようで、だからこそ採算性はどの目にも低いこうした作品にこれだけのキャストを集められたのでしょうが、‘マオリを前面に出した作品を世界に売る’という気負いがやや出すぎた観は否めません。
さて‘大航海時代Online’にもすでにマオリの人々は登場しているわけですが、彼らがゲーム内で見せている言動は感覚的に少しおかしなものに映ります。詳しくは以前の記事(2007年8月26日記事「世界独航記ノ貮」↓末尾にURL)に述べたので割愛しますが、当然ながらそう簡単にヨーロッパ人の営みに馴染んでいったわけではありません。こうしたあたりで、大航海時代のヨーロッパの人々が原住民の住む遠方の土地でどのような形で植民活動を進め、現地の人々がどのように受容していったのかに関心のあるかたには、参考になるシーンが多くある作品にもなっていると思います。
アフリカであれアメリカであれどこであれ、白人たちは一方的な侵略行為によって既存のコミュニティを征服し破壊していっただけだろうと考えるのは簡単です。しかしそこには必ず自らの行為に疑問を抱いて行動に移した人々や、逆に植民活動を利用した原住民たちなどがおり、その展開は地域ごと・時代ごとに様々な変容を見せました。
こうした価値観の異なる集団と集団との接触の帰結として個人個人の内面に生じる葛藤までを読み込むと大航海時代の世界を考える楽しみはぐっと深みを増すはずです。これは一見情緒的な作業のようでいて、実質的にはロジカルな枠組みの問題というかテキスト依存の形態に落とし込みやすい圏域なので、‘大航海時代Online’もいずれはそうした領域にまで踏み込める水準を目指してほしいなとは思います。 うん。妙なまとめかたですね。
“River Queen” by Vincent Ward [+scr] / Samantha Morton, Kiefer Sutherland, Cliff Curtis, Temuera Morrison, Stephen Rea / 113min / New Zealand, UK / 2005 ※本作品の国内上映館での公開はなし。一般流通はDVDのみ。
※※過去記事「世界独航記ノ貮」: http://diarynote.jp/d/75061/20070826.html
Mamma Mia! 教授ブログ!! :
http://rainyheart.blog32.fc2.com/
スタイルは違うけれど思考回路はほぼ一緒なので、‘さよなら航路’に頻訪いただいているかたの幾らかにはこちらも気に入ってもらえると思います。あと私事の報告になりますが、普通免許とれました>w< 技能検定、あのシチュエーションはバカみたいに緊張しますね。(笑)
では本題。‘大航海時代Online’拡張版の新章が来週からスタートしますね。地理面での追加実装はオセアニア一帯がメインとなるようです。それにちなんで今回はニュージーランドの映画をとりあげます。
▼リバー・クイーン
この映画は1860年に起きたマオリ戦争の史実が舞台になっています。イギリス帝国主義の尖兵として密林に送り込まれた開拓団の隊士たちと、彼らを待ち受けるマオリ族の戦士たちのあいだで翻弄される娘が主人公。彼女も史実上の人物で、原題の‘River Queen’はマオリの側から彼女に当てられた呼称です。
19世紀半ばといえばイギリス本国ではすでに産業革命の真っ只中ですから大局的には大航海時代とは言い難いわけですが、そこは地球の裏側の出来事です。ジェームス・クックが初めてこの周辺の海図を作成したのが18世紀後半ですから、この地域では時代を遅らせて考えたほうが妥当というケースは様々な面で見られるのですね。登場する船について言えば、河をさかのぼる小舟やタグボートには素朴な蒸気機関も使用されて始めているものの、外洋向けの大型船舶はいまだ帆走が主体という時代。マオリの人々が乗る船としてはもちろん手漕ぎの木製カヌーが多数登場します。
本編は主人公の娘がマオリ族の青年の子供を身篭るところから始まります。彼女は開拓団に属する軍医の娘であり幼い頃から父より医術の教育を受けていたのですが、このマオリの子を宿したことと医術の素養を得たことの2点がその後の彼女の軌跡を稀有のものにしてゆきます。演じるのはサマンサ・モートン。明日から国内公開される“エリザベス:ゴールデン・エイジ”でもスコットランドのメアリー女王という極めて重要な役を演じています。エリザベス最大のライヴァルといって良い存在ですね。
そして彼女を想うイギリス側の兵士として登場するのがかのキーファー・サザーランド。ドラマ“24”のジャック張りのアクションシーンも確かにあるのですが、日本では軍服姿の彼がライフルを構える姿がDVDジャケットに大きく描かれ、邦題も“ファイナル・ソルジャー”とあたかもサザーランド主人公の戦争アクション映画かのような印象を生む形で売り出されました。このためネットでこの映画の日本での感想を検索すると、この点の不満を書いたものばかりが挙がってきます。このことは騙し半分でも敢えてサザーランドを前面に出した売り手側の商業的手腕を結果的に証明するものとも言えるわけですが、それにしてもこの邦題の野暮ったさは異様です。
主人公の娘をとりあうマオリ側の戦士はクリフ・カーティスが演じています。彼の名はまだあまり知られていませんが、最近そこらじゅうのハリウッド映画に脇役出演しまくっている俳優です。過去にこの記事シリーズで扱った“ファウンテン”ではスペインの南米探検隊に属する謎のイスラム剣士として登場するし、“ダイ・ハード4.0”ではFBIの指揮官としてブルース・ウィリスを牽制します(設定はたぶんアラブ系)。メキシコ人やイラク人、インド人の役も見たことあるかも。でも本人はマオリ出身であることをこの映画を通じて初めて知りました。
実は恒例の記事タイトルに「軍医」ではなく「斥候」の語を当てようかとも考えました。娘のみごもった子がのちに斥候がやるような撹乱行為でイギリス軍を惑わせるシーンがあるためです。けれどこの子役はあまり華がなく感心できず。娘の父である軍医の役にはステファン・リー。いぶし銀の名優だけに演技の水準はキャスト陣のなかでもピカ一です。
作品全編を通しての感想としては、原生林を舞台としたロケハンがとにかく美しく、マオリの集落や開拓団の居住区を再現したセットも非常に緻密で、それだけでも見た甲斐がありました。ただストーリーの展開はやや詩的に過ぎ、説明不足のまま流れてしまうことが徒と出ているようなシーンもそこかしこにあったのはもったいないところです。往々にして制作陣の思い入れが強すぎるとこうなります。ニュージーランド人である監督のヴィンセント・ウォードはプロデューサーとしてもハリウッドで確固たる地位にある人物のようで、だからこそ採算性はどの目にも低いこうした作品にこれだけのキャストを集められたのでしょうが、‘マオリを前面に出した作品を世界に売る’という気負いがやや出すぎた観は否めません。
さて‘大航海時代Online’にもすでにマオリの人々は登場しているわけですが、彼らがゲーム内で見せている言動は感覚的に少しおかしなものに映ります。詳しくは以前の記事(2007年8月26日記事「世界独航記ノ貮」↓末尾にURL)に述べたので割愛しますが、当然ながらそう簡単にヨーロッパ人の営みに馴染んでいったわけではありません。こうしたあたりで、大航海時代のヨーロッパの人々が原住民の住む遠方の土地でどのような形で植民活動を進め、現地の人々がどのように受容していったのかに関心のあるかたには、参考になるシーンが多くある作品にもなっていると思います。
アフリカであれアメリカであれどこであれ、白人たちは一方的な侵略行為によって既存のコミュニティを征服し破壊していっただけだろうと考えるのは簡単です。しかしそこには必ず自らの行為に疑問を抱いて行動に移した人々や、逆に植民活動を利用した原住民たちなどがおり、その展開は地域ごと・時代ごとに様々な変容を見せました。
こうした価値観の異なる集団と集団との接触の帰結として個人個人の内面に生じる葛藤までを読み込むと大航海時代の世界を考える楽しみはぐっと深みを増すはずです。これは一見情緒的な作業のようでいて、実質的にはロジカルな枠組みの問題というかテキスト依存の形態に落とし込みやすい圏域なので、‘大航海時代Online’もいずれはそうした領域にまで踏み込める水準を目指してほしいなとは思います。 うん。妙なまとめかたですね。
“River Queen” by Vincent Ward [+scr] / Samantha Morton, Kiefer Sutherland, Cliff Curtis, Temuera Morrison, Stephen Rea / 113min / New Zealand, UK / 2005 ※本作品の国内上映館での公開はなし。一般流通はDVDのみ。
※※過去記事「世界独航記ノ貮」: http://diarynote.jp/d/75061/20070826.html
この絵の人物、とても綺麗なかたですよね。穏やかな表情のなかにはどこか峻然とした印象もあります。瞳は一見温かみを感じさせますが、茫漠とした目線の先にあるものへの情感がそこには欠落しているようにも思えます。華奢な撫で肩を包み込むローブのひだは、触れれば音もなく形を崩しそうなほど繊細に描かれています。
いつもとは趣向を変え、今回はいきなり脇道へ逸れてみようと思います。
▼大天使の微笑
上掲画像(クリックすると拡大します)はレオナルド・ダ・ヴィンチの代表作の一つ≪岩窟の聖母≫[1495-1508 ロンドン・ナショナルギャラリー蔵]の部分図です。ダ・ヴィンチと聞いてこの絵を見れば、その頬や唇、鼻先から眉にかけての陰影などに、モナ・リザのそれを想い起こすひとも多いことでしょう。この絵の全体像は下記URLにて。
全体図: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Leonardo_da_Vinci_027.jpg
全体図では画面の右下に位置するこのひと、とても品の良さそうな女性に見えますが、実は女性ではありません。というよりも、誰なのかわかっていません。人間ではなく天使なのは主題や背中に描かれた翼からも確かだし、天使は基本的に両性具有なので女性でないこともまた確かなのだけど、イエスの出生と逝去を見守る大天使ガブリエルなのか、洗礼者ヨハネの守護聖人である大天使ウリエルなのか、いまだ見解が割れているんですね。
そしてこの絵にはもう1つのヴァージョンが現存し、そちらはルーヴル美術館の大回廊に現在展示されています。映画“ダ・ヴィンチ・コード”では、聖杯伝説の核心に連なる貸金庫の鍵がこの絵の裏側に隠されていました。
ルーヴル版: http://www.abc-people.com/data/leonardov/021.jpg
様式論的な比較は省きますが、工房での制作過程でどちらにダ・ヴィンチ本人の筆がより多く入ったかという疑問に関しては、ルーヴル版ということでほぼ結論が出ています。日本語でこの論争について検索すると歴史学的な見地からこれに異論を唱えるサイトが上位に出てきますが、人物の顔つきだけをみても、より強い主張や繊細さが込められているのはルーヴルのほうだと感じるひとは多いでしょう。しかしこの屹立した個性のギラギラ感がロンドン版では薄められているため、当時の人々にルーヴル版よりもウケが良かったとしてもうなずける話です。たとえばこの天使の表情をとってみても、ロンドン版のほうがその相対的な凡庸さが落ち着きや優しさの情感を呼び起こしているようにも思えます。
それはさておきこのルーヴル版には、ロンドン版にはない謎がいまだ数多く残されています。画面中の天使の指先やヨハネの持物の不在などがその代表的なものですが、実はこうした謎を残す画家の姿勢こそがダ・ヴィンチのダ・ヴィンチたる所以だったりします。何しろ宗教画とは本来、その宗教の教えを視覚化することで信仰の援けとするのが本義ですから、画家の独創による謎かけなどはあまりにも余計であり、同時代には神への冒涜とすら受け取る向きもあったでしょう。実際この絵の発注元であるフランシスコ会からルーヴル版は受け取りを拒絶され、ダ・ヴィンチ晩年のパトロンであるフランス王フランソワ1世の元に置かれたことが、現在ルーヴル美術館に展示されている由来ともなりました。
油彩画ですから注文主から問題の指摘を受ければ上塗りすることもできたはずです。ゆえにそれをせず我を通したところが宗教画に対するその批評的視座とも相俟って、しばしば彼が‘最初の近代人’の一人とされる理由にもなっているように思います。
▼ミステリアスな生涯
というところで、本題へ。
レオナルド・ダ・ヴィンチといえば稀代の芸術家、万能の天才という他に、上述したような創作への姿勢に限らずどこか謎めいたイメージがつねに纏い付いています。ヨーロッパ各地を転々とした個人史にはいまだ不明な点が多く、鏡文字により遺された手記からは時代を逸脱したかのような着想の持ち主であることが窺えます。今回とりあげる“ダ・ヴィンチ ミステリアスな生涯”は、そうした彼の姿形に迫ったドラマ作品です。
さて彼の名が付く映像作品としては先にも挙げた“ダ・ヴィンチ・コード”を思い浮かべるひとが今は多そうですが、そちらをハリウッドスターを起用した美術史版インディージョーンズとするなら、本作“ダ・ヴィンチ ミステリアスな生涯”は質実に彼の軌跡を描いた大作ドキュメンタリー・ドラマとまずは言えます。
この作品は前回とり上げた“ホーンブロワー 海の勇者”同様、映画ではなくテレビ放映を前提に制作されています。1971年制作のため演出や効果音等に古風な趣きが多少目立ちますが、同じ制作意図で今日作られるとしても越えられそうにないほど作品の水準はしっかりとしています。監督はレナート・カステラーニ。他の映画作品ではカンヌのグランプリ、ヴェネツィアの金獅子賞を獲得している名匠ですが、このドラマ作品でもゴーデングローブ賞を獲得しました。
全5話272分にわたる本編では単なる生年史と作品群の紹介にとどまらず、なぜその時その言動や作品構想に到ったのかという検証を逐一踏まえながら緻密にストーリーが進行していきます。彼の没後30年あまりたってから記されたヴァザーリの『芸術家列伝』を一応の軸として、現代の研究成果も豊富に盛り込んだ形で脚本が組まれており、彼や彼の代表作にまつわる通説のうち何が事実で何が虚構なのかが説得力をもって明かされていきます。残されたデッサンや作品構想をもととした実物大の再現作品/再現映像も数多く登場するため、百聞は一見にしかずという感じでその活動内容の広さ深さ、先見性の鋭さに改めて驚かされました。
ダ・ヴィンチはよく知られているように自身の腕を買ってくれる諸侯を生涯渡り歩いたため、その生年史を少々知っているくらいでは周囲との人間関係が混乱しがちなのですが、本編中にはミケランジェロやラファエロ、チェーザレ・ボルジアやルドヴィーコ・スフォルツァ(ミラノ公)といった同時代人たちがたびたび登場してくるため、彼らとの関わりの実相も窺い知ることができる作品になっています。史実上の登場人物たちの作り込みに対してはそれぞれダ・ヴィンチ作品や同時代の肖像画等の画中人物に似た俳優が起用され、マニアックな見方かもしれませんがその点でも衣装ともどもなかなか凝った出来で見応えがありました。(ex.フランソワ1世の肖像画、ラファエロの自画像など)
当時タブー視されていた死体研究を断行することによる世間との軋轢や、親戚の遺産相続を巡るスノビッシュな立ち回りなど、彼の卓越した面とは別に人間臭い側面の描写にも重点が置かれており、このバランス感覚がドラマに見た目以上の深い奥行きを与えています。季節はこれから冬本番となりますが、年暮れのせわしなさを離れて束の間のくつろぎを味わいたいかたになど、おすすめです。
"La Vita di Leonardo Da Vinci" by Renato Castellani / Philippe Leroy, Giulio Bosetti, Ann Odessa / 272min [5 episodes] / Spain, Italy / 1971
いつもとは趣向を変え、今回はいきなり脇道へ逸れてみようと思います。
▼大天使の微笑
上掲画像(クリックすると拡大します)はレオナルド・ダ・ヴィンチの代表作の一つ≪岩窟の聖母≫[1495-1508 ロンドン・ナショナルギャラリー蔵]の部分図です。ダ・ヴィンチと聞いてこの絵を見れば、その頬や唇、鼻先から眉にかけての陰影などに、モナ・リザのそれを想い起こすひとも多いことでしょう。この絵の全体像は下記URLにて。
全体図: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Leonardo_da_Vinci_027.jpg
全体図では画面の右下に位置するこのひと、とても品の良さそうな女性に見えますが、実は女性ではありません。というよりも、誰なのかわかっていません。人間ではなく天使なのは主題や背中に描かれた翼からも確かだし、天使は基本的に両性具有なので女性でないこともまた確かなのだけど、イエスの出生と逝去を見守る大天使ガブリエルなのか、洗礼者ヨハネの守護聖人である大天使ウリエルなのか、いまだ見解が割れているんですね。
そしてこの絵にはもう1つのヴァージョンが現存し、そちらはルーヴル美術館の大回廊に現在展示されています。映画“ダ・ヴィンチ・コード”では、聖杯伝説の核心に連なる貸金庫の鍵がこの絵の裏側に隠されていました。
ルーヴル版: http://www.abc-people.com/data/leonardov/021.jpg
様式論的な比較は省きますが、工房での制作過程でどちらにダ・ヴィンチ本人の筆がより多く入ったかという疑問に関しては、ルーヴル版ということでほぼ結論が出ています。日本語でこの論争について検索すると歴史学的な見地からこれに異論を唱えるサイトが上位に出てきますが、人物の顔つきだけをみても、より強い主張や繊細さが込められているのはルーヴルのほうだと感じるひとは多いでしょう。しかしこの屹立した個性のギラギラ感がロンドン版では薄められているため、当時の人々にルーヴル版よりもウケが良かったとしてもうなずける話です。たとえばこの天使の表情をとってみても、ロンドン版のほうがその相対的な凡庸さが落ち着きや優しさの情感を呼び起こしているようにも思えます。
それはさておきこのルーヴル版には、ロンドン版にはない謎がいまだ数多く残されています。画面中の天使の指先やヨハネの持物の不在などがその代表的なものですが、実はこうした謎を残す画家の姿勢こそがダ・ヴィンチのダ・ヴィンチたる所以だったりします。何しろ宗教画とは本来、その宗教の教えを視覚化することで信仰の援けとするのが本義ですから、画家の独創による謎かけなどはあまりにも余計であり、同時代には神への冒涜とすら受け取る向きもあったでしょう。実際この絵の発注元であるフランシスコ会からルーヴル版は受け取りを拒絶され、ダ・ヴィンチ晩年のパトロンであるフランス王フランソワ1世の元に置かれたことが、現在ルーヴル美術館に展示されている由来ともなりました。
油彩画ですから注文主から問題の指摘を受ければ上塗りすることもできたはずです。ゆえにそれをせず我を通したところが宗教画に対するその批評的視座とも相俟って、しばしば彼が‘最初の近代人’の一人とされる理由にもなっているように思います。
▼ミステリアスな生涯
というところで、本題へ。
レオナルド・ダ・ヴィンチといえば稀代の芸術家、万能の天才という他に、上述したような創作への姿勢に限らずどこか謎めいたイメージがつねに纏い付いています。ヨーロッパ各地を転々とした個人史にはいまだ不明な点が多く、鏡文字により遺された手記からは時代を逸脱したかのような着想の持ち主であることが窺えます。今回とりあげる“ダ・ヴィンチ ミステリアスな生涯”は、そうした彼の姿形に迫ったドラマ作品です。
さて彼の名が付く映像作品としては先にも挙げた“ダ・ヴィンチ・コード”を思い浮かべるひとが今は多そうですが、そちらをハリウッドスターを起用した美術史版インディージョーンズとするなら、本作“ダ・ヴィンチ ミステリアスな生涯”は質実に彼の軌跡を描いた大作ドキュメンタリー・ドラマとまずは言えます。
この作品は前回とり上げた“ホーンブロワー 海の勇者”同様、映画ではなくテレビ放映を前提に制作されています。1971年制作のため演出や効果音等に古風な趣きが多少目立ちますが、同じ制作意図で今日作られるとしても越えられそうにないほど作品の水準はしっかりとしています。監督はレナート・カステラーニ。他の映画作品ではカンヌのグランプリ、ヴェネツィアの金獅子賞を獲得している名匠ですが、このドラマ作品でもゴーデングローブ賞を獲得しました。
全5話272分にわたる本編では単なる生年史と作品群の紹介にとどまらず、なぜその時その言動や作品構想に到ったのかという検証を逐一踏まえながら緻密にストーリーが進行していきます。彼の没後30年あまりたってから記されたヴァザーリの『芸術家列伝』を一応の軸として、現代の研究成果も豊富に盛り込んだ形で脚本が組まれており、彼や彼の代表作にまつわる通説のうち何が事実で何が虚構なのかが説得力をもって明かされていきます。残されたデッサンや作品構想をもととした実物大の再現作品/再現映像も数多く登場するため、百聞は一見にしかずという感じでその活動内容の広さ深さ、先見性の鋭さに改めて驚かされました。
ダ・ヴィンチはよく知られているように自身の腕を買ってくれる諸侯を生涯渡り歩いたため、その生年史を少々知っているくらいでは周囲との人間関係が混乱しがちなのですが、本編中にはミケランジェロやラファエロ、チェーザレ・ボルジアやルドヴィーコ・スフォルツァ(ミラノ公)といった同時代人たちがたびたび登場してくるため、彼らとの関わりの実相も窺い知ることができる作品になっています。史実上の登場人物たちの作り込みに対してはそれぞれダ・ヴィンチ作品や同時代の肖像画等の画中人物に似た俳優が起用され、マニアックな見方かもしれませんがその点でも衣装ともどもなかなか凝った出来で見応えがありました。(ex.フランソワ1世の肖像画、ラファエロの自画像など)
当時タブー視されていた死体研究を断行することによる世間との軋轢や、親戚の遺産相続を巡るスノビッシュな立ち回りなど、彼の卓越した面とは別に人間臭い側面の描写にも重点が置かれており、このバランス感覚がドラマに見た目以上の深い奥行きを与えています。季節はこれから冬本番となりますが、年暮れのせわしなさを離れて束の間のくつろぎを味わいたいかたになど、おすすめです。
"La Vita di Leonardo Da Vinci" by Renato Castellani / Philippe Leroy, Giulio Bosetti, Ann Odessa / 272min [5 episodes] / Spain, Italy / 1971
Job Description 11: 上級士官 【ホーンブロワー 海の勇者】
2007年10月23日 就職・転職 コメント (6)
“マスター・アンド・コマンダー”から始めた当記事シリーズも、気づけば10編を超えました。そこで今回は原点回帰という意味も込め“ホーンブロワー 海の勇者”をとり上げます。この作品はC.S.フォレスターの帆船小説を映像化したもので、フランスと鋭く対立する当時の英国海軍下でのちの名艦長としての頭角を露わにしていく主人公を描いています。
17歳で士官候補生として任官した主人公ホレーショ・ホーンブロワーは、当時の英国海軍が組織として抱えていた矛盾やフランス・スペインとの激しい抗争のなかで揉まれ、時に命を賭けた強行手段や敵軍の渦中でのロマンスなどを演じつつ一人の軍人としてたくましく成長していき、やがては海尉を経て一隻の軍船を任される艦長へと出世を遂げます。
この作品の何よりの特徴は、映画よりも長尺のテレビドラマとして制作されたために、過去に当記事シリーズで紹介してきたどの作品よりも登場人物一人一人の造形が細やかに描かれていることです。主人公と切磋琢磨する同期の士官候補生たちや、彼らを見守りのちのちは共に闘っていく上官たち、まだ右も左も分からないような主人公を支え成長後は忠実な部下となっていく古参の老水夫や熟練水兵、激しく斬り結ぶ敵国の軍人すらも深い魅力を湛えたキャラクターとして活躍しています。
文学作品が映像化されると、得てして原作を追いかけるだけのストーリーがだらだらと展開しがちですが、そこがこの作品は大きく違っていて脚本・演出・登場人物等々に独自の要素が多分に組み込まれ、見終えたあとになって初めて気づくような巧妙な伏線も無数に配されています。この点は“ホーンブロワー 海の勇者”のもう一つの特徴と言えるもので、このために一見ありがちな歴史物ドラマのような外観をもちながら、一度見始めるとやみつきになるような魅力がにじみ出てくるんですね。
本編は3部構成、全8エピソード。登場人物や時代背景等の連関は保ちつつも、100分の尺をもつ各エピソードはそれぞれに一応独立しています。登場する主要船舶のいくつかは模型やCGに頼らず実物の帆船が再現されており、カリブの要塞や牢獄、軍港ポーツマスやブレストのセットなどもテレビドラマとしてはちょっと信じられないほどに手の込んだものが登場します。英米で制作されるドラマには時々奇跡のような珠玉の水準をいくものが登場しますが、この作品も紛れもなくその類に入っています。第4部以降のシリーズ続行は制作会社によって否定されているようですが、残念だけれどそれもそのはず。これだけのクオリティを発揮できるのは制作会社、業界、ひいてはその国の社会経済が良い状態に保たれている時期だけだろうとも思います。
少し個人的な好みを言うと、主人公が駆け出しの頃から何かと世話を焼き、やがて若き艦長へと出世を遂げた主人公と絶対の信頼関係を結ぶことになる老掌帆長のマシューズと、出会ったときには上官でありながら主人公の類稀な才覚に早くから気づき、第3部では有能な副長として他に代え難い存在になっていくウィリアム・ブッシュの2人はもう大ファンになってしまいました。(笑) また海軍提督として全シリーズを通して主人公を見守り鍛え上げていくサー・エドワード・ペリューの出てくる場面も、組織の幹部としての威厳と息子に対するようなまなざしの醸すコミカルさが絶妙に混ざり合って毎回味わいのあるものになっています。提督を演じる役者ロバート・リンゼイの演技力にはたびたび目を見張らされました。
ちなみにこのペリュー提督は彼の指揮するフリゲート艦HMSインディファティガブルとともに史実上の存在で、他にも実在した人物・艦船が時折登場することも本篇に彩りを与えています。主人公はもちろん架空の人物ですがファーストネームの‘ホレーショ’が英国海軍きっての英雄ホレイショ・ネルソンに由来することは疑いようのないところですね。ネルソンは作戦立案の段階からすでに当時の海軍における慣習を逸脱しているところがありましたから、実際の会戦域における鬼謀ぶりともども小説のモデルとするのにうってつけの存在とも言えるのかもしれません。
また“大航海時代Online”の特に海事メインのプレイヤーにとって本作品は、“マスター・アンド・コマンダー”や“パイレーツ・オブ・カリビアン”などに比べても見どころの多い作品になっていると思います。とりわけ冒頭からフランスの偽装商船を拿捕してしまう第3部などは、船首砲による敵船の減速、速度差を読み込んだ敵船メインマストの破砕、目視できない艦隊との浅瀬での神経戦などなど、戦闘そのものの再現にも強い力点が置かれており垂涎ものです。
日本ではNHK-BSが過去に幾度か放映したほか、CS系列のテレビ局などでも時折放送されているようです。国内版DVDも出ています。かくいうこの10月にもミステリーチャンネルというCS局で全作品が順次放映中だったり。12月にも放送予定あり。[関連URL↓]
http://www.mystery.co.jp/program/hornblower.html
また国内の某人気動画サイトでも現在全シリーズを鑑賞可能です。とはいえこちらは著作権の問題上いつ削除されても不思議はないし画質も悪くお勧めはしませんけれど。(笑)
最後によくできた日本語版ファンサイトもご紹介。コンテンツが豊富です。
http://www.interq.or.jp/venus/blanca/blue/hornblower/
ともあれドラマ作品本体は歴史物ということもあって5年や10年で古色を帯びる質のものではないため、今後も長くいろいろな場所で放映される機会がありそうです。一見の価値はあり。秋の夜長にお薦めします。
"Hornblower" by Andrew Grieve / Ioan Gruffudd, Robert Lindsay, Paul McGann, Paul Copley, Sean Gilder / C.S.Forester [book author] / 100min x 8 episodes / UK / 1998-2003
17歳で士官候補生として任官した主人公ホレーショ・ホーンブロワーは、当時の英国海軍が組織として抱えていた矛盾やフランス・スペインとの激しい抗争のなかで揉まれ、時に命を賭けた強行手段や敵軍の渦中でのロマンスなどを演じつつ一人の軍人としてたくましく成長していき、やがては海尉を経て一隻の軍船を任される艦長へと出世を遂げます。
この作品の何よりの特徴は、映画よりも長尺のテレビドラマとして制作されたために、過去に当記事シリーズで紹介してきたどの作品よりも登場人物一人一人の造形が細やかに描かれていることです。主人公と切磋琢磨する同期の士官候補生たちや、彼らを見守りのちのちは共に闘っていく上官たち、まだ右も左も分からないような主人公を支え成長後は忠実な部下となっていく古参の老水夫や熟練水兵、激しく斬り結ぶ敵国の軍人すらも深い魅力を湛えたキャラクターとして活躍しています。
文学作品が映像化されると、得てして原作を追いかけるだけのストーリーがだらだらと展開しがちですが、そこがこの作品は大きく違っていて脚本・演出・登場人物等々に独自の要素が多分に組み込まれ、見終えたあとになって初めて気づくような巧妙な伏線も無数に配されています。この点は“ホーンブロワー 海の勇者”のもう一つの特徴と言えるもので、このために一見ありがちな歴史物ドラマのような外観をもちながら、一度見始めるとやみつきになるような魅力がにじみ出てくるんですね。
本編は3部構成、全8エピソード。登場人物や時代背景等の連関は保ちつつも、100分の尺をもつ各エピソードはそれぞれに一応独立しています。登場する主要船舶のいくつかは模型やCGに頼らず実物の帆船が再現されており、カリブの要塞や牢獄、軍港ポーツマスやブレストのセットなどもテレビドラマとしてはちょっと信じられないほどに手の込んだものが登場します。英米で制作されるドラマには時々奇跡のような珠玉の水準をいくものが登場しますが、この作品も紛れもなくその類に入っています。第4部以降のシリーズ続行は制作会社によって否定されているようですが、残念だけれどそれもそのはず。これだけのクオリティを発揮できるのは制作会社、業界、ひいてはその国の社会経済が良い状態に保たれている時期だけだろうとも思います。
少し個人的な好みを言うと、主人公が駆け出しの頃から何かと世話を焼き、やがて若き艦長へと出世を遂げた主人公と絶対の信頼関係を結ぶことになる老掌帆長のマシューズと、出会ったときには上官でありながら主人公の類稀な才覚に早くから気づき、第3部では有能な副長として他に代え難い存在になっていくウィリアム・ブッシュの2人はもう大ファンになってしまいました。(笑) また海軍提督として全シリーズを通して主人公を見守り鍛え上げていくサー・エドワード・ペリューの出てくる場面も、組織の幹部としての威厳と息子に対するようなまなざしの醸すコミカルさが絶妙に混ざり合って毎回味わいのあるものになっています。提督を演じる役者ロバート・リンゼイの演技力にはたびたび目を見張らされました。
ちなみにこのペリュー提督は彼の指揮するフリゲート艦HMSインディファティガブルとともに史実上の存在で、他にも実在した人物・艦船が時折登場することも本篇に彩りを与えています。主人公はもちろん架空の人物ですがファーストネームの‘ホレーショ’が英国海軍きっての英雄ホレイショ・ネルソンに由来することは疑いようのないところですね。ネルソンは作戦立案の段階からすでに当時の海軍における慣習を逸脱しているところがありましたから、実際の会戦域における鬼謀ぶりともども小説のモデルとするのにうってつけの存在とも言えるのかもしれません。
また“大航海時代Online”の特に海事メインのプレイヤーにとって本作品は、“マスター・アンド・コマンダー”や“パイレーツ・オブ・カリビアン”などに比べても見どころの多い作品になっていると思います。とりわけ冒頭からフランスの偽装商船を拿捕してしまう第3部などは、船首砲による敵船の減速、速度差を読み込んだ敵船メインマストの破砕、目視できない艦隊との浅瀬での神経戦などなど、戦闘そのものの再現にも強い力点が置かれており垂涎ものです。
日本ではNHK-BSが過去に幾度か放映したほか、CS系列のテレビ局などでも時折放送されているようです。国内版DVDも出ています。かくいうこの10月にもミステリーチャンネルというCS局で全作品が順次放映中だったり。12月にも放送予定あり。[関連URL↓]
http://www.mystery.co.jp/program/hornblower.html
また国内の某人気動画サイトでも現在全シリーズを鑑賞可能です。とはいえこちらは著作権の問題上いつ削除されても不思議はないし画質も悪くお勧めはしませんけれど。(笑)
最後によくできた日本語版ファンサイトもご紹介。コンテンツが豊富です。
http://www.interq.or.jp/venus/blanca/blue/hornblower/
ともあれドラマ作品本体は歴史物ということもあって5年や10年で古色を帯びる質のものではないため、今後も長くいろいろな場所で放映される機会がありそうです。一見の価値はあり。秋の夜長にお薦めします。
"Hornblower" by Andrew Grieve / Ioan Gruffudd, Robert Lindsay, Paul McGann, Paul Copley, Sean Gilder / C.S.Forester [book author] / 100min x 8 episodes / UK / 1998-2003
中世の甲冑に身を固めたコンキスタドール(征服者)が、罠と知りつつ密林にそびえるマヤの神殿へと足を踏み入れるシーンからこの映画は始まります。故国スペインの女王への忠誠を誓う言葉を口にしながらふりそそぐ矢と槍をかいくぐって男は前進し、急角度で階段状にせり上がった石造神殿の頂きへと辿りつくと、そこには……。
3つの時代に舞台がまたがり、相互のシーンが激しく入れ替わりながらストーリーは進行します。残る2つの舞台は現代の最新医療の現場と、未来あるいは異次元の宇宙に浮かぶ‘生命の樹’の樹下。この‘生命の樹’についてはオープニング直後に旧約聖書・創世記の一節が示されることで、その所在が作品全体をつらぬくテーマであることが暗示されます。
創世記において神は土くれから人をつくり生命の息を吹き込むと、東にエデンの園をつくりそこへ住まわせます。このエデンの園の中央に植えられたのが知恵の樹と生命の樹で、‘知恵の樹’の実は知性を、‘生命の樹’の実は永遠の命をもたらしました。よく知られているように人はこの‘知恵の樹’の実を食したことでエデンの園から追放されてしまいます。生命の樹のその後について、旧約聖書はこう記しています。
‘こうして神は人を追放した。そしてエデンの園の東に、ケルビムと回る炎の剣を置いて、生命の樹への道を守らせるようにした’ -創世記3章24節
ではこの‘生命の樹’、現実にはどこにあるのか。あるいはあったのか。こうした設問は一見突拍子もないようにも映りますが、トロイを発掘したシュリーマンを例に出さずとも、神話・伝説の類が現代においてもある一定の真実を含みうると認められていることもまた疑いのないところです。であればこそこのような舞台設定が活きるわけですが、それが象徴的なイメージであればあるほど下手に映像化すれば陳腐かつ悲惨このうえない状況を招きますから、本編中に幾度も‘生命の樹’を登場させてしまう本作の挑戦的な姿勢にはその個別の成否はともかく感心しきりでした。
監督はダーレン・アロノフスキー。“π(パイ)”[1997]、“レクイエム・フォー・ドリーム”[2000]に続く監督3作目。前2作はその斬新な画作りが注目を浴びましたが、今回はストーリーの規模がまったく異なるのもあってか前衛性の点ではトーンダウンした感じに。
また彼の作品はどれも実験的な姿勢や思弁的な方向性が強い一方セットや小道具にも力が入っていて、本作でもたとえばスペインの女王から主人公がマヤ探検の密命を受ける場面での、アルハンブラ宮殿を思わせる東西折衷的な王城のつくりなどは意外に見ごたえがありました。そこから突然最新鋭の医療設備が並ぶ全面ガラス張りの研究施設へと画面が切り替わるのですから、これだけでもなかなかに新鮮な映像体験でした。どんなにごたごたしたシーンでも透徹した空気感を出せるところも、この監督の長所かもしれません。
ただアロノフスキーもまた欧米のこの世代(30代後半〜40代前半くらい)の表現者にはもはや共通すると言ってもよい種の妙な東洋嗜好をもっていて、“π”では劇中の重要なアイテムとして囲碁が登場しましたが、本作でも主人公が作務衣を着て座禅を組むイメージが幾度か登場してきます。異文化に対するリスペクトが十分に感じられるので文句をつける気はないのですが、表面的な東洋理解がこのように記号化されたイメージへと帰結していくのを見ると、何だか‘結局それかい’というような拍子抜け感を覚えるのも確かですね。
BGM演奏をクロノス・クァルテット(Kronos Quartet)が担当していることも見逃せません。彼らは現代音楽を本領とする弦楽四重奏団なのですが、スティーヴ・ライヒからビル・エヴァンズ、ジミヘンからビョークまでと彼らほど多岐に渡る分野で第一線のミュージシャンと共演してきたグループも他にないんじゃないかというほどに懐の深い実力を備えています。むしろラストのほうなど彼らの演奏のBGVとして映像を観るのもアリかも。
ちなみに邦題では“ファウンテン 永遠につづく愛”とサブタイトルが付いています。ファウンテン(fountain: 泉)の語はカタカナとしてはこなれてないので副題を付けた意図はわかるのですが、この副題につられ恋愛モノと期待して作品を観るとラストの展開がまったく感情移入しがたいものになりそうであまり良いネーミングとは思えません。といってもまあ終盤のシークエンスは理解しろというほうが無理な種類のものなんですが。
アロノフスキーがタイトルに“泉”を採用したことには恐らく、前作“レクイエム・フォー・ドリーム”の原作者でありアロノフスキーと共同脚本の筆も執ったヒューバート・セルビー・Jr(Hubert Selby Jr.)の思想が影響していそうです。DVD版“レクイエム〜”の映像特典に入っているインタビューでセルビー・Jrは、‘万物は瞳に映し出された像であり、瞳は万物を映し出す豊穣な泉なのだ!’というようなことを力説しているんですね。すでにかなりの高齢なのですが、よぼよぼになってもエネルギッシュに自らの精神世界を展開させるこういうおじいちゃんってかなり好きです。(笑)
公式HP: http://microsites2.foxinternational.com/jp/fountain/
※ 全国12都市にて目下公開中。たぶん空いてます…。
"The Fountain" by Darren Aronofsky [+scr] / Hugh Jackman,Rachel Weisz,Cliff Curtis / Clint Mansell [music score] / Kronos Quartet [music perform.] / 95min / US / 2006
3つの時代に舞台がまたがり、相互のシーンが激しく入れ替わりながらストーリーは進行します。残る2つの舞台は現代の最新医療の現場と、未来あるいは異次元の宇宙に浮かぶ‘生命の樹’の樹下。この‘生命の樹’についてはオープニング直後に旧約聖書・創世記の一節が示されることで、その所在が作品全体をつらぬくテーマであることが暗示されます。
創世記において神は土くれから人をつくり生命の息を吹き込むと、東にエデンの園をつくりそこへ住まわせます。このエデンの園の中央に植えられたのが知恵の樹と生命の樹で、‘知恵の樹’の実は知性を、‘生命の樹’の実は永遠の命をもたらしました。よく知られているように人はこの‘知恵の樹’の実を食したことでエデンの園から追放されてしまいます。生命の樹のその後について、旧約聖書はこう記しています。
‘こうして神は人を追放した。そしてエデンの園の東に、ケルビムと回る炎の剣を置いて、生命の樹への道を守らせるようにした’ -創世記3章24節
ではこの‘生命の樹’、現実にはどこにあるのか。あるいはあったのか。こうした設問は一見突拍子もないようにも映りますが、トロイを発掘したシュリーマンを例に出さずとも、神話・伝説の類が現代においてもある一定の真実を含みうると認められていることもまた疑いのないところです。であればこそこのような舞台設定が活きるわけですが、それが象徴的なイメージであればあるほど下手に映像化すれば陳腐かつ悲惨このうえない状況を招きますから、本編中に幾度も‘生命の樹’を登場させてしまう本作の挑戦的な姿勢にはその個別の成否はともかく感心しきりでした。
監督はダーレン・アロノフスキー。“π(パイ)”[1997]、“レクイエム・フォー・ドリーム”[2000]に続く監督3作目。前2作はその斬新な画作りが注目を浴びましたが、今回はストーリーの規模がまったく異なるのもあってか前衛性の点ではトーンダウンした感じに。
また彼の作品はどれも実験的な姿勢や思弁的な方向性が強い一方セットや小道具にも力が入っていて、本作でもたとえばスペインの女王から主人公がマヤ探検の密命を受ける場面での、アルハンブラ宮殿を思わせる東西折衷的な王城のつくりなどは意外に見ごたえがありました。そこから突然最新鋭の医療設備が並ぶ全面ガラス張りの研究施設へと画面が切り替わるのですから、これだけでもなかなかに新鮮な映像体験でした。どんなにごたごたしたシーンでも透徹した空気感を出せるところも、この監督の長所かもしれません。
ただアロノフスキーもまた欧米のこの世代(30代後半〜40代前半くらい)の表現者にはもはや共通すると言ってもよい種の妙な東洋嗜好をもっていて、“π”では劇中の重要なアイテムとして囲碁が登場しましたが、本作でも主人公が作務衣を着て座禅を組むイメージが幾度か登場してきます。異文化に対するリスペクトが十分に感じられるので文句をつける気はないのですが、表面的な東洋理解がこのように記号化されたイメージへと帰結していくのを見ると、何だか‘結局それかい’というような拍子抜け感を覚えるのも確かですね。
BGM演奏をクロノス・クァルテット(Kronos Quartet)が担当していることも見逃せません。彼らは現代音楽を本領とする弦楽四重奏団なのですが、スティーヴ・ライヒからビル・エヴァンズ、ジミヘンからビョークまでと彼らほど多岐に渡る分野で第一線のミュージシャンと共演してきたグループも他にないんじゃないかというほどに懐の深い実力を備えています。むしろラストのほうなど彼らの演奏のBGVとして映像を観るのもアリかも。
ちなみに邦題では“ファウンテン 永遠につづく愛”とサブタイトルが付いています。ファウンテン(fountain: 泉)の語はカタカナとしてはこなれてないので副題を付けた意図はわかるのですが、この副題につられ恋愛モノと期待して作品を観るとラストの展開がまったく感情移入しがたいものになりそうであまり良いネーミングとは思えません。といってもまあ終盤のシークエンスは理解しろというほうが無理な種類のものなんですが。
アロノフスキーがタイトルに“泉”を採用したことには恐らく、前作“レクイエム・フォー・ドリーム”の原作者でありアロノフスキーと共同脚本の筆も執ったヒューバート・セルビー・Jr(Hubert Selby Jr.)の思想が影響していそうです。DVD版“レクイエム〜”の映像特典に入っているインタビューでセルビー・Jrは、‘万物は瞳に映し出された像であり、瞳は万物を映し出す豊穣な泉なのだ!’というようなことを力説しているんですね。すでにかなりの高齢なのですが、よぼよぼになってもエネルギッシュに自らの精神世界を展開させるこういうおじいちゃんってかなり好きです。(笑)
公式HP: http://microsites2.foxinternational.com/jp/fountain/
※ 全国12都市にて目下公開中。たぶん空いてます…。
"The Fountain" by Darren Aronofsky [+scr] / Hugh Jackman,Rachel Weisz,Cliff Curtis / Clint Mansell [music score] / Kronos Quartet [music perform.] / 95min / US / 2006
Job Description 9: 剣士 【アポカリプト】
2007年7月25日 就職・転職 コメント (4)
16世紀中央アメリカの密林の奥深く、スペインの侵攻を控えマヤ文明は最後の輝きを放っていました。映画の主人公ジャグァは辺縁の一部族に生まれ、妻子とともに部族間の熾烈な抗争にまき込まれてゆきます。
今回はポイントを3つに絞ります。全編マヤ語であること、敵役へのコンテンポラリーダンサーの起用、そして監督のメル・ギブソンについて。
◆全編がマヤ語
この作品が全編マヤ語で製作されたことは公開前から話題となりました。衣装にもセットにもこだわるのに言葉だけが現代英語(or日本製なら日本語)、みたいな歴史劇が普通に受け入れられるなかでこの達成は特筆に値します。むろんここには製作者の意図だけでなく‘全編字幕になっても現地語が良い’という方向への観客サイドの意識変化があることは言うまでもありません。“硫黄島からの手紙”[2006]や“バベル”[2006]といった高水準でかつ集客力のある作品にこうした傾向が見られることは、近年の大きな流れの一つと言ってよさそうです。
メル・ギブソンは前作(後述)でもアラム語(ヘブライ語混じり)やラテン語のみで脚本を仕上げていますから、もともとこういう映画を作りたかったのかも。
◆敵役へのダンサーの起用
主要キャストがほとんど前歴のない俳優たちで占められたことも話題に。もっともスコットランドの英雄を描いた初監督作の“ブレイブ・ハート”[1995]でも、メル・ギブソンは演劇学校を出たばかりの新人女優をヒロインに抜擢していますからこの点はさして驚くにあたらないのですが、そんななかで一人だけ出演者にフォーカスするなら、やはりラオール・トゥルヒロ(Raoul Trujillo)の存在は見逃せないところです。彼は本編のなかで主人公の青年を執拗に追い詰める戦闘的な部族の長ゼロ・ウルフを演じているのですが、壮年にも関わらず四肢の動きがいちいちキレと凄味を感じさせて、要するに無茶苦茶カッコよかったんですね。
とはいえわたしもこの役者を意識したのは初めてだったので、映画を観終わったあとネットで調べて驚きました。なんとこのひと、アパッチ族やユト族といったネイティヴアメリカンの血をひく、プロのコンテンポラリーダンサーだったのです。下記サイトの二人目に特集されているので興味のある方はどうぞ。
Native Peoples Magazine:
http://www.nativepeoples.com/article/articles/149/
さらに驚いたことに、わたしは前にも彼の演技を観ていたのです。このブログでも以前にとり上げたテレンス・マリックの“ニュー・ワールド”[2005]に出ていました。(というか当該記事[本ブログ2月24日記事]の画像の人物がそうです。‘DVDのながら観’だったからか意識化するに至らなかったものの、画像に使用したくらいなのでどこか引っかかっていたのかも)
プロの踊り手がアクション系の時代物で敵のボス役を演じている近例としては、日本では“たそがれ清兵衛”[2002]がすぐに思い浮かぶところです。現代舞踏家の田中泯はこの作品で妖艶なまでの剣技(というか足技)を披露してみせましたが、これは彼と戦う主人公を演じた真田広之が身体的な素養としても世界水準に達している役者であればこそでした。そうした意味で本作でのラオール・トゥルヒロの身体のキレを引き立てているのはジャングルの大自然と言えそうです。密林の土を足指でがっちりと踏みしめ、草葉を巻き上げて疾走していく姿は見応えがありました。
コンテンポラリーダンスというとなにか取っつきにくい印象もありますが、モダンダンスへの反駁というほか特に総括的な定義はないのが現状なので、非欧米圏におけるコンテンポラリーダンスの潮流としては往々にしてローカルな伝統文化に基づく身振りがクローズアップされてきます。この意味でラオール・トゥルヒロと田中泯の商業映画への起用とその成功には同じ論理が通底していそうです。個人的にこれは意外な発見でした。
◆メル・ギブソン監督作
メル・ギブソンの監督作としての前作“パッション (The Passion of The Christ)”[2004]は、血みどろのイエス・キリストを巡る表現が世上を賑わせましたが、本作“アポカリプト”においても残虐的な戦闘シーンはもとより、生贄の儀式や昆虫の首をもいで治療に使うシーンなど、その異色さは健在。この両作品で彼の映画監督としての立ち位置はほぼ固まったように思います。
以前この記事シリーズのコメント欄で少し述べたこともありますが(“ミッション”2006年8月5日記事)、やはりbloody-dirtyな手触りは彼の表現手法の根底に抜きがたく横たわっているようで、単に世間の耳目をひくために付加されたセンセーショナルな演出というよりは、むしろこうした暴力性の充溢こそが作品の本質になっています。
ただしここで注意しなければならないのは、映像表現として立ち現われてくるのはあくまで作り手もしくは受け手の内なる何かに過ぎないという点です。そのためこの場合であれば現代文明における‘暴力’が必ずしも他の文明にとっても‘暴力’たりえないのが当然である一方で、商業映画におけるストーリー進行は観客の共感を導くものであることが宿命づけられているために、他の文明を扱う際にはこの点での齟齬をどう乗り越えるかが大問題となってくるんですね。たとえば“パール・ハーバー”[2001]に登場する戯画的な日本人像に比べ、先にも挙げた“硫黄島からの手紙”でクリント・イーストウッドは極限下における人間倫理の普遍を描くことによりこの点をきっちりとクリアしていますが、メル・ギブソンは逆に徹頭徹尾アクション描写にこだわることでこうしたズレを無化する方法を採っています。
したがって“アポカリプト”の文明論的な部分を切り取って正しい正しくないと批評するのはそもそもがお門違いということにたぶんなります。たとえば生贄の儀式のシーンでマヤの司祭が民衆を前に現代の西洋人っぽい名声欲を丸出しにしたり、生贄の青年があたかも夏休みの旅行中に誘拐されて殺される前のバックパッカーのような反応を見せたりすることにはおかしさを感じざるをえないのですが、そこは監督本人もとうに開き直っているはずです。そもそもこの作品に比較文明論的な視座を見いだせるとしても、それは実際問題としてどうでもいいことなんですよね。最後のほうではスペインのガレオン艦隊が上陸を開始するシーンもありますが、やはり説明的な挿話以上のものにはなってなかったり。
メル・ギブソンは私生活では熱狂的なクリスチャンとして知られる一方で、“アポカリプト”公開前にはユダヤ人差別発言で物議を醸したりも。映画産業にユダヤ系資本が深く噛み込んでいる現状でこのパフォーマンスは致命的とも思えましたが、公開してみると真逆の大入り状態に。また俳優としての昨今のメル・ギブソンを観てみたいひとにはヴィム・ヴェンダース監督の“ミリオンダラー・ホテル”[2000]が一押し。すっごい変です。でも彼以外は考えられないほどのハマリ役。
“アポカリプト”の音楽を担当しているのはジェームス・ホーナー。“ニュー・ワールド”と同じです。ここらへんの調子の良さもメル・ギブソンならではかも。ここではいろいろと突っ込んだことを書いてますが、作品自体は頭をカラっぽにして楽しめる上質のチェイス物アクション映画になっています。おススメです。
"Apocalypto" by Mel Gibson [+scr] / Rudy Youngblood,Dalia Hernandez,Raoul Trujillo / James Horner [music] / 138min / US / 2006
※ 国内では先月半ば公開の新作ですが、早くも終了しだしています。これから観に行くかたはお急ぎを。レンタル開始はたぶん11月くらい。
今回はポイントを3つに絞ります。全編マヤ語であること、敵役へのコンテンポラリーダンサーの起用、そして監督のメル・ギブソンについて。
◆全編がマヤ語
この作品が全編マヤ語で製作されたことは公開前から話題となりました。衣装にもセットにもこだわるのに言葉だけが現代英語(or日本製なら日本語)、みたいな歴史劇が普通に受け入れられるなかでこの達成は特筆に値します。むろんここには製作者の意図だけでなく‘全編字幕になっても現地語が良い’という方向への観客サイドの意識変化があることは言うまでもありません。“硫黄島からの手紙”[2006]や“バベル”[2006]といった高水準でかつ集客力のある作品にこうした傾向が見られることは、近年の大きな流れの一つと言ってよさそうです。
メル・ギブソンは前作(後述)でもアラム語(ヘブライ語混じり)やラテン語のみで脚本を仕上げていますから、もともとこういう映画を作りたかったのかも。
◆敵役へのダンサーの起用
主要キャストがほとんど前歴のない俳優たちで占められたことも話題に。もっともスコットランドの英雄を描いた初監督作の“ブレイブ・ハート”[1995]でも、メル・ギブソンは演劇学校を出たばかりの新人女優をヒロインに抜擢していますからこの点はさして驚くにあたらないのですが、そんななかで一人だけ出演者にフォーカスするなら、やはりラオール・トゥルヒロ(Raoul Trujillo)の存在は見逃せないところです。彼は本編のなかで主人公の青年を執拗に追い詰める戦闘的な部族の長ゼロ・ウルフを演じているのですが、壮年にも関わらず四肢の動きがいちいちキレと凄味を感じさせて、要するに無茶苦茶カッコよかったんですね。
とはいえわたしもこの役者を意識したのは初めてだったので、映画を観終わったあとネットで調べて驚きました。なんとこのひと、アパッチ族やユト族といったネイティヴアメリカンの血をひく、プロのコンテンポラリーダンサーだったのです。下記サイトの二人目に特集されているので興味のある方はどうぞ。
Native Peoples Magazine:
http://www.nativepeoples.com/article/articles/149/
さらに驚いたことに、わたしは前にも彼の演技を観ていたのです。このブログでも以前にとり上げたテレンス・マリックの“ニュー・ワールド”[2005]に出ていました。(というか当該記事[本ブログ2月24日記事]の画像の人物がそうです。‘DVDのながら観’だったからか意識化するに至らなかったものの、画像に使用したくらいなのでどこか引っかかっていたのかも)
プロの踊り手がアクション系の時代物で敵のボス役を演じている近例としては、日本では“たそがれ清兵衛”[2002]がすぐに思い浮かぶところです。現代舞踏家の田中泯はこの作品で妖艶なまでの剣技(というか足技)を披露してみせましたが、これは彼と戦う主人公を演じた真田広之が身体的な素養としても世界水準に達している役者であればこそでした。そうした意味で本作でのラオール・トゥルヒロの身体のキレを引き立てているのはジャングルの大自然と言えそうです。密林の土を足指でがっちりと踏みしめ、草葉を巻き上げて疾走していく姿は見応えがありました。
コンテンポラリーダンスというとなにか取っつきにくい印象もありますが、モダンダンスへの反駁というほか特に総括的な定義はないのが現状なので、非欧米圏におけるコンテンポラリーダンスの潮流としては往々にしてローカルな伝統文化に基づく身振りがクローズアップされてきます。この意味でラオール・トゥルヒロと田中泯の商業映画への起用とその成功には同じ論理が通底していそうです。個人的にこれは意外な発見でした。
◆メル・ギブソン監督作
メル・ギブソンの監督作としての前作“パッション (The Passion of The Christ)”[2004]は、血みどろのイエス・キリストを巡る表現が世上を賑わせましたが、本作“アポカリプト”においても残虐的な戦闘シーンはもとより、生贄の儀式や昆虫の首をもいで治療に使うシーンなど、その異色さは健在。この両作品で彼の映画監督としての立ち位置はほぼ固まったように思います。
以前この記事シリーズのコメント欄で少し述べたこともありますが(“ミッション”2006年8月5日記事)、やはりbloody-dirtyな手触りは彼の表現手法の根底に抜きがたく横たわっているようで、単に世間の耳目をひくために付加されたセンセーショナルな演出というよりは、むしろこうした暴力性の充溢こそが作品の本質になっています。
ただしここで注意しなければならないのは、映像表現として立ち現われてくるのはあくまで作り手もしくは受け手の内なる何かに過ぎないという点です。そのためこの場合であれば現代文明における‘暴力’が必ずしも他の文明にとっても‘暴力’たりえないのが当然である一方で、商業映画におけるストーリー進行は観客の共感を導くものであることが宿命づけられているために、他の文明を扱う際にはこの点での齟齬をどう乗り越えるかが大問題となってくるんですね。たとえば“パール・ハーバー”[2001]に登場する戯画的な日本人像に比べ、先にも挙げた“硫黄島からの手紙”でクリント・イーストウッドは極限下における人間倫理の普遍を描くことによりこの点をきっちりとクリアしていますが、メル・ギブソンは逆に徹頭徹尾アクション描写にこだわることでこうしたズレを無化する方法を採っています。
したがって“アポカリプト”の文明論的な部分を切り取って正しい正しくないと批評するのはそもそもがお門違いということにたぶんなります。たとえば生贄の儀式のシーンでマヤの司祭が民衆を前に現代の西洋人っぽい名声欲を丸出しにしたり、生贄の青年があたかも夏休みの旅行中に誘拐されて殺される前のバックパッカーのような反応を見せたりすることにはおかしさを感じざるをえないのですが、そこは監督本人もとうに開き直っているはずです。そもそもこの作品に比較文明論的な視座を見いだせるとしても、それは実際問題としてどうでもいいことなんですよね。最後のほうではスペインのガレオン艦隊が上陸を開始するシーンもありますが、やはり説明的な挿話以上のものにはなってなかったり。
メル・ギブソンは私生活では熱狂的なクリスチャンとして知られる一方で、“アポカリプト”公開前にはユダヤ人差別発言で物議を醸したりも。映画産業にユダヤ系資本が深く噛み込んでいる現状でこのパフォーマンスは致命的とも思えましたが、公開してみると真逆の大入り状態に。また俳優としての昨今のメル・ギブソンを観てみたいひとにはヴィム・ヴェンダース監督の“ミリオンダラー・ホテル”[2000]が一押し。すっごい変です。でも彼以外は考えられないほどのハマリ役。
“アポカリプト”の音楽を担当しているのはジェームス・ホーナー。“ニュー・ワールド”と同じです。ここらへんの調子の良さもメル・ギブソンならではかも。ここではいろいろと突っ込んだことを書いてますが、作品自体は頭をカラっぽにして楽しめる上質のチェイス物アクション映画になっています。おススメです。
"Apocalypto" by Mel Gibson [+scr] / Rudy Youngblood,Dalia Hernandez,Raoul Trujillo / James Horner [music] / 138min / US / 2006
※ 国内では先月半ば公開の新作ですが、早くも終了しだしています。これから観に行くかたはお急ぎを。レンタル開始はたぶん11月くらい。
1748年、2人組の盗賊がその噂でロンドン中を賑わせます。“紳士怪盗”("the Gentleman Highwayman")とあだ名された彼らの特徴は‘貴族からしか盗まない’こと、そしてあくまで‘紳士的に盗む’こと。史実上のこの事件を元に、映画はこの種の作品としては珍しいほどのパンキッシュな演出とともに展開されます。
2人組の片割れ、ロバート・カーライル演じる元薬剤師のプランケットは商売に失敗しすべてを失ったのち盗賊稼業に手を染めます。ジョニー・リー・ミラー演じるマクレーンは聖職者の家に生まれて身を持ち崩し、社交界への復帰を夢みつつも酒に溺れているころ相棒プランケットに出会います。墓場で出会った2人は獄中で‘紳士協定’を結び一気にその名を馳せてゆくのですが、こうしたストーリーがとてもスピーディに展開されるため、終始MTVを見ているかのような感覚に襲われるひともいるかもしれません。
なかでも圧巻なのは前半の山場、リヴ・タイラー扮するヒロインとマクレーンが初めて出会う晩餐会の場面。着飾った貴族たちによる群舞の旋律に合わせ複数の登場人物たちにより重層的に会話が進行していくのですが、そのいずれもがストーリー進行を決定づける役割を果たしており、権謀術数の渦巻くヨーロッパ社交界のいわば沸騰点のような存在としての晩餐会がもつ高揚感をうまく描出しているように思います。
時間にして約5分の短いこのシークエンスでは、まず通底音として弦楽音を基調とするビートの利いたBGMが流れ出し、異様な静止ポーズを交えた群舞を織りなす無数の男女と宮殿の大広間中央に配置された奇怪な巨大オブジェが遠景に映し出され、何かと主人公たちを助けるバイセクシュアルの貴族ローチェスター卿の案内で主要な貴族たちが次々に紹介されていきます。群舞の進行に併せてBGMも段々と盛り上がっていくのだけれど、この展開が極めて鮮やか、局所的に配される静止も巧みで引きと寄せの緩急があらゆる面で利いており、作品のエッセンスがすべてここに集約、昇華されていると言って良い名シーンになっています。
実を言うと、現在公開中の古代スパルタ軍とレオニダス王を素材とした映画“300<スリーハンドレッド>”を観たことが、この作品を思い出した直接のきっかけだったりします。これら両作品に共通するのは、ある部分では時代背景にかなり忠実な一面をみせつつも、別の部分では過剰とも言えるほどに文化考証を無視した演出が施されていることです。この点を認めるか認めないかでこの種の作品を巡る評価は大きく分かれることになりますが、そもそもこうした方向性は失敗の危険が高いことから実現化へ至るケース自体が稀なんですね。ただ一方でその時代の音楽、その時代の事物に忠実であればその時代精神の的確な表現になるかと言えば、これはこれでまったく別の話であることも確かです。
では“プランケット&マクレーン”においてこの試みは成功しているのかどうか。わたしの答えは大いにYesです。その根拠としては上記の1シーンだけを挙げれば十分な気もします。レンタル版DVDでは37:14-42:32‘夜会’の章がこれに当たります。このシーンで使われたBGMなんてクラシックどころかハイパーテクノなんですけどね(笑)、この作品ののちハリウッドの他作品でもよく使われる定番の1つになりました。
ちなみにこのマクレーン、史実では1750年に処刑台にて最期を迎えるのですがその後ジョン・ゲイの戯曲『乞食オペラ』のモデルとなり、ブレヒトはこの戯曲を元に『三文オペラ』を書きあげたといいますから、当時の人々のあいだでその悪名とは裏腹にかなりの人気を誇っていたことが窺えます。また2人は作品中で追っ手から逃れてあらゆる束縛から自由な土地‘アメリカ’を目指すのですが、対照的なのがローチェスター卿のさいごのセリフ。
「新しい世界は遠すぎるし、広すぎるし、野蛮だわ。
これからもわたしはここで若い男の子たちを堕落させていきたいの」 (筆者訳)
彼は登場するのっけから両刀使いであることを軽々と告白するのですが、その時のセリフ‘I swing everywhere.’とラストでのこのセリフが見せるコントラストは、大航海時代から近代へと移りつつある当時の人々が感じただろう世界の広がりと階層社会の窮屈さをうまく捉えているように思います。
監督はジェイク・スコット。“ブレードランナー”“ブラックホーク・ダウン”などのリドリー・スコットを父に、“トップガン ”“デイズ・オブ・サンダー ”のトニー・スコットを叔父にもつサラブレットの映画監督デビュー作がこの作品でしたから大いに期待されるところですが、その後はいまだ鳴かず飛ばず。ロバート・カーライルは“トレインスポッティング”の大ヒットをきっかけにハリウッドへ進出しますが、元々イギリス下層社会の男を演じ続けて評価を固めた役者なので、この作品をその延長線上に位置づけてもよさそうです。また名優ゲイリー・オールドマンが製作・総指揮で参加しています。
映画“300”を記事にすることも考えたのですが、そこはこのブログにふさわしいほうを選んでみました。“300”の評価関連については相互リンクのある秋林さんのブログに詳しいので、下記に記事URLを紹介させていただきます。
http://diarynote.jp/d/25683/20070316.html
"Plunkett & Macleane" by Jake Scott / Robert Carlyle,Jonny Lee Miller,Liv Tyler,Alan Cumming,Michael Gambon / Gary Oldman [executive prd.] / Craig Armstrong [music] / 100min / UK / 1999
2人組の片割れ、ロバート・カーライル演じる元薬剤師のプランケットは商売に失敗しすべてを失ったのち盗賊稼業に手を染めます。ジョニー・リー・ミラー演じるマクレーンは聖職者の家に生まれて身を持ち崩し、社交界への復帰を夢みつつも酒に溺れているころ相棒プランケットに出会います。墓場で出会った2人は獄中で‘紳士協定’を結び一気にその名を馳せてゆくのですが、こうしたストーリーがとてもスピーディに展開されるため、終始MTVを見ているかのような感覚に襲われるひともいるかもしれません。
なかでも圧巻なのは前半の山場、リヴ・タイラー扮するヒロインとマクレーンが初めて出会う晩餐会の場面。着飾った貴族たちによる群舞の旋律に合わせ複数の登場人物たちにより重層的に会話が進行していくのですが、そのいずれもがストーリー進行を決定づける役割を果たしており、権謀術数の渦巻くヨーロッパ社交界のいわば沸騰点のような存在としての晩餐会がもつ高揚感をうまく描出しているように思います。
時間にして約5分の短いこのシークエンスでは、まず通底音として弦楽音を基調とするビートの利いたBGMが流れ出し、異様な静止ポーズを交えた群舞を織りなす無数の男女と宮殿の大広間中央に配置された奇怪な巨大オブジェが遠景に映し出され、何かと主人公たちを助けるバイセクシュアルの貴族ローチェスター卿の案内で主要な貴族たちが次々に紹介されていきます。群舞の進行に併せてBGMも段々と盛り上がっていくのだけれど、この展開が極めて鮮やか、局所的に配される静止も巧みで引きと寄せの緩急があらゆる面で利いており、作品のエッセンスがすべてここに集約、昇華されていると言って良い名シーンになっています。
実を言うと、現在公開中の古代スパルタ軍とレオニダス王を素材とした映画“300<スリーハンドレッド>”を観たことが、この作品を思い出した直接のきっかけだったりします。これら両作品に共通するのは、ある部分では時代背景にかなり忠実な一面をみせつつも、別の部分では過剰とも言えるほどに文化考証を無視した演出が施されていることです。この点を認めるか認めないかでこの種の作品を巡る評価は大きく分かれることになりますが、そもそもこうした方向性は失敗の危険が高いことから実現化へ至るケース自体が稀なんですね。ただ一方でその時代の音楽、その時代の事物に忠実であればその時代精神の的確な表現になるかと言えば、これはこれでまったく別の話であることも確かです。
では“プランケット&マクレーン”においてこの試みは成功しているのかどうか。わたしの答えは大いにYesです。その根拠としては上記の1シーンだけを挙げれば十分な気もします。レンタル版DVDでは37:14-42:32‘夜会’の章がこれに当たります。このシーンで使われたBGMなんてクラシックどころかハイパーテクノなんですけどね(笑)、この作品ののちハリウッドの他作品でもよく使われる定番の1つになりました。
ちなみにこのマクレーン、史実では1750年に処刑台にて最期を迎えるのですがその後ジョン・ゲイの戯曲『乞食オペラ』のモデルとなり、ブレヒトはこの戯曲を元に『三文オペラ』を書きあげたといいますから、当時の人々のあいだでその悪名とは裏腹にかなりの人気を誇っていたことが窺えます。また2人は作品中で追っ手から逃れてあらゆる束縛から自由な土地‘アメリカ’を目指すのですが、対照的なのがローチェスター卿のさいごのセリフ。
「新しい世界は遠すぎるし、広すぎるし、野蛮だわ。
これからもわたしはここで若い男の子たちを堕落させていきたいの」 (筆者訳)
彼は登場するのっけから両刀使いであることを軽々と告白するのですが、その時のセリフ‘I swing everywhere.’とラストでのこのセリフが見せるコントラストは、大航海時代から近代へと移りつつある当時の人々が感じただろう世界の広がりと階層社会の窮屈さをうまく捉えているように思います。
監督はジェイク・スコット。“ブレードランナー”“ブラックホーク・ダウン”などのリドリー・スコットを父に、“トップガン ”“デイズ・オブ・サンダー ”のトニー・スコットを叔父にもつサラブレットの映画監督デビュー作がこの作品でしたから大いに期待されるところですが、その後はいまだ鳴かず飛ばず。ロバート・カーライルは“トレインスポッティング”の大ヒットをきっかけにハリウッドへ進出しますが、元々イギリス下層社会の男を演じ続けて評価を固めた役者なので、この作品をその延長線上に位置づけてもよさそうです。また名優ゲイリー・オールドマンが製作・総指揮で参加しています。
映画“300”を記事にすることも考えたのですが、そこはこのブログにふさわしいほうを選んでみました。“300”の評価関連については相互リンクのある秋林さんのブログに詳しいので、下記に記事URLを紹介させていただきます。
http://diarynote.jp/d/25683/20070316.html
"Plunkett & Macleane" by Jake Scott / Robert Carlyle,Jonny Lee Miller,Liv Tyler,Alan Cumming,Michael Gambon / Gary Oldman [executive prd.] / Craig Armstrong [music] / 100min / UK / 1999
『パイレーツ・オブ・カリビアン』、きのうから第3作が日本公開に。すっかり海賊映画の代名詞的存在となりましたね。第1作について書いた過去記事(「Job Description 2:〜」昨年7月23日記事)では作品を巡る製作背景に焦点を当てたので、今回はできるだけ作品内容にシフトしてみます。
とはいえこれから観ようというかたも多いでしょうから、ここではストーリーを追うことはせず、代わりにキーワードを3つ。「世界の果て」と「父と子」、「船」。では参ります。
◆世界の果て
サブタイトルにもある通り、この作品では「ワールドエンド(世界の果て)」が大きな意味をもっています。原題では"At World’s End"と’at’が付いているように、ストーリー進行そのものが「世界の果て」を主舞台として展開するのですね。しばらく前に当ブログで紹介した予告篇動画にも出てくるので記憶にあるかたもいるかもしれませんが、視覚化されたこの「世界の果て」はなかなかに凄かった。とにかく本作は視覚エフェクトの点で目を見張る場面が前作よりも増えていました。
以前にも触れましたが、この第3作は昨年公開された第2作と同時撮影されているんですね。つまりエフェクト等を含む編集作業のみに1年近い時間をかけることが可能だったわけで、この時差を両作品の差異化へとうまく活かした構成になっていることが窺えます。
◆父と子
作品前半では世界各地の大海賊9名による‘評議会’開催までの顛末が描かれるのですが、この会議の場で大海賊の首領たちをも黙らせる‘海賊の掟’の番人として登場する男がいます。3、4ヶ所しか出番がないもののやたらにカッコいい役柄で、ひと目みてスパローの父親だったらいいなと個人的に思いました。
というのも3人の主人公のうち鍛冶見習いだった青年と貴族出身のヒロインの2人については、前2作ですでにそれぞれの父親が登場し重要な役割を果たしていますが、本作においてはさらにそのプレゼンスを増しているんですね。そこでもしかしたらこの作品の裏テーマは‘父と子’かもなという気配を感じていたからなのですが、この掟の番人、その後のシーンでやはりジャック・スパローの父であることが明かされます。
実を言うと“パイレーツ・オブ・カリビアン”の第1作は、興行的成功を収めた一方でディズニー製作の映画としては初めてPG-12指定を受けた作品でもあったので、もしかしたらここには教育的配慮を前面に出す意図が働いたのかもしれません。しかも考えてみるとこの3人の父親、作品の根幹となる本筋のみを採り出すと必ずしも彼らが主人公3人の父親である必要はないんですね。むしろ‘父と子’の裏テーマを付加させるべく彼らの存在がクローズアップされたとみると、複雑なストーリー構成が幾分スッキリしてきます。
‘父と子’を‘継承’の問題と広げて考えると、その船の船長、その盟主、その伝統は誰が継ぐのかといったテーマが本編中でたびたび俎上にあがっているのがわかります。第2作でも登場したフライング・ダッチマン(さまよえる幽霊船)の船長も意外な人物が継ぐことに。乞うご期待。(笑)
◆船
とにかくお金のかかった米メジャー製作による大作映画、見どころの一つに視覚表現の卓越さがあるのは言うまでもないところですが、本作においては大航海時代当時の船舶や建築物の再現にもそれが活かされています。といっても見た目の質感が重要視されるので歴史考証的な厳密さは求められないわけですが、たとえば第2作以降終始不穏な敵役として振る舞うイギリス東インド会社の重役ベケット卿が登場するシーンなど、提督居室のインテリアや手にする小道具がなかなかよく出来ていて見ごたえを感じました。
また彼の乗る四層甲板の超一等戦列艦が、この映画ではすでにお馴染みのブラックパール号(快速フリゲート艦)とフライング・ダッチマンから同時砲撃を受ける場面があるのですが、このシーンなどは敵の意表を突いた戦術にアブキール海戦でナポレオン艦隊を破ったネルソン提督の鬼謀を彷彿とさせるものがあり、ちょっと感動してしまいました。ここでベケット卿が茫然としつつ艦橋を降りる場面など、リア王や『乱』における仲代達矢のごとく‘世界の王の終わり’の元型イメージにけっこう迫っていたと思います。
少し話が逸れますがこのベケット卿、史実上のイギリス海軍省の幹部(ロード・オブ・アドミラルもしくはロード・オブ・ハイ・アドミラル、海軍卿)とイギリス東インド会社の重役が意図的に混同された役柄となっているんですね。もし史実上にそんな人物がいたら、当時の世界で5本指に入るほどの実権の持ち主にたぶんなります。現代で言えば陸海空軍を手にしたビル・ゲイツといったところ。
前作の終わりでイカの怪物クラーケンによってスパローともども海中に引きずり込まれたブラックパール号、その直前のシーンでクラーケンによって別の船が両断されたため記憶が混ざりがちなのですが、破壊はされずに丸ごと海に呑み込まれていることが本作への布石になっています。本作ではとんでもない場所を信じがたい航法で進みます。これは予想しようもないシーンでした、とだけここでは書いておきます。(笑)
第2作で海中から現れるという凄まじい登場の仕方をしたさまよえる幽霊船フライング・ダッチマンについても触れておくと、この船が召喚できたクラーケンは前作でお役御免となりつつも、船首に配されたギャトリングガンをそのまま大型化したような三連装砲や、木造船なのに空恐ろしい速度で沈んでいく潜航能力など、本作でも存分に見る目を楽しませてくれています。また今回はこの船が海中から現れる仕掛けについても、ジャック・スパローの天才的というか彼らしいとぼけた思いつきからその秘密が明かされます。
◆配役その他
第3作は一応完結編ということもあり、他にもいろいろな謎が順次明らかにされます。その過程で初めてデイヴィ・ジョーンズ(軟体動物の化け物、フライング・ダッチマンの船長)をビル・ナイが演じていることに気づきかなり驚きました。CG処理で顔を覆われてほとんど目と仕草だけの演技なのですが、なるほどこういう役柄ほど実のある役者でなければ務まらないのは確かだなぁと感心も。それに比べるとチョウ・ユンファ演じる華僑の海賊を始めとする‘9人の大海賊’については、もう少し個々につくり込みが欲しかったかなとも。ジョニー・デップはつくづく立ち位置の不思議な役者だなぁと思うのですが、彼の見せ場は前作のほうが多かったかもしれません。
エンドロールは最後まで見ることをお薦めします。早々に席を立つひとも多そうですが、第2作にもあったようにおまけシーンが付いてます。構成的にはプロローグに登場する処刑台を前にした少年とかすかに呼応しており、わたしなどはここでこの映画に施されたもう一つのテーマについて‘やっぱりそうなんだ’と再確認したわけですが、その理由も観に行ったかたにはお分かりになるはず。ぜひ。(笑)
"Pirates of the Caribbean: At World’s End" by Gore Verbinski / Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Geoffrey Rush, Bill Nighy, Yun-Fat Chow/ Jerry Bruckheimer [prd.] / Hans Zimmer [music] / 170min / US / 2007
とはいえこれから観ようというかたも多いでしょうから、ここではストーリーを追うことはせず、代わりにキーワードを3つ。「世界の果て」と「父と子」、「船」。では参ります。
◆世界の果て
サブタイトルにもある通り、この作品では「ワールドエンド(世界の果て)」が大きな意味をもっています。原題では"At World’s End"と’at’が付いているように、ストーリー進行そのものが「世界の果て」を主舞台として展開するのですね。しばらく前に当ブログで紹介した予告篇動画にも出てくるので記憶にあるかたもいるかもしれませんが、視覚化されたこの「世界の果て」はなかなかに凄かった。とにかく本作は視覚エフェクトの点で目を見張る場面が前作よりも増えていました。
以前にも触れましたが、この第3作は昨年公開された第2作と同時撮影されているんですね。つまりエフェクト等を含む編集作業のみに1年近い時間をかけることが可能だったわけで、この時差を両作品の差異化へとうまく活かした構成になっていることが窺えます。
◆父と子
作品前半では世界各地の大海賊9名による‘評議会’開催までの顛末が描かれるのですが、この会議の場で大海賊の首領たちをも黙らせる‘海賊の掟’の番人として登場する男がいます。3、4ヶ所しか出番がないもののやたらにカッコいい役柄で、ひと目みてスパローの父親だったらいいなと個人的に思いました。
というのも3人の主人公のうち鍛冶見習いだった青年と貴族出身のヒロインの2人については、前2作ですでにそれぞれの父親が登場し重要な役割を果たしていますが、本作においてはさらにそのプレゼンスを増しているんですね。そこでもしかしたらこの作品の裏テーマは‘父と子’かもなという気配を感じていたからなのですが、この掟の番人、その後のシーンでやはりジャック・スパローの父であることが明かされます。
実を言うと“パイレーツ・オブ・カリビアン”の第1作は、興行的成功を収めた一方でディズニー製作の映画としては初めてPG-12指定を受けた作品でもあったので、もしかしたらここには教育的配慮を前面に出す意図が働いたのかもしれません。しかも考えてみるとこの3人の父親、作品の根幹となる本筋のみを採り出すと必ずしも彼らが主人公3人の父親である必要はないんですね。むしろ‘父と子’の裏テーマを付加させるべく彼らの存在がクローズアップされたとみると、複雑なストーリー構成が幾分スッキリしてきます。
‘父と子’を‘継承’の問題と広げて考えると、その船の船長、その盟主、その伝統は誰が継ぐのかといったテーマが本編中でたびたび俎上にあがっているのがわかります。第2作でも登場したフライング・ダッチマン(さまよえる幽霊船)の船長も意外な人物が継ぐことに。乞うご期待。(笑)
◆船
とにかくお金のかかった米メジャー製作による大作映画、見どころの一つに視覚表現の卓越さがあるのは言うまでもないところですが、本作においては大航海時代当時の船舶や建築物の再現にもそれが活かされています。といっても見た目の質感が重要視されるので歴史考証的な厳密さは求められないわけですが、たとえば第2作以降終始不穏な敵役として振る舞うイギリス東インド会社の重役ベケット卿が登場するシーンなど、提督居室のインテリアや手にする小道具がなかなかよく出来ていて見ごたえを感じました。
また彼の乗る四層甲板の超一等戦列艦が、この映画ではすでにお馴染みのブラックパール号(快速フリゲート艦)とフライング・ダッチマンから同時砲撃を受ける場面があるのですが、このシーンなどは敵の意表を突いた戦術にアブキール海戦でナポレオン艦隊を破ったネルソン提督の鬼謀を彷彿とさせるものがあり、ちょっと感動してしまいました。ここでベケット卿が茫然としつつ艦橋を降りる場面など、リア王や『乱』における仲代達矢のごとく‘世界の王の終わり’の元型イメージにけっこう迫っていたと思います。
少し話が逸れますがこのベケット卿、史実上のイギリス海軍省の幹部(ロード・オブ・アドミラルもしくはロード・オブ・ハイ・アドミラル、海軍卿)とイギリス東インド会社の重役が意図的に混同された役柄となっているんですね。もし史実上にそんな人物がいたら、当時の世界で5本指に入るほどの実権の持ち主にたぶんなります。現代で言えば陸海空軍を手にしたビル・ゲイツといったところ。
前作の終わりでイカの怪物クラーケンによってスパローともども海中に引きずり込まれたブラックパール号、その直前のシーンでクラーケンによって別の船が両断されたため記憶が混ざりがちなのですが、破壊はされずに丸ごと海に呑み込まれていることが本作への布石になっています。本作ではとんでもない場所を信じがたい航法で進みます。これは予想しようもないシーンでした、とだけここでは書いておきます。(笑)
第2作で海中から現れるという凄まじい登場の仕方をしたさまよえる幽霊船フライング・ダッチマンについても触れておくと、この船が召喚できたクラーケンは前作でお役御免となりつつも、船首に配されたギャトリングガンをそのまま大型化したような三連装砲や、木造船なのに空恐ろしい速度で沈んでいく潜航能力など、本作でも存分に見る目を楽しませてくれています。また今回はこの船が海中から現れる仕掛けについても、ジャック・スパローの天才的というか彼らしいとぼけた思いつきからその秘密が明かされます。
◆配役その他
第3作は一応完結編ということもあり、他にもいろいろな謎が順次明らかにされます。その過程で初めてデイヴィ・ジョーンズ(軟体動物の化け物、フライング・ダッチマンの船長)をビル・ナイが演じていることに気づきかなり驚きました。CG処理で顔を覆われてほとんど目と仕草だけの演技なのですが、なるほどこういう役柄ほど実のある役者でなければ務まらないのは確かだなぁと感心も。それに比べるとチョウ・ユンファ演じる華僑の海賊を始めとする‘9人の大海賊’については、もう少し個々につくり込みが欲しかったかなとも。ジョニー・デップはつくづく立ち位置の不思議な役者だなぁと思うのですが、彼の見せ場は前作のほうが多かったかもしれません。
エンドロールは最後まで見ることをお薦めします。早々に席を立つひとも多そうですが、第2作にもあったようにおまけシーンが付いてます。構成的にはプロローグに登場する処刑台を前にした少年とかすかに呼応しており、わたしなどはここでこの映画に施されたもう一つのテーマについて‘やっぱりそうなんだ’と再確認したわけですが、その理由も観に行ったかたにはお分かりになるはず。ぜひ。(笑)
"Pirates of the Caribbean: At World’s End" by Gore Verbinski / Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Geoffrey Rush, Bill Nighy, Yun-Fat Chow/ Jerry Bruckheimer [prd.] / Hans Zimmer [music] / 170min / US / 2007
Job Description 6: 探検家 【ニュー・ワールド】
2007年2月24日 就職・転職 コメント (6)
1607年4月、イギリス最初の植民者たちを載せたスーザン・コンスタント号など3隻の船が、大西洋を渡り北米の現ヴァージニア州ヘンリー岬へとたどり着きます。彼らはその後入植に適した土地を求めてジェームス川をさかのぼるのですが、この映画はこれら3隻の帆船による遡行のシーンから始まります。
静けさのなか次第に曲勢の高まる音楽とともに、半年の航海を終えて入植準備を開始する一行の緊張と、白人たちの到来を迎えたネイティヴアメリカンの一族の警戒心とが一体的に映し出され、繊細な自然描写も交えつつ場面は一気に両者の遭遇へとつながっていきます。映像表現としてこの流れが非常に秀逸で、レンタルDVDを片手間に見始めたのですが映画館へ行かなかったことを即座に後悔しました。しかもたびたび挿入される昆虫や草花の近接ショットに、ああまた“シン・レッド・ライン”のパクりかぁと思って監督名を確認したら、なんとテレンス・マリックその人。後悔はさらに深くなりました。
なぜこれまでこの作品がノーマークだったかを考えるに、どうも主演のコリン・ファレル(“タイガーランド”,“マイアミバイス”等)ばかりへ光を当てた宣伝に騙されたのかもしれません。彼は出てきた当初こそ注目したものの、演技力よりスター性を前面に出すトム・クルーズやブラット・ピットのような近年の舵取りに少しがっかりしていたんですね。(彼らが嫌いという話ではなく、DVDで観ることが多いという話。) それに加えてテレンス・マリック、まさかこんなにすぐ次作の公開があるとは想像もしなかった。
この監督が“シン・レッド・ライン”で20年の沈黙を破ったことは映画好きの人間であればいまだ記憶に新しいところでしょう。しかし彼が“シン・レッド・ライン”で果たした功績、他の表現者に与えた影響の深さについてはなお図りがたいものを感じます。近接の映画・TV界のみならず、卑近なところではたとえば井上雄彦『バガボンド』やかわぐちかいじ『ジパング』などにも明らかにこの映画からの援用と思われるカットが諸処に登場したり。
ともあれ話を本作品に戻すと、作中の主人公は3人。いずれも史実上の人物で、実際にジェームスタウン植民者とパウハタン族との和解を仲介したジョン・スミス、その後同植民州においてタバコ栽培の産業化を主導したジョン・ロルフ、そしてかの有名なポカホンタス。この名を出した途端ディズニーのようなイメージを持たれかねないためここまで控えておきましたが、実際には彼女の目を通した光景が劇中で核となるシーンのほとんどを占めています。
パウハタン族の生活、身振り、衣装などはとてもよく作り込まれており見る目を存分に楽しませてくれますが、と同時に90年代までこの種の題材を扱う映画がことごとく侵されていた妙なエキゾチシズムに対しても慎重に配慮されており、ポカホンタスがプロテスタントの洗礼を受け欧州へと渡った後半生を描いたシーンにおいてすらこの配慮はまったく欠けるところがありません。ジョン・スミスを想いながらもジョン・ロルフの誠実さに次第に心を溶かしていく彼女は映画の終盤でスミスとの再会を果たすのですが、ここにおいても彼女がしっかりと屹立した個性をもって表出され得ていることはこの種の慎重さが成功を収めていることの何よりの証とも言えそうです。
クリストファー・プラマー、ノア・テイラーといった脇を固める役者陣も素晴らしく、ジェームス・ホーナーの音楽の良さは冒頭に述べた通りです。いまこの文章を打ちつつ傍らでDVDを観なおしてもいるのですが、この映像の構成力はさすがだと思わせる箇所がそこかしこに散見されます。こうした作り込みかたは、毎年のように作品を量産している売れっ子監督にはまず見られません。一見の価値ありです。
公式HP: http://www.thenewworldmovie.com/
◇関連の予告など
思うに大航海時代ほど現代映画の素材に適した舞台も珍しいかもしれません。この時代の思考生活様式のヴィジュアライズは、そのまま‘異世界’との感覚的な邂逅へと展開しうるからです。というわけで、下記作品の日本での公開があり次第、たぶんまた書きます。
"Apocalypto": マヤ文明末期の部族抗争が舞台。過去記事のコメント欄で一度話題になったメル・ギブソン監督がまたやってくれたらしく。駄作でも映画館で観る価値がありそう。[2006年公開@米] http://apocalypto.movies.go.com/
"Pirates of the Caribbean: At World’s End": DOLプレイヤーにはおなじみのパイレーツ・オブ・カリビアン第3作。前作とは同時撮影されたため、こちらを観ないことには第2作についても書く気になれず。スタッフ&キャスト陣もほぼ同じ。[2007年公開@米]
"The Fountain": 作品舞台となる3時代のうち1つが大航海時代。女王の命を受けマヤの密林へ分け入る冒険者が主人公。“π(パイ)”,“レクイエム・フォー・ドリーム”のダーレン・アロノフスキー監督作で、目下売れ線のレイチェル・ワイズ(“ナイロビの蜂”,“コンスタンティン”等)主演。[2006年公開@伊] http://thefountainmovie.warnerbros.com/
"The New World" by Terrence Malick [+scr] / Colin Farrell, Q’orianka Kilcher, Christopher Plummer, Christian Bale, Noah Taylor / James Horner [Music Score] / 149min / US / 2005
静けさのなか次第に曲勢の高まる音楽とともに、半年の航海を終えて入植準備を開始する一行の緊張と、白人たちの到来を迎えたネイティヴアメリカンの一族の警戒心とが一体的に映し出され、繊細な自然描写も交えつつ場面は一気に両者の遭遇へとつながっていきます。映像表現としてこの流れが非常に秀逸で、レンタルDVDを片手間に見始めたのですが映画館へ行かなかったことを即座に後悔しました。しかもたびたび挿入される昆虫や草花の近接ショットに、ああまた“シン・レッド・ライン”のパクりかぁと思って監督名を確認したら、なんとテレンス・マリックその人。後悔はさらに深くなりました。
なぜこれまでこの作品がノーマークだったかを考えるに、どうも主演のコリン・ファレル(“タイガーランド”,“マイアミバイス”等)ばかりへ光を当てた宣伝に騙されたのかもしれません。彼は出てきた当初こそ注目したものの、演技力よりスター性を前面に出すトム・クルーズやブラット・ピットのような近年の舵取りに少しがっかりしていたんですね。(彼らが嫌いという話ではなく、DVDで観ることが多いという話。) それに加えてテレンス・マリック、まさかこんなにすぐ次作の公開があるとは想像もしなかった。
この監督が“シン・レッド・ライン”で20年の沈黙を破ったことは映画好きの人間であればいまだ記憶に新しいところでしょう。しかし彼が“シン・レッド・ライン”で果たした功績、他の表現者に与えた影響の深さについてはなお図りがたいものを感じます。近接の映画・TV界のみならず、卑近なところではたとえば井上雄彦『バガボンド』やかわぐちかいじ『ジパング』などにも明らかにこの映画からの援用と思われるカットが諸処に登場したり。
ともあれ話を本作品に戻すと、作中の主人公は3人。いずれも史実上の人物で、実際にジェームスタウン植民者とパウハタン族との和解を仲介したジョン・スミス、その後同植民州においてタバコ栽培の産業化を主導したジョン・ロルフ、そしてかの有名なポカホンタス。この名を出した途端ディズニーのようなイメージを持たれかねないためここまで控えておきましたが、実際には彼女の目を通した光景が劇中で核となるシーンのほとんどを占めています。
パウハタン族の生活、身振り、衣装などはとてもよく作り込まれており見る目を存分に楽しませてくれますが、と同時に90年代までこの種の題材を扱う映画がことごとく侵されていた妙なエキゾチシズムに対しても慎重に配慮されており、ポカホンタスがプロテスタントの洗礼を受け欧州へと渡った後半生を描いたシーンにおいてすらこの配慮はまったく欠けるところがありません。ジョン・スミスを想いながらもジョン・ロルフの誠実さに次第に心を溶かしていく彼女は映画の終盤でスミスとの再会を果たすのですが、ここにおいても彼女がしっかりと屹立した個性をもって表出され得ていることはこの種の慎重さが成功を収めていることの何よりの証とも言えそうです。
クリストファー・プラマー、ノア・テイラーといった脇を固める役者陣も素晴らしく、ジェームス・ホーナーの音楽の良さは冒頭に述べた通りです。いまこの文章を打ちつつ傍らでDVDを観なおしてもいるのですが、この映像の構成力はさすがだと思わせる箇所がそこかしこに散見されます。こうした作り込みかたは、毎年のように作品を量産している売れっ子監督にはまず見られません。一見の価値ありです。
公式HP: http://www.thenewworldmovie.com/
◇関連の予告など
思うに大航海時代ほど現代映画の素材に適した舞台も珍しいかもしれません。この時代の思考生活様式のヴィジュアライズは、そのまま‘異世界’との感覚的な邂逅へと展開しうるからです。というわけで、下記作品の日本での公開があり次第、たぶんまた書きます。
"Apocalypto": マヤ文明末期の部族抗争が舞台。過去記事のコメント欄で一度話題になったメル・ギブソン監督がまたやってくれたらしく。駄作でも映画館で観る価値がありそう。[2006年公開@米] http://apocalypto.movies.go.com/
"Pirates of the Caribbean: At World’s End": DOLプレイヤーにはおなじみのパイレーツ・オブ・カリビアン第3作。前作とは同時撮影されたため、こちらを観ないことには第2作についても書く気になれず。スタッフ&キャスト陣もほぼ同じ。[2007年公開@米]
"The Fountain": 作品舞台となる3時代のうち1つが大航海時代。女王の命を受けマヤの密林へ分け入る冒険者が主人公。“π(パイ)”,“レクイエム・フォー・ドリーム”のダーレン・アロノフスキー監督作で、目下売れ線のレイチェル・ワイズ(“ナイロビの蜂”,“コンスタンティン”等)主演。[2006年公開@伊] http://thefountainmovie.warnerbros.com/
"The New World" by Terrence Malick [+scr] / Colin Farrell, Q’orianka Kilcher, Christopher Plummer, Christian Bale, Noah Taylor / James Horner [Music Score] / 149min / US / 2005
Job Description 5: 准士官 【バリー・リンドン】
2006年9月16日 就職・転職
18世紀半ばアイルランドに生まれた青年が波瀾万丈、イングランドをへて中欧諸国を遍歴し貴族の生活を手に入れる軌跡を描いたこの作品、監督は言わずと知れた20世紀最後の巨匠、スタンリー・キューブリックです。今回は監督にフォーカスを。
ダブリン遠郊の農家に生まれた主人公は、恋敵との決闘をへて故郷を出奔、英仏戦争への従軍、脱走、プロイセン軍での身分詐称、賭博師の仮面をかぶった二重スパイと紆余曲折をへたのちイギリス貴族の暮らしにたどり着くのですが、全3時間の映画はここでようやくその前半を終わります。ビルドゥングスロマンとしてはありがちと言えなくもないこの展開も、後半へ入ると徐々に大きな逸脱を見せ始めるのですが、そこは見てのお楽しみということに。
この冒険心に溢れた前半の大活劇から後半での堕落の旅路へと至る境目では、妖艶な夜の貴族生活を描いたシークエンスがたびたび挿入されています。(画像) ここで登場するローソクの炎による演出は、人のもつ欲望と虚飾、野心と官能のゆらめきが映像空間すべてを充たすようで見応え十分なのですが、ローソクの灯りだけで画を撮るここでの技法は、当時における最前衛の試みとしていまだに語り草となっているものです。(不気味さだけをとればこの炎は“フルメタル・ジャケット”[1987]のラストへも通じるものあり)
ただこの伝説が一人歩きしたあげく、CG効果に慣れた目で「大したことないじゃん」と断じる向きもあるので補足すればこれはもう、当時における制約の限界に挑んだ結果生じた味わいが現代の目から見ても凄いんです、と言うしかありません。そこは今の技術では、どうしても成し遂げようのないものなんですね。
キューブリックの映画といえば、そのリジッドな構築性がもたらす乾いた手触りが何よりの特色なわけですが、それはこの作品でも如何なく発揮されています。この見た目の感触からか、彼の手法についてはよく完璧主義という言葉により、あらかじめ用意された彼個人の構想に役者もスタッフも徹底して従わせるかのような文脈で語られるのですが、実のところこうした解釈にはかなりの偏見が含まれているなぁというのが私的な実感だったりします。
というのも、“2001年宇宙の旅”[1968]にしても“時計じかけのオレンジ”[1971]にしてもそうですが、 彼の監督作に共通して感じるのは‘個人がどうあがこうと逃れられない何者か’の強烈な存在で、それは全編全シーンを通してキューブリック作品の表現世界の底でつねに息づいているように思えるからです。このほとんど‘普遍’とでも言うべき何者か(人によっては神とか天とか言いそうな)の表出を映画という総合芸術において達成するのに、たった一人の内面のみがいったいどれほどの意味をもつのか、そこがまず疑問なんですね。
などと思っていたところ、さいきん“シャイニング”[1980]の復元版DVDに収録されていた、当時17歳の娘さんヴィヴィアン・キューブリックが撮ったメイキングフィルムを観て、この謎はほぼ氷解することに。そこに映し出されている彼の製作手法は、ジャック・ニコルソンら俳優・スタッフとときに喧嘩のような議論を交わし、状況の変化に適時柔軟な対応を見せていく徹底した現場主義そのものでした。
コッポラ夫人が撮った“地獄の黙示録”[1979]のメイキングフィルムなどもそうですが、監督本人の肉親が撮っている作品は、その立ち位置を活かしてかなり遠慮のないところまでカメラが迫るものが多いようです。(マイナーどころでもマフマルバフ一家とか、わりとよくあるパターンかも) それがウン十年前の一編ともなれば、現代史ドキュメンタリー的な面白さも備わります。世がVHSテープ主流の頃に一度流通したものは、こういうDVD特典が見逃せないポイントだなぁともあらためて思った次第。(笑)
話を戻して“バリー・リンドン”、原作者のウィリアム・メイクピース・サッカレーは19世紀半ばの人。イギリス東インド会社所属の父をもち、英領カルカッタで生まれた大航海時代の申し子のような作家です。
また、男爵や子爵、銃士や賭博師などのほうがストーリーの比重的にはふさわしいにも関わらず記事タイトルへ「准士官」をもってきたのは、作品後半で病に臥す一人息子に乞われて主人公が語るのが、兵曹時代のウソの武勇譚だったから。数人の部下を従えてフランス軍の砦に一番槍で乗り込むおはなしなのだけど、これだけ海千山千の道行きを歩んでおきながら、この世で最も大切なわが子の最期に本当は体験もしていない話を誇るしかない主人公のズームアップは、もしかしたらこの作品中で一番哀愁を誘う場面かもしれません。
"Barry Lyndon" by Stanley Kubrick [+scr] / Ryan O’Neal, Marisa Berenson, Patrick Magee, Leon Vitali / John Alcott [cinematographer] / William Makepeace Thackeray [book author] / 184min / UK / 1975
ダブリン遠郊の農家に生まれた主人公は、恋敵との決闘をへて故郷を出奔、英仏戦争への従軍、脱走、プロイセン軍での身分詐称、賭博師の仮面をかぶった二重スパイと紆余曲折をへたのちイギリス貴族の暮らしにたどり着くのですが、全3時間の映画はここでようやくその前半を終わります。ビルドゥングスロマンとしてはありがちと言えなくもないこの展開も、後半へ入ると徐々に大きな逸脱を見せ始めるのですが、そこは見てのお楽しみということに。
この冒険心に溢れた前半の大活劇から後半での堕落の旅路へと至る境目では、妖艶な夜の貴族生活を描いたシークエンスがたびたび挿入されています。(画像) ここで登場するローソクの炎による演出は、人のもつ欲望と虚飾、野心と官能のゆらめきが映像空間すべてを充たすようで見応え十分なのですが、ローソクの灯りだけで画を撮るここでの技法は、当時における最前衛の試みとしていまだに語り草となっているものです。(不気味さだけをとればこの炎は“フルメタル・ジャケット”[1987]のラストへも通じるものあり)
ただこの伝説が一人歩きしたあげく、CG効果に慣れた目で「大したことないじゃん」と断じる向きもあるので補足すればこれはもう、当時における制約の限界に挑んだ結果生じた味わいが現代の目から見ても凄いんです、と言うしかありません。そこは今の技術では、どうしても成し遂げようのないものなんですね。
キューブリックの映画といえば、そのリジッドな構築性がもたらす乾いた手触りが何よりの特色なわけですが、それはこの作品でも如何なく発揮されています。この見た目の感触からか、彼の手法についてはよく完璧主義という言葉により、あらかじめ用意された彼個人の構想に役者もスタッフも徹底して従わせるかのような文脈で語られるのですが、実のところこうした解釈にはかなりの偏見が含まれているなぁというのが私的な実感だったりします。
というのも、“2001年宇宙の旅”[1968]にしても“時計じかけのオレンジ”[1971]にしてもそうですが、 彼の監督作に共通して感じるのは‘個人がどうあがこうと逃れられない何者か’の強烈な存在で、それは全編全シーンを通してキューブリック作品の表現世界の底でつねに息づいているように思えるからです。このほとんど‘普遍’とでも言うべき何者か(人によっては神とか天とか言いそうな)の表出を映画という総合芸術において達成するのに、たった一人の内面のみがいったいどれほどの意味をもつのか、そこがまず疑問なんですね。
などと思っていたところ、さいきん“シャイニング”[1980]の復元版DVDに収録されていた、当時17歳の娘さんヴィヴィアン・キューブリックが撮ったメイキングフィルムを観て、この謎はほぼ氷解することに。そこに映し出されている彼の製作手法は、ジャック・ニコルソンら俳優・スタッフとときに喧嘩のような議論を交わし、状況の変化に適時柔軟な対応を見せていく徹底した現場主義そのものでした。
コッポラ夫人が撮った“地獄の黙示録”[1979]のメイキングフィルムなどもそうですが、監督本人の肉親が撮っている作品は、その立ち位置を活かしてかなり遠慮のないところまでカメラが迫るものが多いようです。(マイナーどころでもマフマルバフ一家とか、わりとよくあるパターンかも) それがウン十年前の一編ともなれば、現代史ドキュメンタリー的な面白さも備わります。世がVHSテープ主流の頃に一度流通したものは、こういうDVD特典が見逃せないポイントだなぁともあらためて思った次第。(笑)
話を戻して“バリー・リンドン”、原作者のウィリアム・メイクピース・サッカレーは19世紀半ばの人。イギリス東インド会社所属の父をもち、英領カルカッタで生まれた大航海時代の申し子のような作家です。
また、男爵や子爵、銃士や賭博師などのほうがストーリーの比重的にはふさわしいにも関わらず記事タイトルへ「准士官」をもってきたのは、作品後半で病に臥す一人息子に乞われて主人公が語るのが、兵曹時代のウソの武勇譚だったから。数人の部下を従えてフランス軍の砦に一番槍で乗り込むおはなしなのだけど、これだけ海千山千の道行きを歩んでおきながら、この世で最も大切なわが子の最期に本当は体験もしていない話を誇るしかない主人公のズームアップは、もしかしたらこの作品中で一番哀愁を誘う場面かもしれません。
"Barry Lyndon" by Stanley Kubrick [+scr] / Ryan O’Neal, Marisa Berenson, Patrick Magee, Leon Vitali / John Alcott [cinematographer] / William Makepeace Thackeray [book author] / 184min / UK / 1975
Job Description 4: 両替商 【ヴェニスの商人】
2006年8月31日 就職・転職 コメント (1)
貿易都市として絶頂期にあった16世紀ヴェネツィアを舞台とするこの映画は、時代考証やシェイクスピアによる原作戯曲に基本的には忠実ながらも、ユダヤ商人であるシャイロックを中心人物に据えることで人種差別や法正義論など今日にも通じる戯曲の一側面を浮き彫りにさせ、現代的なテイストを存分にそなえた良作となっています。
主演のアル・パチーノはこの作品でその豪放かつ繊細な演技力を全編に渡って発揮し続けるのですが、今回はこの“アル・パチーノがシェイクスピア作品を演じる意味”をテーマに少し書いてみようと思います。とはいえそも彼のファンにとっては周知のごとく、アル・パチーノのシェイクスピアに対する情熱は尋常なものではありません。有名なところではたとえば、1996年のドキュメンタリー作品“リチャードを探して”。シェイクスピア戯曲中でも難解な“リチャード三世”を舞台に仕上げる過程を追ったこの作品で、彼は自ら製作を担いメガホンを採り、脚本を書いて主人公として出演もしています。
ではなぜ稀代のハリウッドスターがいま、シェイクスピアなのか。
現代のハリウッド映画を考えるうえで欠かせない要素の一つに、“アクターズ・スタジオ(The Actors Studio)”の存在があります。第二次大戦後エリア・カザンらによりNYに生まれたこの演劇学校は、リアリズムを志向する演劇理論“スタニスラフスキー・システム”(少しでも演劇論をかじった人ならまず知らないことはないといって良いものです)を採用し、同校出身者たちの出演する20世紀後半のハリウッド大作映画群を通じてその影響力を世界的なものとしました。日本では昨今NHK系列で深夜によく放送されている“フランシス・コッポラ自らを語る”、“アンジェリーナ・ジョリー自らを語る”というような番組シリーズでおなじみのかたも多いことでしょう。
その後独自の洗練を遂げた“アクターズ・スタジオ・メソッド”とでも言える方法論の最大の特色は、‘映像的に自然にみえる’演技の追及にあります。演技に関心のないかたには少し想像しにくいことかもしれませんが、‘カメラなしで見て自然な演技=映像で見て自然な演技’ではまったくないのですね。映像的にリアルに見えるためには、そう見せるために磨かれた特殊な技術が多々必要なわけです。ハリウッド界でも名優と目されるロバート・デ・ニーロやダスティン・ホフマンなどアル・パチーノと同世代の役者たちにしても、エドワード・ノートンやショーン・ペン、ラッセル・クロウ(“マスター・アンド・コマンダー”[7/8記事]主演)等々といった後続する才能豊かな役者たちにしてもおしなべて言えることは、この意味での技術の引き出しを多くもっているということです。
そしてこのメソッドから最も遠いところにあるのが、泣く子もだまる(眠る…)シェイクスピア戯曲群なんですね。なぜならシェイクスピア作品は主にその時代的な制約により、特撮技術も音響証明の類も一切のナレーションもなしに、もっぱら舞台役者のセリフだけで作品世界のエッセンスを全て表出しきれるように書かれているからです。にもかかわらずその深い訴求力によって、いまだに広汎な人々から支持され読み演じ継がれてもいます。映画俳優として円熟の域に達してなお自足しない人物が挑戦するには、まさに至上の高峰とも言える理由がここにあります。そしてこうした挑戦のなかにこそ、次なる表現領域の萌芽がありうることは言うまでもありません。
結果としてアル・パチーノの試みが功を奏しているのか否かについては、ご覧いただくみなさんの判断にお任せしたいと思います。ただ準主役級の3人にいずれも、シェイクスピア作品の舞台俳優としてもハリウッドの映画俳優としてもすでに実績のある役者たちが抜擢されたゆえの長所短所が見られること(うち一人は“ミッション”[8/5記事]の主演ジェレミー・アイアンズ)、アル・パチーノの脚本に対する深い読み込みが凄みをもって窺えるのはむしろ声にならない演技のほうであることは、判断材料として参考までに付記しておきます。
16世紀当時のヴェネツィア本島の雑踏やドゥッカーレ宮殿内部の様子を、CG処理等によりうまく再現している点も見どころの一つです。種々のトガリーヌやトーガ、色とりどりのサテンドレス等々の衣装群も非常に見ごたえがあります。監督は“イル・ポスティーノ”のマイケル・ラドフォード。「トリポリ沖で海賊に襲われたらしい」、「船がドーバー海峡で嵐に遭った」といったセリフからは、当時ヴェネツィアの商人たちにとってアドリア海の外こそが危険だらけの‘外海’としてイメージされていたことなどが想像されて興味深いものがあります。個々の出生地や民族宗教の違いに捉われつつも、コスモポリタンとしての“ヴェネツィア人”の意識に己の基盤を置こうとする登場人物たちの言動は、少し痛快でもありました。
"The Merchant of Venice (Il Mercante di Venezia)" by Michael Radford [+scr] / Al Pacino, Jeremy Irons, Joseph Fiennes, Lynn Collins / William Shakespeare [book author] / 131min / US, Italy, UK, Luxembourg / 2004
主演のアル・パチーノはこの作品でその豪放かつ繊細な演技力を全編に渡って発揮し続けるのですが、今回はこの“アル・パチーノがシェイクスピア作品を演じる意味”をテーマに少し書いてみようと思います。とはいえそも彼のファンにとっては周知のごとく、アル・パチーノのシェイクスピアに対する情熱は尋常なものではありません。有名なところではたとえば、1996年のドキュメンタリー作品“リチャードを探して”。シェイクスピア戯曲中でも難解な“リチャード三世”を舞台に仕上げる過程を追ったこの作品で、彼は自ら製作を担いメガホンを採り、脚本を書いて主人公として出演もしています。
ではなぜ稀代のハリウッドスターがいま、シェイクスピアなのか。
現代のハリウッド映画を考えるうえで欠かせない要素の一つに、“アクターズ・スタジオ(The Actors Studio)”の存在があります。第二次大戦後エリア・カザンらによりNYに生まれたこの演劇学校は、リアリズムを志向する演劇理論“スタニスラフスキー・システム”(少しでも演劇論をかじった人ならまず知らないことはないといって良いものです)を採用し、同校出身者たちの出演する20世紀後半のハリウッド大作映画群を通じてその影響力を世界的なものとしました。日本では昨今NHK系列で深夜によく放送されている“フランシス・コッポラ自らを語る”、“アンジェリーナ・ジョリー自らを語る”というような番組シリーズでおなじみのかたも多いことでしょう。
その後独自の洗練を遂げた“アクターズ・スタジオ・メソッド”とでも言える方法論の最大の特色は、‘映像的に自然にみえる’演技の追及にあります。演技に関心のないかたには少し想像しにくいことかもしれませんが、‘カメラなしで見て自然な演技=映像で見て自然な演技’ではまったくないのですね。映像的にリアルに見えるためには、そう見せるために磨かれた特殊な技術が多々必要なわけです。ハリウッド界でも名優と目されるロバート・デ・ニーロやダスティン・ホフマンなどアル・パチーノと同世代の役者たちにしても、エドワード・ノートンやショーン・ペン、ラッセル・クロウ(“マスター・アンド・コマンダー”[7/8記事]主演)等々といった後続する才能豊かな役者たちにしてもおしなべて言えることは、この意味での技術の引き出しを多くもっているということです。
そしてこのメソッドから最も遠いところにあるのが、泣く子もだまる(眠る…)シェイクスピア戯曲群なんですね。なぜならシェイクスピア作品は主にその時代的な制約により、特撮技術も音響証明の類も一切のナレーションもなしに、もっぱら舞台役者のセリフだけで作品世界のエッセンスを全て表出しきれるように書かれているからです。にもかかわらずその深い訴求力によって、いまだに広汎な人々から支持され読み演じ継がれてもいます。映画俳優として円熟の域に達してなお自足しない人物が挑戦するには、まさに至上の高峰とも言える理由がここにあります。そしてこうした挑戦のなかにこそ、次なる表現領域の萌芽がありうることは言うまでもありません。
結果としてアル・パチーノの試みが功を奏しているのか否かについては、ご覧いただくみなさんの判断にお任せしたいと思います。ただ準主役級の3人にいずれも、シェイクスピア作品の舞台俳優としてもハリウッドの映画俳優としてもすでに実績のある役者たちが抜擢されたゆえの長所短所が見られること(うち一人は“ミッション”[8/5記事]の主演ジェレミー・アイアンズ)、アル・パチーノの脚本に対する深い読み込みが凄みをもって窺えるのはむしろ声にならない演技のほうであることは、判断材料として参考までに付記しておきます。
16世紀当時のヴェネツィア本島の雑踏やドゥッカーレ宮殿内部の様子を、CG処理等によりうまく再現している点も見どころの一つです。種々のトガリーヌやトーガ、色とりどりのサテンドレス等々の衣装群も非常に見ごたえがあります。監督は“イル・ポスティーノ”のマイケル・ラドフォード。「トリポリ沖で海賊に襲われたらしい」、「船がドーバー海峡で嵐に遭った」といったセリフからは、当時ヴェネツィアの商人たちにとってアドリア海の外こそが危険だらけの‘外海’としてイメージされていたことなどが想像されて興味深いものがあります。個々の出生地や民族宗教の違いに捉われつつも、コスモポリタンとしての“ヴェネツィア人”の意識に己の基盤を置こうとする登場人物たちの言動は、少し痛快でもありました。
"The Merchant of Venice (Il Mercante di Venezia)" by Michael Radford [+scr] / Al Pacino, Jeremy Irons, Joseph Fiennes, Lynn Collins / William Shakespeare [book author] / 131min / US, Italy, UK, Luxembourg / 2004
Job Description 3: 宣教師 【ミッション】
2006年8月5日 就職・転職 コメント (6)
木製の十字架へ磔にされた無名の神父が河に流され、そのままイグアスの瀑布に呑み込まれていくシーンから始まるこの作品は、18世紀半ばの南米奥地、パラナ川上流域(現ブラジル-アルゼンチン国境域)を舞台とします。大航海時代のさなかにあってそこではスペインとポルトガルが奴隷貿易の利権を競い、イエズス会が布教の根を張っています。
映画前半では対立する二人の主人公、誠実に布教活動へ従事する神父ガブリエル(byジェレミー・アイアンズ)と原住民を冷徹に狩っていく奴隷商人メンドーサ(byロバート・デ・ニーロ)は、作品後半に入ると教会と政府の意向に抗い互いに手を結びます。そしてこの作品において語り部となるイエズス会本部から派遣されてきた枢機卿(byレイ・マカナリー)は、政治的な決定においては本国の事情を優先して原住民の幸福と平安を犠牲にする施策をとるも、原住民に寄り添おうとする主人公たちを心情的には次第に理解してゆきます。
この作品の公開年にあたる1986年といえばポスト・コロニアル思想が大衆芸術の分野へもようやく浸透を始める頃ゆえ仕方ないとも言えるのでしょうが、植民地政治や奴隷制度への義憤は描かれても、イエズス会の布教行為そのものに対してはまるで無批判な点は2000年代現在の目から見ればどうにも不自然に映ります。けれども改宗し定住した部族により築かれた社会が一時的にとはいえ共産制に行き着いたとして描かれる点や、宣教師の存在が結局は原住民社会の破滅を防げなかったとするプロットにより、ぎりぎりのラインでPC的な誹りを免れているとは言えるのかも。デ・ニーロ扮するメンドーサが一度は捨てた武器を再度手にとる決意ののち祝福を請うシーンでの、J・アイアンズ演じる神父ガブリエルによるセリフは印象に深く残るところです。下記引用します。
‘私が祝福を施さずとも、あなたの行ないが正しいなら神が祝福するだろう。また行ないが過ちなら、私が祝福しても無意味である。ただ私はおもう。もし力が正しいなら、この世に愛は要らなくなる’
出演者では他に、いまやすっかり大御所俳優の仲間入りを果たしたリーアム・ニーソンが若い神父役で登場しています。監督のローランド・ジョフィは他に“キリング・フィールド”(1984)や“シティ・オブ・ジョイ”(1992)、“スカーレット・レター”(1995)など。前二作はこの作品と並んで時代を画した名作(私見)ですが、こうして並べてみると近現代史物に強いことがよくわかりますね。脚本のロバート・ボルトは“アラビアのロレンス”でも脚本を担当、確かに原住民へのリスペクトのある(この年代には稀な)まなざしには通底する部分も感じます。エンニオ・モリコーネによる音楽もいい。
念のため付記しておけば、"mission"の語には「使命,任務」等の他に「宣教,伝道」の意があります。日本を含む非欧米諸国のカトリック教会では "missionaries church" という英語表記をよく目にしますね。つまり宣教会。
"The Mission" by Roland Joffe / Robert Bolt [scr] / David Puttnam [prd.] / Robert De Niro, Jeremy Irons, Ray McAnally, Liam Neeson, Aidan Quinn / Ennio Morricone [music] / 125min / UK / 1986
映画前半では対立する二人の主人公、誠実に布教活動へ従事する神父ガブリエル(byジェレミー・アイアンズ)と原住民を冷徹に狩っていく奴隷商人メンドーサ(byロバート・デ・ニーロ)は、作品後半に入ると教会と政府の意向に抗い互いに手を結びます。そしてこの作品において語り部となるイエズス会本部から派遣されてきた枢機卿(byレイ・マカナリー)は、政治的な決定においては本国の事情を優先して原住民の幸福と平安を犠牲にする施策をとるも、原住民に寄り添おうとする主人公たちを心情的には次第に理解してゆきます。
この作品の公開年にあたる1986年といえばポスト・コロニアル思想が大衆芸術の分野へもようやく浸透を始める頃ゆえ仕方ないとも言えるのでしょうが、植民地政治や奴隷制度への義憤は描かれても、イエズス会の布教行為そのものに対してはまるで無批判な点は2000年代現在の目から見ればどうにも不自然に映ります。けれども改宗し定住した部族により築かれた社会が一時的にとはいえ共産制に行き着いたとして描かれる点や、宣教師の存在が結局は原住民社会の破滅を防げなかったとするプロットにより、ぎりぎりのラインでPC的な誹りを免れているとは言えるのかも。デ・ニーロ扮するメンドーサが一度は捨てた武器を再度手にとる決意ののち祝福を請うシーンでの、J・アイアンズ演じる神父ガブリエルによるセリフは印象に深く残るところです。下記引用します。
‘私が祝福を施さずとも、あなたの行ないが正しいなら神が祝福するだろう。また行ないが過ちなら、私が祝福しても無意味である。ただ私はおもう。もし力が正しいなら、この世に愛は要らなくなる’
出演者では他に、いまやすっかり大御所俳優の仲間入りを果たしたリーアム・ニーソンが若い神父役で登場しています。監督のローランド・ジョフィは他に“キリング・フィールド”(1984)や“シティ・オブ・ジョイ”(1992)、“スカーレット・レター”(1995)など。前二作はこの作品と並んで時代を画した名作(私見)ですが、こうして並べてみると近現代史物に強いことがよくわかりますね。脚本のロバート・ボルトは“アラビアのロレンス”でも脚本を担当、確かに原住民へのリスペクトのある(この年代には稀な)まなざしには通底する部分も感じます。エンニオ・モリコーネによる音楽もいい。
念のため付記しておけば、"mission"の語には「使命,任務」等の他に「宣教,伝道」の意があります。日本を含む非欧米諸国のカトリック教会では "missionaries church" という英語表記をよく目にしますね。つまり宣教会。
"The Mission" by Roland Joffe / Robert Bolt [scr] / David Puttnam [prd.] / Robert De Niro, Jeremy Irons, Ray McAnally, Liam Neeson, Aidan Quinn / Ennio Morricone [music] / 125min / UK / 1986
この作品の続編となる『パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト』が国内の映画館できのうから封切られましたね。それにちなんで。
以前の記事でこの映画について“ディズニーランドのアトラクションを映像化したに過ぎない”と述べましたが、これは酷評の意図のみによるものではなく、実際この作品は Walt Disney Pictures による製作なんですよね。本家ディズニーランド(in US)のアトラクションには、ジョニー・デップ演じる主人公ジャック・スパローを模した人形も登場しているようです。
こうしたディズニーランド本体の集客戦略とも絡んだ映画製作の方向性は、作品の中身にも当然強い影響を与えているわけですが、そうした観点も踏まえてこの映画の見どころを以下のようにまとめてみます。
■親しみのもてるアクション/見世物小屋性
ヒーローとしてのジャック・スパロー像は、もう一人の主人公である刀鍛治の青年(byオーランド・ブルーム)の眼差しを通して描かれるのですが、この二人が鍛治屋の工房で初めて顔を合わした際の格闘シーンに顕著なように、作品中に登場するアクションは超絶的な身体妙技を見せつける種の演出を施されることがありません。
これには児童層を観客対象に含む作品だから、という以上に、感情移入の契機をそのような直接的な身体性へ求めたからという理由が大きいように思います。映画後半の完全CGにより展開する幽霊海賊たちとの格闘シーンですら、不死であることがむしろコミカルに描かれているのもおそらくこのためでしょう。ここでは“ワイヤーアクション”や“スローモーション弾除け”はむしろ余計なんですね。『パイレーツ・オブ・カリビアン』は“ビッグ・サンダー・マウンテン”のようなジェット・コースター系ではなく、あくまで“アマゾン・クルーズ”や“ホーテッド・マンション”のような見世物系作品として製作される必要があったわけです。
こうした傾向は海賊島トルトゥーガのシークエンスなどにもよく表れており、アトラクションのカートに座った乗客の視線同様、カメラは海賊島の歓楽街の様子をなめ回すように進んで行きますね。DOLで実装される海賊島も、ビジュアル的にはこのシーンがある程度モデルになる可能性は高いかなと思っています。海賊島のヴィジュアルイメージの源泉って、それほど多くはありませんからね。
■ジェリー・ブラッカイマーによる製作
ハリウッドメジャーによる大作映画群を、インディーズ系やヨーロピアンシネマの作品群と質的に同列なものとして語るひとが時折いるけれど、わたし個人はこうした視点で現在のハリウッド映画を語ることはあまり意味がないだろうと思っています。つまり、この手の娯楽大作映画の市場が“統計的に”あぶり出す最大多数の観客にとって映画とはすでに、ウーファーをも使用した多層的な音響効果や心地良いリラクゼーションシートといったサービスの行き届いた環境下で楽しむイリュージョン装置に他ならず、映画作品本体の質は‘趣味’の選択を左右する最終的なソフトの微細な差異としてしか機能しない。その意味では文字通り、現在のハリウッド映画は従来の通念における“映画”よりむしろ“アトラクション”に近いんですね。
そうした流れの権化のようなプロデューサーがジェリー・ブラッカイマーなわけで、彼の製作した映画を楽しむコツは、ストーリーの意味やら辻褄合わせなどにとらわれず、そのお金のかかった視覚的イリュージョンにひたすら身を委ね切ることとまずは言ってよいでしょう。主人公が二人でフリゲートクラスの艦船を乗っ取るシーンや幽霊たちが海底からヒロインのいる船に襲撃をかけるシーンなど、DOLプレイヤーにとっても見ごたえのあるシーンは多いですよね。カメラ撮りも上手いです。
この映画はすでに観たひとも多いでしょうから、角度を少し変えて書いてみました。90年代から加速しているハリウッドメジャー統廃合の流れのなか、アニメ専業からの脱却を図る Walt Disney Pictures にとってこの作品が興行的に成功をおさめたことの意味合いは非常に大きいものだったと想像できます。すでに三作目が製作中のようですが、とりあえず第一作、まだ観ていないかたにはオススメできます。わたしは来週中にも二作目を観に映画館へ出かける予定です。夏休みな子供たちにまぎれて。(笑)
"Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl" by Gore Verbinski / Jerry Bruckheimer [prd.] / Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley / 143min / US / 2003
以前の記事でこの映画について“ディズニーランドのアトラクションを映像化したに過ぎない”と述べましたが、これは酷評の意図のみによるものではなく、実際この作品は Walt Disney Pictures による製作なんですよね。本家ディズニーランド(in US)のアトラクションには、ジョニー・デップ演じる主人公ジャック・スパローを模した人形も登場しているようです。
こうしたディズニーランド本体の集客戦略とも絡んだ映画製作の方向性は、作品の中身にも当然強い影響を与えているわけですが、そうした観点も踏まえてこの映画の見どころを以下のようにまとめてみます。
■親しみのもてるアクション/見世物小屋性
ヒーローとしてのジャック・スパロー像は、もう一人の主人公である刀鍛治の青年(byオーランド・ブルーム)の眼差しを通して描かれるのですが、この二人が鍛治屋の工房で初めて顔を合わした際の格闘シーンに顕著なように、作品中に登場するアクションは超絶的な身体妙技を見せつける種の演出を施されることがありません。
これには児童層を観客対象に含む作品だから、という以上に、感情移入の契機をそのような直接的な身体性へ求めたからという理由が大きいように思います。映画後半の完全CGにより展開する幽霊海賊たちとの格闘シーンですら、不死であることがむしろコミカルに描かれているのもおそらくこのためでしょう。ここでは“ワイヤーアクション”や“スローモーション弾除け”はむしろ余計なんですね。『パイレーツ・オブ・カリビアン』は“ビッグ・サンダー・マウンテン”のようなジェット・コースター系ではなく、あくまで“アマゾン・クルーズ”や“ホーテッド・マンション”のような見世物系作品として製作される必要があったわけです。
こうした傾向は海賊島トルトゥーガのシークエンスなどにもよく表れており、アトラクションのカートに座った乗客の視線同様、カメラは海賊島の歓楽街の様子をなめ回すように進んで行きますね。DOLで実装される海賊島も、ビジュアル的にはこのシーンがある程度モデルになる可能性は高いかなと思っています。海賊島のヴィジュアルイメージの源泉って、それほど多くはありませんからね。
■ジェリー・ブラッカイマーによる製作
ハリウッドメジャーによる大作映画群を、インディーズ系やヨーロピアンシネマの作品群と質的に同列なものとして語るひとが時折いるけれど、わたし個人はこうした視点で現在のハリウッド映画を語ることはあまり意味がないだろうと思っています。つまり、この手の娯楽大作映画の市場が“統計的に”あぶり出す最大多数の観客にとって映画とはすでに、ウーファーをも使用した多層的な音響効果や心地良いリラクゼーションシートといったサービスの行き届いた環境下で楽しむイリュージョン装置に他ならず、映画作品本体の質は‘趣味’の選択を左右する最終的なソフトの微細な差異としてしか機能しない。その意味では文字通り、現在のハリウッド映画は従来の通念における“映画”よりむしろ“アトラクション”に近いんですね。
そうした流れの権化のようなプロデューサーがジェリー・ブラッカイマーなわけで、彼の製作した映画を楽しむコツは、ストーリーの意味やら辻褄合わせなどにとらわれず、そのお金のかかった視覚的イリュージョンにひたすら身を委ね切ることとまずは言ってよいでしょう。主人公が二人でフリゲートクラスの艦船を乗っ取るシーンや幽霊たちが海底からヒロインのいる船に襲撃をかけるシーンなど、DOLプレイヤーにとっても見ごたえのあるシーンは多いですよね。カメラ撮りも上手いです。
この映画はすでに観たひとも多いでしょうから、角度を少し変えて書いてみました。90年代から加速しているハリウッドメジャー統廃合の流れのなか、アニメ専業からの脱却を図る Walt Disney Pictures にとってこの作品が興行的に成功をおさめたことの意味合いは非常に大きいものだったと想像できます。すでに三作目が製作中のようですが、とりあえず第一作、まだ観ていないかたにはオススメできます。わたしは来週中にも二作目を観に映画館へ出かける予定です。夏休みな子供たちにまぎれて。(笑)
"Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl" by Gore Verbinski / Jerry Bruckheimer [prd.] / Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley / 143min / US / 2003
海洋物の映画と聞いて、まずこの作品を思い浮かべる大航海時代のプレイヤーはきっと少なくないかもしれません。まだ観ていないかたには一押し。帆船の表現がリアルだという評もある“パイレーツ・オブ・カリビアン”が、ディズニーランドのアトラクションを映画化したに過ぎないことがよくわかるはずです。
1805年ドーバー沖を航行する英海軍のフリゲート船H.M.S.サプライズが、カレーを出航したフランス私掠船アケロン号を索敵/交戦ののち、延々とラテンアメリカまで追跡していくというストーリーは、おもに下記3種のシークエンスにより展開されます。
まず帆船描写。提督、航海士、見張りに立つ准士官、船大工、船医らがこの時代、どのような秩序と手順をもってふだんの航海をこなし、嵐を切り抜け、海戦に臨んでいたのかがうまく再現されています。フルリグドセイルの使用により最大戦速を出すシーン、海上で損壊部を修繕していくシーン、甲板上の敵船員の殺傷とメインマストの破損を目的とした至近距離の仰角射撃に始まり、コヴァースによる敵船拘束後の白兵戦へと続く海戦シーンなど、見どころは多いです。
そして乗組員のセリフによる背景描写。船長室で交わされる提督と船医による互いの職分を超えた友情、晩餐の場で俎上にあがる英海軍の英雄ネルソン提督を巡る逸話、二層甲板に流線形の船体構造を備えた敵戦列艦の模型を巡る士官との会話、等々。個々の会話が、18世紀半ばから19世紀初頭にかけての西欧の航海状況を反映しており興味が尽きることはありません。
最後に作品後半の舞台となる、ガラパゴス諸島の自然描写。提督の親友であり、博物学者でもある船医がここでの主役となります。新種の植生、未知の生態へ次々と触れるうちに沸いてきた、自分がこれらの生物群の第一発見者になったのだという興奮、学者としての使命感と、軍属として優先すべき任務とのあいだに生じてゆく葛藤はとても鮮明で痛ましいものがあります。ハリウッドの商業映画がガラパゴスを撮ったこと自体がまず、稀有な達成。
ここでDOLに引き付けた余談を一つ。システム的な区別が恣意的なため論議を呼びがちな軍人/海賊の境界について、劇中に年配の船夫らが若い士官に説く形で印象的な会話がなされる場面があります。簡単に言えば、敵対国の商船が目の前を素通りするのを指をくわえて見ているのは国家に仕える軍人として失格だけれど、被害に遭う商船の側からみれば襲ってくる相手はすべて海賊野郎という話。つまり“軍人”は身分で“海賊”はレッテルなので、同じレヴェルで語ること自体に一定のバイアスがかかっているということ。ここらへんがきっちりと整理されればぐだぐだなことを言うひとも減って、このゲームでの対人プレイはきっとより楽しくなりますよね。
ちなみにこの映画の副題は“The Far Side of the World”。「船長、世界の果てですぜ、針路を変えさせてもらいやす」という事態が作品中でも起こってます。ガラパゴスがどう実装されるのかは、個人的に今夏の追加パックで一番楽しみにしているところ。ガラパゴス上陸地点、カム。
"Master and Commander: The Far Side of the World" by Peter Weir [+scr] / Russell Crowe, Paul Bettany / William Sandell [prd. design] / Patrick O’Brian [book author] / 139min / US / 2003
1805年ドーバー沖を航行する英海軍のフリゲート船H.M.S.サプライズが、カレーを出航したフランス私掠船アケロン号を索敵/交戦ののち、延々とラテンアメリカまで追跡していくというストーリーは、おもに下記3種のシークエンスにより展開されます。
まず帆船描写。提督、航海士、見張りに立つ准士官、船大工、船医らがこの時代、どのような秩序と手順をもってふだんの航海をこなし、嵐を切り抜け、海戦に臨んでいたのかがうまく再現されています。フルリグドセイルの使用により最大戦速を出すシーン、海上で損壊部を修繕していくシーン、甲板上の敵船員の殺傷とメインマストの破損を目的とした至近距離の仰角射撃に始まり、コヴァースによる敵船拘束後の白兵戦へと続く海戦シーンなど、見どころは多いです。
そして乗組員のセリフによる背景描写。船長室で交わされる提督と船医による互いの職分を超えた友情、晩餐の場で俎上にあがる英海軍の英雄ネルソン提督を巡る逸話、二層甲板に流線形の船体構造を備えた敵戦列艦の模型を巡る士官との会話、等々。個々の会話が、18世紀半ばから19世紀初頭にかけての西欧の航海状況を反映しており興味が尽きることはありません。
最後に作品後半の舞台となる、ガラパゴス諸島の自然描写。提督の親友であり、博物学者でもある船医がここでの主役となります。新種の植生、未知の生態へ次々と触れるうちに沸いてきた、自分がこれらの生物群の第一発見者になったのだという興奮、学者としての使命感と、軍属として優先すべき任務とのあいだに生じてゆく葛藤はとても鮮明で痛ましいものがあります。ハリウッドの商業映画がガラパゴスを撮ったこと自体がまず、稀有な達成。
ここでDOLに引き付けた余談を一つ。システム的な区別が恣意的なため論議を呼びがちな軍人/海賊の境界について、劇中に年配の船夫らが若い士官に説く形で印象的な会話がなされる場面があります。簡単に言えば、敵対国の商船が目の前を素通りするのを指をくわえて見ているのは国家に仕える軍人として失格だけれど、被害に遭う商船の側からみれば襲ってくる相手はすべて海賊野郎という話。つまり“軍人”は身分で“海賊”はレッテルなので、同じレヴェルで語ること自体に一定のバイアスがかかっているということ。ここらへんがきっちりと整理されればぐだぐだなことを言うひとも減って、このゲームでの対人プレイはきっとより楽しくなりますよね。
ちなみにこの映画の副題は“The Far Side of the World”。「船長、世界の果てですぜ、針路を変えさせてもらいやす」という事態が作品中でも起こってます。ガラパゴスがどう実装されるのかは、個人的に今夏の追加パックで一番楽しみにしているところ。ガラパゴス上陸地点、カム。
"Master and Commander: The Far Side of the World" by Peter Weir [+scr] / Russell Crowe, Paul Bettany / William Sandell [prd. design] / Patrick O’Brian [book author] / 139min / US / 2003